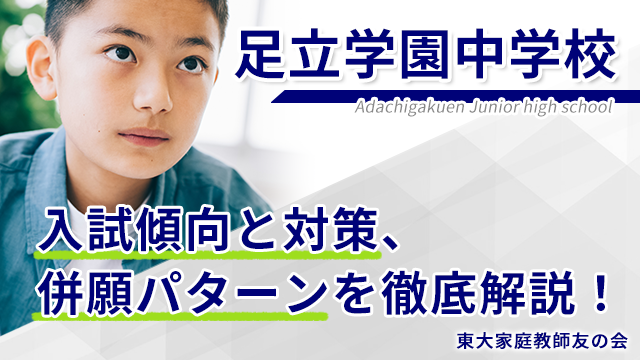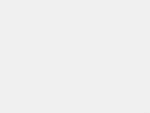1. 足立学園中学校とは?

1929年創立で、北千住駅から徒歩1分の好立地にある足立学園中学校。中学1年生の段階から、難関国公立大学を目指す「特別クラス」を設置。
朝7時から使用できる、都内最大級の自習室を完備しており、先生方の面倒見は良く、学習環境は整っていると言えるでしょう。慶応大学・早稲田大学などの難関校への指定校推薦枠も保持しております。
希望者ではありますが、海外への留学プログラムが多数存在し、中でもアフリカ・スタディツアーは、非常に稀なプログラムです。中学3年生~高校2年生までを対象にしたプログラムで、タンザニアにてキリマンジャロの森林破壊、コーヒーファームやサファリ体験など、ここでしか味わえない経験をすることが出来ます。
2. 足立学園中学校の入試傾向について

第一回~第四回一般入試は、算数・国語・理科・社会の四科目、もしくは、算数・国語の二科目です。 試験時間が算数50分・国語50分・理科30分・社会30分、配点は算数100点・国語100点・理科50点・社会50点です。 また、第一回~第四回特別奨学生入試は、算数・国語・理科・社会の四科目となり、試験時間・配点は一般入試と一緒です。
この他、志入試と、適性検査型特別奨学生入試があります。 志入試は、第一回一般入試と同じ日時で始まります。試験科目は算数・国語・面接です。 算数・国語の試験時間・配点は一般入試と同じです。 適性検査型特別奨学生入試は、第一回特別奨学生入試と同じ日時で始まります。試験科目は適性検査ⅠⅡⅢです。
特別奨学生入試は、一般入試と比べ偏差値が10程高いため、問題もその分難しくなっています。 特別奨学生入試の合格は、①「特別クラス」学費免除合格②「特別クラス」合格③「一般クラス」合格の3パターンに分かれています。
一般入試も特別奨学生入試も、問題文が長く難しく見えることがあります。 しかし、問われていることは基本的な事が多いです。文章の長さに圧倒されない様にして下さい。 点差のつきやすい科目は、算数・国語です。両方とも、しっかり勉強時間を確保して対応していきましょう。
①算数
例年、大問5、6題の出題です。大問1番が計算問題、大問2番が小問集合、大問3番以降が単元別の問題となっています。後半の問題は、解法を書く欄があります。式・やり方が採点官に伝わるように書けるよう練習しましょう。以上の傾向は、一般入試、特別奨学生入試で変わりありませんが、特別奨学生入試の方が問題は難しめとなっています。
大問1番は、4.5題の計算問題で、整数・小数・分数の計算や、逆数の計算が出題されています。 大問2番の小問集合は、基本的な問題です。この問題までを完答したい所です。 大問3番以降は、数の問題・図形・速さ・思考力問題が頻出です。
数の問題は、規則性・場合の数が頻出です。やや複雑な問題も出題されています。図形は、平面図形が中心です。相似・面積・角度・図形の移動に関する問題が頻出です。速さは、旅人算が中心です。約数・倍数と絡めた問題も見受けられます。 思考力問題は、足立学園中学校の大きな特徴です。文章・資料を読み込み、状況を把握して答える問題です。適性検査で出題されるような問題も見受けられます。2024年度第一回一般入試でも、駐車場に関する思考力問題が出題されました。しっかりと読み込み、具体的に考えなければ、ミスが発生する問題でしたので、差がついたと思われます。過去問でしっかり演習し、慣れていきましょう。
②国語
例年、大問3題の出題です。これは、一般入試・特別奨学生入試で変わりありません。
大問1番が漢字です。読み書きどちらも出題されます。特別奨学生入試は、読み書きのうち、書きのみの出題が多いです。 大問2.3番は、物語文と説明文が1題ずつ出題されます。語彙・抜き出し・接続詞・正誤選択・記述など総合的に出題されています。他校と比較し、記述問題は少なめで、抜き出し問題が多いのが特徴です。要旨に関わる部分が抜き出し問題になっている事も多いですから、普段から要旨把握に努めましょう。また、足立学園中学校の抜き出し問題は記述問題が抜き出し問題に変わっただけ、という捉え方が出来ます。ですから、記述問題だとしたら、どこの部分を根拠とするか、という発想で解くと良いと思われれます。2024年度も、例年同様抜き出し問題が多数出題されましたので、以上を念頭に置いて、学習を進めて下さい。
③理科
例年、大問3〜5題の出題です。物理が最も出題されており、思考を要する問題が出題されます。足立学園中学校の大きな特徴でしょう。その他の化学・生物・地学に関しましては、比較的知識問題が多く、時事的な問題が出題される事もあります。計算問題が出題される事もある点には注意しましょう。これらの傾向は、一般入試・特別奨学生入試で変わりありません。
足立学園の特徴である物理ですが、単元としては満遍なく出題されており、主に計算問題を伴う考察問題が出題されます。高校物理で習うような内容を、説明を加えながら設問としている事もあり、難しめの問題と言えるでしょう。2024年度第一回一般型では、物理の問題が2題出題され、一つは現象理解を問う振り子に関する問題、もう一つは音速に関する計算問題でした。どちらも、単なる暗記では解けない問題でしたから、差がついたと考えられます。足立学園中学校では、物理に力を入れて取り組む必要があります。
④社会
例年、大問3題の出題で、地理・歴史・公民・時事問題が満遍なく出題されます。ユニークな問題が出題されており、例えば有名な政治家や活動家の顔写真を選ぶ問題や、有名な書籍に関する地理の問題、箱根駅伝の通るルートなど、一般常識を問う問題が出題されています。勉強だけではなく、日頃から幅広い視野を持って生活しているかを問う問題と言えるでしょう。
地理・歴史・公民全体として、設問が長い場合でも、基本的な内容が問われていますので、見た目に圧倒されないようにして下さい。端的に何が問われているかを考えて答えを出して下さい。問われている事は一問一答的な内容です。
時事問題は、よく出題されています。ここ5年程度の内容は学習しておいた方が良いでしょう。2024年度第一回一般型では、先にご説明しました、顔写真問題が出題されました。今回は、岸田総理大臣と、イギリスのリシ・スナク首相の顔写真を選ぶ問題でした。顔写真問題は頻出ですから、有名な日本の政治家や、海外の首相・大統領・活動家等の顔写真は対策しておきましょう。日本の首相や、政党の党首のプロフィールも確認すると良いでしょう。
⑤適性検査
例年、適性検査はⅠ〜Ⅲまであり、Ⅰは国語の問題、Ⅱは理科を題材にした算数との複合問題、Ⅲ番は算数の思考力問題です。
Ⅰは、長文を題材にした国語の問題で、物語文・説明文どちらか1題が出題されます。記述問題が多く、作文問題も出題されています。2024年度第一回特別奨学生入試適性検査型でも、例年通り、最後の設問で350字以上400字以内の作文問題が出題されました。これだけの長さの作文問題は、付け焼き刃では対応出来ません。ですから、しっかり対策をされていた生徒様とそうでない生徒様では、大きく差が開いたものと思われます。
Ⅱは、理科、とりわけ物理・化学分野を中心とした題材をベースに、算数的な思考を合わせた問題となっています。理系的な素養があるかどうかを問う問題で、理科を暗記ではなく、現象理解出来ているか、及び算数の基本的な考え方が身についているかが問われます。
Ⅲは、算数の思考力問題で、じっくりと考えて答えを出す問題が出題されています。図形問題が出題されることが多く、一部資料問題なども出題されています。解法暗記ではなく、生徒様自身でしっかりと考える習慣付けが出来ているか、多面的に物事を捉えることが出来るか、が試されています。
⑥問題の形式等が似ている学校は?
全体的な傾向を考えますと、佼成学園中学校と似ているかと思われます。算数の問題で思考力問題が出題されることなど、参考になる部分が多いでしょう。特に、奨学生入試の生徒様にマッチする部分が多いと思います。
3. 足立学園中学校を受ける際の併願パターンは?

①1月受験校
|
城西川越中学校・埼玉平成中学校・城北埼玉中学校・西武学園文理中学校
|
1月は練習として、城西川越中学校・埼玉平成中学校・城北埼玉中学校・西武学園文理学園中学校が挙げられます。 これらの学校で、しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
|
午前:足立学園中学校(一般・1次)(志)
午後:足立学園中学校(特別奨学生・1次)
|
午前入試は足立学園中学校(一般・1次)(志)で決まりです。
午後入試も足立学園中学校(特別奨学生・1次)で決まりでしょう。
尚、午前入試で志入試に合格された場合、足立学園中学校への入学が必須となります。
③2月2日
|
午前:足立学園中学校(一般・2次)・佼成学園中学校(一般・2次)
午後:足立学園中学校(特別奨学生・2次)
|
午前・午後共に足立学園中学校で決まりです。しかし、1日に一般入試に合格している場合は、 佼成学園中学校(一般・2次)を受験するか、もしくは休養に充てるのが良いでしょう。
④2月3日
|
午前:足立学園中学校(一般・3次)・佼成学園中学校(一般・3次)
午後:足立学園中学校(特別奨学生・3次)
|
3日も基本的には足立学園中学校で決まりです。前日同様、一般入試で合格していれば、 佼成学園中学校(一般・3次)を受験するか、休養に充てましょう。
⑤2月4日
|
午前:足立学園中学校(一般・4次)
午後:足立学園中学校(特別奨学生・4次)・国士舘中学校(4次)
|
4日で最後の日程です。足立学園中学校合格に向けて頑張りましょう。
午後の特別奨学生入試が厳しいとご判断された場合は、国士舘中学校(4次)を受験されるのも手だと思われます。
4. 足立学園中学校の受験対策方法
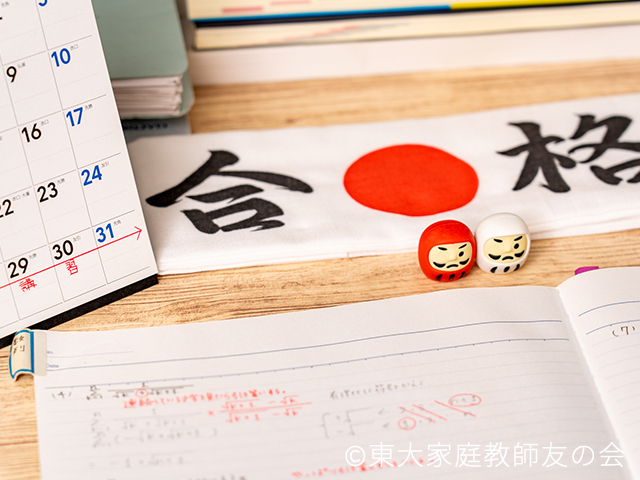
足立学園中学校は、基本~標準的な問題が多いため、基礎の定着が重要となります。
差がつきやすい算数・国語を中心に学習を進めるのが良いでしょう。
算数は、計算を含めた基礎を徹底して取りこぼしが無いようにすることが大切です。
単元としては、数の問題・図形・速さ・思考力問題に力を入れましょう。
国語は、漢字・語彙の学習を継続的に行うことと、毎日の読書が必須です。
要約を練習して、文章の言いたいことを把握出来るようにしていきましょう。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくと良いでしょう。
足立学園中学校は、小問を含めて比較的満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。
また、計算力も必須です。足立学園中学校では、計算問題が必ず出題されます。
速く、正確に計算が出来るように毎日トレーニングをして下さい。
国語も、カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにして下さい。
文章を読んでから、要旨を50字程度で書いていくのが、将来の足立学園中学校の受験対策には良いでしょう。
文章を書くという意味では、日記も効果的です。保護者様が添削してあげると良いでしょう。 少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行いたい所です。
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
また、足立学園中学校の入試問題に対応するには、暗記だけでなく、身の回りの現象理解がとても大切です。
これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察して下さい。 例えば、夕焼けはどうやって起きるのか、など身近な内容について、考察してみると良いでしょう。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。 基本的な暗記事項は、この時期にしっかり覚えてしまいましょう。 ニュースや新聞を見る習慣付けが出来ると良いと思います。 また、政治・経済・スポーツ・アニメ・特集など様々なジャンルに興味を持つようにしましょう。
(2)小学五年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにして下さい。
少し時間が経ってしまうと、出来なくなってしまう事も多いです。
全体的に基本〜標準的な問題をしっかり解けるようにしていきましょう。
計算練習も忘れずに行って下さい。
国語は、物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。
生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を50字程度で書く練習をしましょう。
書きたいポイントを箇条書きにしてから、記述するのが良いでしょう。
また、正誤選択問題など答える時には、傍線部だけではなく、本文全体を踏まえて答える癖付けをしていきましょう。
読書・日記は継続的に行い、漢字・語彙も忘れずに行って下さい。
理科は、物理・化学などの計算問題が始まります。基本~標準的な問題が解けるように演習しましょう。
また、引き続き、単なる暗記ではなく、何故身近な現象が起きるのか、考えてみましょう。
わからない事は、調べつつ、理解を深めて下さい。
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記を行って下さい。
主な出来事が何時代なのか、判断できるまで反復して下さい。主要な事項の年号暗記も必要です。
時間を見ながら地理の復習も適宜行えると良いでしょう。
ニュース・新聞は引き続き、見る様にしていきましょう。政治家や首相の顔を見慣れておくと良いでしょう。
(3)小学六年生(4月〜6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
特に、数の問題・図形・速さに不安がある場合は、この時期に克服したい所です。
思考力問題対策として、少し複雑な問題でも時間を掛けて、じっくりと解くようにしましょう。
特別奨学生入試を受ける生徒様は過去問を解き始めましょう。
国語は、標準的な文章で、設問の解き方を確認して下さい。
読書・要約・日記を継続していくと良いでしょう。
算数同様、特別奨学生入試を受ける生徒様は過去問を解いてみましょう。
理科は、引き続き、身の回りの事柄への理解を深めつつ、暗記も行いましょう。
計算問題も、基本~標準問題を演習していきましょう。
特に、物理単元については、力を入れて学習をしていきましょう。
社会は、公民が始まります。基本事項をしっかり暗記出来る様にしていきましょう。 時間を見つけて、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。
(4)小学六年生(7月〜8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。一般入試のみ受験の生徒様も同様です。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
基本~標準問題演習として「ベストチェック」(日能研)を行うのは良いと思います。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
計算練習も、毎日5題でも良いですから、引き続き継続して下さい。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。一般入試のみの生徒様も同様です。
漢字・語彙については、この夏休みで固めていきましょう。
理科も、過去問を3回分解きましょう。理解不足の所は、基本に戻って理解をしていきましょう。
計算問題については、引き続き基本~標準的な問題の対策をしておいた方が良いでしょう。
物理については、少し難しい問題にも手を出してみましょう。
社会も、過去問を3回分行いましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強して行きましょう。 引き続き、ニュース・新聞を見て、時事的な内容を知っていくと良いでしょう。また、ここ5年位の時事問題についても学習していきましょう。
(5)小学六年生(9月~11月)
算数は、過去問中心になりますが、特に解き直しに力を入れて下さい。
数の問題・図形・速さ・思考力問題に力を入れて学習して下さい。思考力問題は、適性試験の問題も参考になります。
特別奨学生入試を受験予定の生徒様は、「プラスワン」「ステップアップ」(東京出版)といった問題集を行うと良いでしょう。
基礎を重視して取り組んで下さい。
国語は、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なって下さい。
過去問の解き直しも行いましょう。
この時期でも、読書・要約・日記は継続して頂くと良いでしょう。
理科も、やはり過去問を中心に行っていきます。
過去問で出題されていた内容については、暗記だけでなく、理解が出来ているか、保護者様で確認して頂くと良いと思います。
社会同様、ニュース・新聞で時事的な内容を知っていきましょう。
計算問題を中心に、解き直しも忘れずに行って下さい。
社会も、過去問は解きますが、それと同時に、全般的な復習も忘れずに行って下さい。
この時期から「日本のすがた」(最新版)を利用した統計の勉強や、大手塾から出版されている「重大ニュース」を用いた時事対策を本格的に始めましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問の解き直し、数の問題・図形・速さ・思考力問題を含めた全般的な定着を行いましょう。
この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。
思考力問題の問題数が不十分でしたら、公立中高一貫校の適性試験問題が参考になります。
基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、復習しましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、今まで習ってきた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認して下さい。
計算問題も過去問の復習を中心に、解けるまで繰り返しましょう。物理については、特に時間を取って復習をしましょう。
社会は、全般的な復習をしていきましょう。一見、受験に関係ないような知識も大事だったりしますので、色々なジャンルの情報を頭に入れていきましょう。有名な政治家の名前・顔写真・経歴は目を通しておきましょう。有名な国々の首相や活動家に関する名前と顔写真も同様です。
②足立学園中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
足立学園中学校は、全体として過去問と似た問題が出題されます。
ですから、過去問を遡って解くことが重要です。解くだけではなく、必ず解けるまで解き直しを行って下さい。
(2)いつから解き始めればよいか
特別奨学生入試を受験予定の生徒様は、算数・国語については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。
算数は差がつきやすいですし、国語は記述問題を中心に様々な問題が出題されます。どちらも早めに対応した方が良いでしょう。
理科・社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。
理科・社会については、あまり早く始めても、試験範囲の学習が終わっていない場合もありますので、焦らず夏休みに集中して行っていきましょう。
一般入試のみ受験予定の生徒様は、夏休みから算数・国語を中心に解き始めましょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は10回分、出来れば15回分解いておきたい所です。
まずは時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は10回分以上解くと良いでしょう。2周解き直しが出来れば良いと考えます。 文章の読解力をつけるために、読書を欠かさずに行いましょう。
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すようにしましょう。
10回分解くと良いかと思います。計算問題の解き直しは必須です。解き直しは3周行いましょう。
社会も10回分解くと良いでしょう。解き直しは3周行って下さい。
弱い単元の復習・時事問題も忘れずに行って下さい。
③保護者様に出来るサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒計算力対策様を見てあげて下さい。
(2)計算力対策
足立学園中学校は、計算力が鍵を握ります。
毎日5問〜10問程度、四則演算の計算問題を解くと良いでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。
正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)理科の対策
足立学園中学校の理科は、これまでご説明している通り、理解を問う問題が多く出題されております。
保護者様としましては、身近な事柄について、生徒様と会話をし、一緒に調べて理解を促すようにして頂けると宜しいかと思います。
例えば、 「どうして電池を繋ぐと電流は流れるのか一緒に考えてみようか」 「夕焼けはどうやって起きるんだろうね」 など、日常当たり前の事をしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。
物理の単元を中心に、是非、生徒様とご一緒に取り組んでみて下さい。
(4)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的な事でも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。 ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにして下さい。
例えば、 「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」 「男女の格差社会ってどういう事なんだろうね?」 と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。
是非、取り組んで頂ければと思います。
まとめ
足立学園中学校の試験問題は、文章が長く、圧倒されそうになる問題もありますが、実は基本〜標準的な問題で構成されています。ですから、落ち着いて何が訊かれているのか、よく考えるようにすれば、解答は思いつきやすいでしょう。
また、基本〜標準的な問題が出題されるという事は、基礎の徹底が大事だという事です。算数では、計算や小問集合をしっかりと得点出来る様に、その後に数の問題・図形・速さ・思考力問題を強化しましょう。国語では、漢字・語彙・毎日の読書を行い、文章の要約を行っていくと良いでしょう。
【参考文献】
足立学園中学校HP(https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/)
足立学園中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
佼成学園中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら