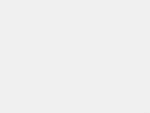1. 雙葉中学校とは
雙葉中学校は1875年に創立された中高一貫の私立女子中学校で四ツ谷駅(JR線・丸の内線・南北線)から徒歩2分と通いやすい場所に位置しています。
雙葉中学校ではカトリックの精神に基づき、「徳においては純真に 義務においては堅実に」を校訓に掲げた規律正しい教育を行っています。
また中学受験御三家の1つに数えられる雙葉中学校では勉学にも力を入れており、高校課程の先取り・フランス語を必修教科に導入するなど独自のカリキュラムで高い進学実績を上げています。
2. 雙葉中学校の入試傾向について
雙葉中学校入試の各科目の配点・試験時間は以下の通りです。
| 科目 | 配点 | 時間 |
| 算数 | 100点 | 50分 |
| 国語 | 100点 | 50分 |
| 理科 | 50点 |
30分 |
| 社会 | 50点 | 30分 |
まず配点比重の高い算数・国語を苦手科目にすることは致命傷となります。
特に雙葉中の算数・国語は記述問題が多く、差がつきやすい構成となっているためこれらの得点が合格の鍵となります。
理科・社会に関しては思考力・考察力が問われる問題が出題される傾向があります。
難度の高い問題をクリアするためには単なる知識ではなく、原理・背景等も含めた深い知識を身につけ、基礎固めを行うことが必要です。
①算数の出題傾向
雙葉中学校の算数は試験時間50分・大問5題の出題形式です。
大問1は標準レベルの問題で構成された小問集合であり、難易度はあまり高くありません。
一方大問2〜5は「規則性」「文章題」「速さ」「平面図形」からの出題が多く、「論理推理」「立体図形」からの出題は極めて少ないです。
標準レベルから応用レベルまで幅広く出題される傾向にあります。
また雙葉中学校の算数の特徴としては次の二点が挙げられます。
|
・記述式で考えを簡潔にまとめる必要があること ・地道に手を動かして考える必要のある問題が出題されること
|
記述式に慣れるためには式・図を書く習慣をつけることが有効です。
算数は答えに到達するまでに必ず根拠・プロセスが存在します。考え方を図・式にまとめて整理する習慣は間違えた原因を特定するきっかけにもなります。
また基礎力だけでは対応できない地道に手を動かす必要があるような問題も存在します。
2024年度大問4の「食塩水」の問題では3種類の操作を並べ替えて最も食塩水の濃度が濃くなる手順を考える問題が出題されました。
効果的な手順を自分で絞ってから、自分で調べることを必要とする難易度の高い問題でした。
②国語の出題傾向
雙葉中学校の出題形式は数年で大きく変化しています。
試験時間は50分であるものの大問の内容が年度によって異なるためです。
特に知識問題の内容が一定でなく、漢字の読み・読み書き・総合知識問題など種類はさまざまです。
まず幅広い知識力を身につける必要があります。
読解問題に関しては「選択肢」「抜き出し」「空所補充」「記述」などさまざまなパターンから問われます。しかし「記述」の比率がかなり高く、文章の内容を自分の言葉で説明することを重要視しています。
特に雙葉の国語では自身の経験と結びつけた自由記述が出題されることが大きな特徴です。
2024年度大問2では「あなたが経験した『魔法の時間』」について論述する問題が出題されました。
筆者の言う「魔法の時間」の意味について理解し、その条件に当てはまる自身の経験をまとめる必要がありました。
③理科の出題傾向
雙葉中学校の理科は試験時間30分・大問4題の出題形式です。
物理・化学・生物・地学の4分野から均等に出題され、大半が標準レベルの問題です。
しかし分析力・思考力が問われる問題・記述問題・時事問題からも出題されます。
2024年度大問2(地学)では標準問題だけでなく
|
・「防災の日」に関する時事問題 ・写真からどのような地盤変動があったのか説明させる問題
|
という時事問題・考察問題が出題されました。また、
|
・地震以外に海岸段丘が作られる要因を答えさせる問題
|
も出題され、原理・背景も含めた深い知識を身につける必要があります。
④社会の出題傾向
雙葉中学校の社会は試験時間30分・大問3題の出題形式です。
地理・歴史・公民の3分野から均等に出題されます。
基礎知識が問われる問題もありますが、記述問題・資料の読み取り問題も目立ちます。
さらに近年では新しい大学入試制度を意識した考察問題の出題がありました。
2024年度大問1(公民)では「温室効果ガスの削減への取り組み」に関して「各国が現在の排出量に合わせた削減目標を設定すべき」という先進国の意見に対して発展途上国の立場に立って反対意見を説明する問題が出題されました。
このように早期に基礎知識を身につけ、資料の読み取り問題・考察問題に慣れるための実践演習の機会を設ける必要があるでしょう。
3. 雙葉中学校の入試対策について
まず全教科に共通して
|
・基礎固めのフェーズ ・入試に向けた実践力を高めるフェーズ
|
に分けて対策を進めていくことが有効です。
基礎固めができていないと
|
・出題分野によって得点が安定しない ・応用問題を解くのに必要な基礎が理解できていない
|
など実践力を高める時期に影響が出てきてしまいます。 そのため6年前期までに基礎固めをしっかり行い、6年後期に応用力を高めていくという流れを推奨しています。
また確認テストや志望校別判定テストを目標とし、具体的な学習計画を立てると勉強を進めやすいです。
そこで雙葉中の偏差値を目標にすることをオススメします。
| SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 |
| 58 | 67 | 65 |
①算数の入試対策
【6年生前期まで】
6年生前期までは標準レベルを確実に解ける状態を作りましょう。
1つ1つの問題の解き方を説明できる状態を作っておくことで、応用問題に向けた土台を作ることができます。
「解法を覚える」勉強に走る生徒様も多いようですが、解法暗記では今後応用問題を解く際に太刀打ちできません。図・式を書きながら 「なぜこのように解くのか?」 に着目して答えまでのプロセスを理解することが大切です。
5年生以降新しい分野を次々に習うことになるため確認テストを目標におき、各分野の習熟度をチェックすることをオススメします。
【6年生後期以降】
6年生後期では応用力を磨いていきます。
雙葉の出題傾向である「規則性」「文章題」「速さ」「平面図形」を中心に応用問題に取り組みましょう。
しかし単に問題を解くだけでは応用力は向上しません。
以下のことを意識して問題を解くことが効果的です。
|
・雙葉の記述問題を意識して解答を記述で残す ・どのような解き方を用いたのか分析し、もう一度解いてみる
|
記述問題を意識した勉強は言うまでもないでしょう。
間違えた問題は自分の書いた図・式を見て原因を確認します。
この際単に解き直しをするのではなく、どのような解き方を使ったのか分析することが大切です。
「今までに習った解き方なのか?」 「その解き方がどの問題で使われているのか」 をしっかり考えることで復習効率が高まります。
ほとんどの応用問題は6年前期までに習った標準問題の解き方を利用することで解けるケースがほとんどです。
そのため習った解き方がどのように使われているのか確認することは非常に有効な勉強であるといえます。
また実践演習の機会は塾での演習時間・志望校別判定テストなど増えるため、家庭学習の時間はそれらの復習に時間を割くことをオススメします。
このように復習をあまりせず量を意識して学習するよりは、扱った問題をしっかり分析し、解き直すことで1つ1つの問題を着実に消化していくことが大切です。
②国語の入試対策
まず知識の強化が必要で、受験直前まで「毎朝○○分やる」など習慣づけて行うことが大切です。その上で読解問題の対策を行いましょう。
【6年生前期まで】
6年前期までは特に「質」を意識した読解問題の勉強を行いましょう。授業で扱った文章を深く復習することが大切となります。
|
・授業で解いた問題の「解答までのプロセス」を理解する ・最終的に自身の言葉でまとめ直す
|
この2点を意識し、効率的な復習方法を身につけることが成績アップの鍵となります。
読解問題の成績は短期的に上げることは難しく、6年後期の時点で苦手な状況はなるべく避けたいです。
そのため毎回の確認テスト・志望校別判定テストの得点を気にすると良いでしょう。
もし点数が悪い場合は特に答案を見て自分の苦手箇所・原因を突き詰める必要があります。
【6年生後期以降】
前期までは1つの文章を深く復習する方法が主でしたが、後期では塾での実践演習・志望校別判定テスト・過去問など扱う問題数が非常に増えます。よって復習効率を上げる必要があります。
この際解けた問題は軽く見直し、解けなかった問題は
・なぜ解けなかったか/どのような流れで答えに至ったのか
・使える解法はなかったか を分析してもう一度まとめてみましょう。
また雙葉独自の「自由記述問題」に慣れる必要もあります。まずは過去問などを通して問題を解いてみて、最終的には解き方の流れを自分で確立させてしまうことをオススメします。
③理科の入試対策
まずは各分野で基礎固めを行い、その上で応用力をつけていく勉強の流れが効果的となります。
【6年生前期まで】
5年生は新しい分野を次々に習うことになると思います。そのため覚える知識の量が非常に多くなります。よって毎回の授業で
|
・基礎知識・原理を暗記する ・計算問題を理由もふまえて解けるようにする
|
勉強を着実に行う必要があります。
また知識量が多い分野では特にインプットだけに専念せず、積極的に問題を解いてアウトプットすることが大切です。 基礎力の確認を行う上で確認テストは良い判断材料となります。
そのため6年生前期までは特に確認テストに焦点をおいた学習が有効です。
以下は各分野における学習のポイントです。
<物理>
覚える知識量は少ないものの、てこ・浮力・電気回路など計算問題が多く原理の理解が重要な分野です。そのため「どうやって解くか?」を説明できるようにしておくことが大切となります。
<化学>
知識・計算問題どちらも重要な分野です。 まず水溶液・気体の性質、指示薬の色の変化など基本知識を押さえましょう。
また中和・酸素発生・溶解度などの計算問題は「どうやって解くか?」を説明できるようになりましょう。
また雙葉中学校では実験器具、実験操作に関する問題も出題されるため実験に対する理解を深めることも重要となります。
<生物>
知識量が非常に多い分野です。インプットだけでなく、問題演習を通したアウトプットも行うことで着実に知識を身につけていきましょう。
<地学>
生物と同じく知識量が非常に多い分野ですが、その知識には原理が関わっている場合がほとんどです。
例えば「隆起」「沈降」はどのようにして起こるのでしょうか? このように原理・背景と紐付けて知識を覚えていくことで深く勉強を行うことができます。
【6年生後期以降】
後期では分析力・思考力へ対応できる力を養う必要があります。 理科に関しても入試本番に向けて実践演習・模試の機会が増えてくるかと思いますが復習の際は
|
・計算問題であれば、解き方の根拠 ・知識問題であれば6年前期の学習内容
|
をしっかり見直すことが大切となります。
また志望校別判定テスト等を用いて、演習の成果を常々チェックすることも有効です。自分の苦手箇所を把握し、それに応じた学習計画を立てる必要があります。
このように応用力の向上に注力する期間ですが、知識の抜け漏れには注意しなければなりません。そのため知識の確認を学習習慣に取り入れることをオススメします。
④社会の入試対策
理科と同様まずは各分野で基礎固めを行い、その上で応用力をつけていく勉強の流れが効果的となります。
【6年生前期まで】
5年生は新しい単元を次々に習うこととなり、覚える知識の量が非常に多くなります。よって毎回の授業で知識のインプットを欠かさず行うことが大切です。
また社会はインプットが重要な教科ですが、同時に背景の理解が重要となります。
以下が各分野における学習のポイントとなります。
<地理>
地理の学習は地名・気候→産業の流れで授業が進んでいきます。
地名は名前・場所を地図帳・白地図を用いて暗記し、気候は海流・地形など原因を理解することに注力しましょう。
また産業に関しては地形・気候と密接に関連していることが多いため、どのように関連しているのか着目しながら勉強していきましょう。
<歴史>
まずは時代の流れ・出来事の因果関係をしっかり追いましょう。 「政策はどのような時代背景・流れがあってとられたか」など背景を理解することで知識の理解が深まります。
これらの理解が深まったら文化・外交・産業・学問の切り口でジャンル別に学習していくと歴史の整理がしやすいです。
ここでおすすめなのが、ジャンル別に年表をつくって流れを図式化する勉強です。時代の流れを図式化することで視覚的に覚えることができます。
<公民>
日本国憲法・三権分立に関しては暗記の側面がかなり大きいため、理解に重点をおいて暗記しましょう。
また雙葉では時事問題に関する問題が出題されるケースが多いです。そのため習った内容が時事問題と関連していないかチェックすることも有効です。
このような流れで背景・理屈を理解しながら知識のインプットを行うことで理解が深まります。知識を一通りインプットしたら問題集で確認してみましょう。
【6年生後期以降】
後期では考察問題・記述問題へ対応できる力を養う必要があります。
入試本番に向けた実践演習・模試の機会が増えてくるかと思います。しかし大半は6年前期までに学習した内容が関わっているので、6年前期の学習を振り返ってみることが有効です。
このように実践力の底上げ+基礎力の確認を日々行いながら、着実に入試に向けた対策を進めていきましょう。
また志望校判定テストの結果を見て、自分の苦手分野・問題を分析しておきましょう。応用力が足りないのであれば演習量を増やしていく必要があります。
知識の抜け漏れも発生するかと思いますので、知識の確認を学習習慣に取り入れることをオススメします。
⑤過去問の取り組み方
過去問は基礎力が身についた6年後期の時期に取り組むことが効果的です。
6年後期は応用力の向上を目的として演習の機会が増えることとなりますが、過去問は学校の入試傾向、難易度、時間配分を掴むことを目的として取り組みます。
まず夏期講習が終わったタイミングで1年分を解いてみて、各科目の出題傾向や時間配分の方法を掴んでおきましょう。また失点した問題を確認し、苦手分野や原因を特定しておきましょう。
特定分野の応用問題が苦手なのであればその分野の演習量を増やす、時間が足りないのであれば解くスピードを意識して演習に取り組むなど本番に向けた具体的な対策を練ることができます。
このように1ヶ月に2年分くらいのペースで過去問に取り組み、最終的には10年分取り組めることが理想です。 また第二・三志望校に関しては3年分取り組み、同じく過去問の傾向等を掴んでおきましょう。
⑥保護者様ができるサポート
生徒様は4教科の学習を効率よく行うことが必要ですが、各教科における勉強目的、勉強計画を自力で整理することはかなり難しいと思われます。
そのため目標を生徒様と一緒に立て、目標から逆算したスケジューリングをしてあげることが重要となります。
特に漢字・知識などの勉強については継続的に行う必要があるため、習慣を作ってあげるようなサポートも重要です。
「○月のテストで△点を取ろう!」「計画通り進んでる?」などの声かけを通して生徒様と保護者様が共に目標に向かって進めるような環境づくりを行うと良いでしょう。
また試験結果が悪くても「できなかったところを責める」ことは避けましょう。まずはできたところに注目して褒めてあげることが大切です。
その上で苦手科目、分野を一緒に分析し、苦手克服のための勉強計画を練り直すことが重要です。
4. 雙葉中学校の併願校について
以下が雙葉中を受験される生徒様の代表的な併願校となります。
| 〜1/31 | 2/2 | 2/3 | 2/4〜 |
| 浦和明の星 | 白百合 | 豊島岡 | 豊島岡③ |
| 栄東A | 豊島岡 | 東洋英和 | 洗足 |
| 渋幕 | 吉祥女子 | 鴎友学園 | 浦和明の星 |
まず1月中の受験は必須と考えてください。
それは①安全校の合格を勝ち取る、②受験の緊張感に慣れるといった目的があるためです。
生徒様の緊張感をなるべくなくすためにも早めに合格を得ておくことが大切となります。
雙葉中の合格判定が高く、他校の対策にも十分時間が取れる場合は渋幕・豊島岡などの難関中を併願校にして良いと思います。
しかし合格判定が低い場合は雙葉中学校の対策に比重を置き安全校を確実に取る戦略が有効です。
また2/4以降は倍率がかなり上がってしまうため2/3までの期間で確実に合格を勝ち取れるスケジュールを組むことが非常に重要となります。
5. まとめ
雙葉中の入試傾向と対策法について幅広く解説してきました。
雙葉中に合格するためにはまず基礎固めを徹底し、応用力を着実に身につける必要があります。また記述問題に重点をおく雙葉中に向けて日頃から「書く」ことに意識を向けましょう。
入試突破は生徒様1人ではなく、保護者様のサポートも大切となります。 ぜひスケジュール管理など影で支えていただき、生徒様と二人三脚で受験に向かって頑張っていただければと思います。
正しい努力で中学受験を成功させるために勉強計画や勉強方法の参考にしていただければ幸いです。
【参考文献】
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら