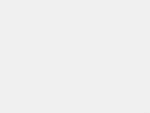1. 広尾学園中学校とは?

都心の好立地にある広尾学園中学校。1918年に設立された順心女学校が2007年に共学化され、現在の名称に変更されました。最新設備を備えたサイエンスラボではDNA操作が行えるなど、最新設備を導入しており、他校には無い本物の教育を体験出来ます。
英語教育にも力を入れており、ネイティブの先生が25人も在籍しています。週3時間はネイティブの先生による英語授業があり、その結果、アメリカ・イギリスを中心として海外大学へ進学する生徒様が大変多くなっています。将来的に、国際関係の仕事に就きたい生徒様や、世界を飛び回る仕事に興味がある生徒様にはおすすめの学校です。
2. 広尾学園中学校の入試傾向とは?

第一回~第三回の試験科目は、算数・国語・理科・社会の四科目です。
試験時間は各々50分・50分・30分・30分、配点は100点・100点・50点・50点となっています。
医進・サイエンス回の試験科目も、算数・国語・理科・社会の四科目です。
試験時間は各々50分・30分・50分・30分、配点は100点・50点・100点・50点となっており、
理系科目の比重が高くなっています。
第二回・第三回では、インターナショナルコースSGと本科コースとで分かれていますが、試験科目・試験時間・配点は共通です。これらのコースは入学後のカリキュラムに違いがあり、
インターナショナルSGは、英語の授業が全てネイティブの先生となっています。
尚、どちらに出願しても合格最低点は一緒で、合格者の割合によってどちらかにスライド合格という形になります。
その他、国際生AG回があり、英検2級以上所有している生徒様向けの試験となっています。
第一回~第三回では、算数で最も差がつきますが、国語も同じ位差がつく事があります。
また、医進・サイエンス回では、配点の関係上、算数の次に理科で差がつく傾向にあります。
問題全体として、基礎を前提とした理解力・思考力を問う問題が多く、知識問題は非常に少ない試験となっています。
①算数
第一回〜第三回では、大問5題程度の出題で、大問1番が小問集合、残りが単元別の問題となっています。小問集合は計算問題とその他様々な単元で構成されていますが、残りの大問では、図形・推理問題・数の問題の出題が大半です。この傾向は回数によりません。
図形では、平面図形・立体図形どちらも出題されており、面積・体積・切断・相似・回転体・角度など、図形に関するあらゆる問題が出題されています。
推理問題は、他校ではあまりみられませんが、広尾学園中学校では頻繁に出題されています。2024年度では、第二回に出題されており、過去問を中心に対策する必要があります。具体的に場合分けをして考えることが大切です。
数の問題は、場合の数・規則性・約数・倍数・不定方程式・約束記号など、こちらも広範囲に亘って出題されています。2024年度第一回では、この単元で大問3題の出題がありました。数にまつわる問題が得意な生徒様とそうで無い生徒様で大きく差が開いた問題となりました。図形や推理問題と合わせて、頻出単元には力を入れて学習をする必要があります。
医進・サイエンス回では、小問はなく、大問4題全てが単元別の問題です。第一回〜第三回よりも問題は難しく、本格的な問題です。出題される単元は、上記の単元と大きくは変わりませんので、より難しい問題まで演習する必要があるということです。医進・サイエンス回では、解法を書く欄がありますから、式・やり方を採点官に伝わるように書く練習もしておきましょう。
②国語
例年、第一回〜第三回では、大問4題の出題で、大問1番が漢字の読み書き、大問2番が、語彙に関する問題です。大問3・4番は説明文・物語文が1題ずつの構成で、正誤選択・記述・抜き出し・接続詞などの問題が出題されています。この傾向は、回数によりません。
最も特徴的な問題は記述式問題です。100字程度の長い記述問題が、物語文・説明文共に1題ずつ、合計2題される事が多く、文章全体から判断して答える設問となっているため難しい問題です。2024年度第一回も、今までの傾向通り、75字〜100字程度の記述問題が1題ずつ、計2題の出題でした。ポイントを外さずに論理的な文章が書けた生徒様とそうで無い生徒様で差が開いた問題でした。
尚、医進・サイエンス回では、物語文を除いた大問3題の出題です。100字程度の記述問題も出題されていますから、やはり一般の回と同様の対策が必要となるでしょう。
③理科
例年、大問4題の出題で物理・化学・生物・地学が満遍なく出題されており、回数により傾向は変わりません。全体的に文章が長く、考察問題が大半です。暗記だけでは対応出来ない問題ばかりで、しっかりとした現象理解が必要です。わからない事は図鑑・理科事典などで調べる癖付けが必要ですし、疑問に思う事はとことんまで追求して下さい。
計算問題も出題されていますが、多くはその場で考える思考力問題です。但し、定番の計算問題が出題されないわけではありません。2024年度第一回では、ばねの計算問題が出題され、問題集によくある形式の計算問題も出題されました。あくまでも、基本的な計算問題はしっかりと解けるレベルにある事が前提です。その場で考えればいいや、では無いですからご注意下さい。
医進・サイエンスの問題も傾向は似ていますが、問題のレベルが上がります。過去問で演習する事が大切です。
➃社会
例年、大問4題の出題で、地理・歴史・公民が満遍なく出題されています。これは回数によりません。特徴的な問題は大問4番の記述問題です。設問は2問出題され、資料や文章を読み込みつつ、生徒様自身の考えを書く問題となっています。2024年度第一回は、女性の参政権獲得についての問題と、ダイナミック・プライシングについての問題でした。記述問題は差がつきやすいですから、しっかり答えられるように対策をする必要があります。
地理では、地図帳を中心とした学習は勿論ですが、資料やグラフがふんだんに与えられ、それらを読み解く練習が欠かせません。日頃から統計を読み、どういった事が考えられるか思考する必要があるでしょう。また、地形図の問題が毎回出題されています。
歴史は史料や写真など、資料からの出題が多数出題されます。資料集を用いた学習は必須です。出来事の並べ替え問題もありますから、年号暗記も必要です。
公民は言葉の定義が重要です。例えば、公衆衛生とは?違憲立法審査権とは?納税の義務とは?など、小学生の生徒様には理解しにくい単語が公民には数多くあります。それらをしっかりと理解しておく事が欠かせません。
医進・サイエンスの回は、おおよそ一般回と同じような問題が出題されています。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
全体的な傾向としては、渋谷教育学園渋谷中学校に似ています。理系科目は攻玉社中学校の問題も似ていると思われます。攻玉社中学校は算数特選入試問題もありますので参考にすると良いでしょう。
3. 広尾学園中学校を受ける際の併願パターンは?
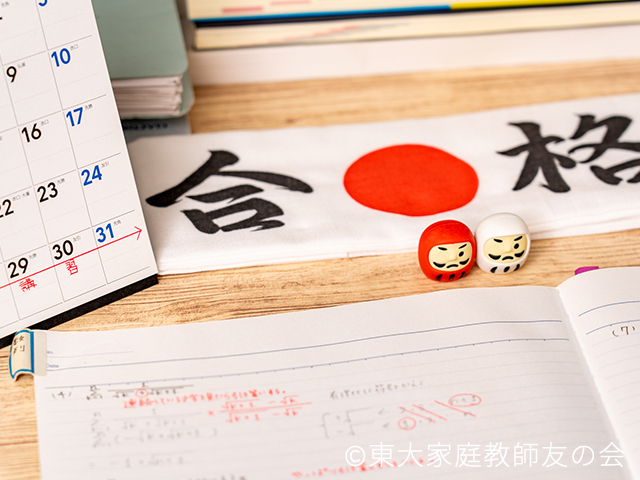
①1月受験校
|
・栄東中学校・東邦大学附属東邦中学校・市川中学校
|
1月は練習として、栄東中学校・東邦大学付属東邦中学校・市川中学校が挙げられます。
この中で、しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
|
午前:広尾学園中学校(1次)
|
午前入試は広尾学園中学校(1次)で決まりです。
午後入試は広尾学園中学校(2次)が良いと思いますが、レベルが高いのも事実です。
ですので、広尾学園小石川中学校(2次)を受験するのも良いと思います。
③2月2日
|
午前:明治大学付属明治中学校(1次)
|
午前は明治大学付属明治中学校(1次)が候補に挙がります。
午後は1日目と同様に、広尾学園中学校(医進・サイエンス)がありますが、やはりレベルが高いです。
そのため、東京農業大学第一高等学校中等部(3次)が候補に挙がって来るでしょう。
1日に午前・午後どちらも受験されると思いますから、2日は疲れも考慮して、
午前・午後どちらかの受験が良いでしょう。状況に応じて、上記の3校の中からお考え頂ければと思います。
④2月3日
|
午前:明治大学付属明治中学校(2次)
|
午前は、明治大学付属明治中学校(2次)が候補に挙がります。
午後は、広尾学園小石川中学校(3次)が候補に挙がります。
午前・午後どちらも受験されるかどうかは生徒様の状況に応じてご判断下さい。
⑤2月4日
|
・中央大学付属中学校(2次)
|
4日は、抑え校が合格されていない場合、中央大学付属中学校(2次)が良いでしょう。
抑え校が合格されていれば、2月5日には広尾学園中学校(3次)がありますから、休養に充てて下さい。
4. 広尾学園中学校の受験対策方法

広尾学園中学校の入試問題は、基礎を前提とした理解力・思考力問題が大半で、読解力・記述力も必要です。
最も差がつきやすい算数は、図形・推理問題・数の問題が中心です。
どの問題も、試行錯誤が必要ですから、じっくりと取り組むようにして下さい。
算数と同様に差がつきやすい国語は、漢字・語彙の定着をしつつも、記述問題対策が重要です。
要約練習が良い対策となりますので、日頃から実践することをおすすめします。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾は、SAPIX・グノーブル・早稲田アカデミーなど難関校向けカリキュラムがある塾が望ましいでしょう。
小問集合を含めますと、比較的満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。
広尾学園中学校では、計算力が必要です。入試問題の大問1番で、必ず計算問題は出題されますし、その他の問題でも、計算力が必要な問題が出題されます。ですので、計算力の強化を今のうちに行いましょう。毎日計算練習を行い、早く、正確に解く練習を行って下さい。
国語も、カリキュラムをもとに行いますが、授業で扱った文章の要約をすると良いでしょう。50字程度で書く練習をして下さい。日記を書いて、保護者様で添削を行うのも良いでしょう。また、毎日の読書を心掛けて下さい。様々なジャンルの文章を読んでいきましょう。
語彙・漢字についても、しっかりと定着させていきましょう。
理科は、生物・地学を中心とした学習が始まります。広尾学園中学校の入試問題に対応するには、暗記だけでなく、身の回りの現象理解が大切です。疑問に思うことは、図鑑・理科事典を用いて、深く調べていきましょう。これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察して下さい。科学館などに行ったり、実験を行うのも非常に大切です。自由研究を行うのも良いでしょう。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。
全般的な知識の暗記が必要ですが、統計や資料を確認しながら行いましょう。また、日頃からニュース・新聞を見て、今話題の内容について理解を深めていくと良いでしょう。地形図の読み取りを出来る様にして下さい。
(2)小学五年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生の内容も適宜復習するようにして下さい。
同じ教材で復習すると、暗記っぽくなってしまう生徒様は、「プラスワン」「ステップアップ問題集」(各々東京出版)を使用して、別の角度から復習するのも良いと思います。
国語は、物語文・説明文共に、生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、客観的に読む訓練です。
また、前学年同様、要旨を50~80字程度で書く練習や日記・読書について、引き続き行って下さい。
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。広尾学園中学校では、計算問題はよく出題されますので、発展的な問題まで解けるようにしましょう。
引き続き、単なる暗記ではなく、何故身近な現象が起きるのか、考えてみましょう。
図鑑・理科事典で深く調べていくと良いでしょう。科学に関するドキュメンタリー番組を見るのも良い事です。
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、確実に暗記を行って下さい。
主な出来事が何時代なのか、判断できるまで反復して下さい。難しい漢字も書ける様にしていきましょう。
写真・絵・史料といった資料につきましても、しっかりと確認しながら学習を進めて下さい。
また、ニュース・新聞を通して時事問題の理解を深めましょう。
(3)小学六年生(4月~6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
特に、図形・推理問題・数の問題について不安がある場合は、この時期に克服する必要があります。
過去問をいくらか解ける時期になりますので、一度解いて頂くと宜しいかと思います。
国語は、様々なジャンルの文章を読んで、問題を解いていく時期です。
この時期でも、要旨を纏める練習、日記・読書の習慣は継続して下さい。
算数同様、過去問を解き始めると良いでしょう。
理科は、全分野の暗記や理解を総復習しつつ、より高度な理解をしていきましょう。問題の答えが合っていた、で満足せずに様々な場合を思考しながら、納得いくまで調べてみましょう。
社会は、公民が始まります。言葉の定義を理解しつつ、憲法の条文やグラフなど基となる情報を中心にしっかりと理解するようにしましょう。
時間を見つけて、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。
ニュース・新聞で見聞きした内容を深める作業を行いましょう。問題点や生徒様ご自身の意見を整理していくと良いでしょう。
(4)小学六年生(7月~8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
特に、図形・推理問題・数の問題には時間をとって、復習・演習をして下さい。
「プラスワン」「ステップアップ」の復習を行いましょう。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。記述問題はポイントを箇条書きしてから解答を書いていくようにしましょう。主語をきちんと書くことが大切です。
語彙・漢字については、この夏休みで固めていきましょう。
理科も、過去問を3回分解きましょう。その場で考えながら解く実験・考察問題が多いですから、しっかり情報整理して解く練習をして下さい。
また、理解していない単元があれば、この夏休みに徹底して行いましょう。
社会も、過去問を3回分行いましょう。資料をしっかりと読み解く練習、論理的に文章を書く練習を行って下さい。
また、ここ10年ほどの時事問題を学びつつ、地図帳・統計・資料集・条文など確認して知識の総復習をしましょう。
(5)小学六年生(9月~11月)
算数は、過去問が中心になりますが、特に図形・推理問題・数の問題の復習・演習に力を入れましょう。
過去問の解き直しもしっかり行なって下さい。
演習量が足りないようでしたら、最高水準問題集(シグマベスト)や渋谷教育学園渋谷中学校・攻玉社中学校などの過去問で演習をするのが良いでしょう。
国語も、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なって下さい。
これまでの解き直しも行いましょう。
この時期でも、読書・日記は継続して下さい。
理科も、やはり過去問が中心になります。過去問や授業で扱った問題の内容を、もっと深く掘り下げていきましょう。身の回りの現象理解についても、引き続き行って下さい。
社会も、過去問が中心になりますが、引き続き、時事問題やテーマ史について考察・理解をしていきましょう。
また、「日本のすがた」(最新版)を利用した統計の勉強や、大手塾から出版されている「重大ニュース」も見ておきましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問の解き直し、図形・推理問題・数の問題を含めた全般的な定着を行いましょう。
この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。
基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、復習しましょう。
「プラスワン」「ステップアップ」「最高水準問題集」、他校の過去問の解き直しも行いましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、今まで習ってきた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認して下さい。
計算問題についても、難しい問題まで復習をしておきましょう。
テーマ毎にノートに纏めておくと良いでしょう。
社会は、全般的な復習をしつつ、地図帳・地形図・統計・資料集・条文などを使用して、疎かになりやすい所を復習しましょう。
出来るだけ時事問題の理解を深めましょう。理科同様に、テーマごとにノートに纏めておくと良いでしょう。
②広尾学園中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
算数は比較的似た傾向の問題が出題されますので、なるべく遡って行い、解き直しもしっかり行って下さい。国語は形式に慣れることが重要です。理科・社会は過去問で形式に慣れた後に、過去問をヒントにテーマ毎に纏めて、深く掘り下げることが必要でしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と国語については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。
この2科目は配点が高い科目です。早めに解き始めた方が良いでしょう。
一方、理科と社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。あまり早く始めても、試験範囲の学習が終わっていない場合もありますので、焦らず夏休みに集中して行っていきましょう。
尚、医進・サイエンス回を受験予定の生徒様は、理科も夏休み前から始めた方が良いでしょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、図形・速さ・数の問題といった、よく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。
従って、最低10回分、出来れば20回分解いておきたい所です。
時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は、記述問題をしっかり書けるかどうかが重要です。
10回分解くと良いでしょう。2周解き直しが出来れば良いと考えます。
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すようにしましょう。
そのため、最低10回分、出来れば15回分解くと良いかと思います。解き直しについては、計算問題の解き直しを中心に3周行いましょう。
過去問とは別に、テーマ毎に纏めることも大切です。
社会は、出題形式に慣れる意味で、10回分行いましょう。解き直しは2周程度で良いと思われますが、過去問で間違えた問題から、弱い所を見つけ出し、その強化に時間を掛ける様にして下さい。理科同様に、テーマ毎に纏めることも必要です。
③保護者様に出来るサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)計算力対策
広尾学園中学校は、計算力が鍵を握ります。計算問題は必ず出題されていますし、スピードが必要な試験です。
毎日10問程度、四則演算の計算問題を解くと良いでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。
正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)理科の対策
広尾学園中学校の理科は、これまでご説明している通り、理解を問う問題が出題されております。
保護者様としましては、身近な事柄や科学の現象について、生徒様と会話をし、一緒に調べて理解を促すようにして頂けると宜しいかと思います。
例えば、
「洗濯物を干すと乾くのは何故だろうね?」 |
など、不思議に思う事をしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。
是非、生徒様とご一緒に取り組んでみて下さい。
(4)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的な事でも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。
ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにして下さい。
例えば、
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」 |
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。
是非、取り組んで頂ければと思います。
(5)自由研究
小学校で夏休みの課題として出される自由研究。広尾学園中学校受験にはもってこいの題材です。
毎年、理科・社会といった内容についての自由研究課題を見つけ、提出するようにしましょう。
その際にも、保護者様からの「なんでそうなるんだろうね?一緒に調べてみようか。」と言ったお声がけをしながら、深掘りして進めてみて下さい。自由研究そのものにも意味はありますが、文章をまとめる作業も大変重要です。
是非取り組んでみて下さい。
まとめ
広尾学園中学校は共学校になって日が浅いですが、高度な英語教育と、最新設備により、大変人気がある難関校です。入試問題は基礎を前提とした理解力・思考力を問う問題で、単なる暗記では処理出来ない問題が大半です。最も差がつきやすい算数は、図形・推理問題・数の問題が中心で、どの問題も簡単には解けません。日頃から、試行錯誤をして自力で解答まで辿り着ける練習をしていく必要があります。そのような経験が自信に繋がり、思考力の向上に繋がります。全科目的に文章が長く、記述問題も多いですから、読書・日記・要約を中心とした読解力・記述力も磨いていきましょう。
【参考文献】
・広尾学園中学校ホームページ
・広尾学園中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・渋谷教育学園渋谷中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・攻玉社中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
広尾学園中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら