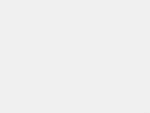市川中学校とは?
市川中学校は、千葉県市川市にある創立87年の伝統校です。「個性の尊重」と「自主自立」を教育方針としており、生徒一人ひとりが自ら考え、行動する力を育てることを目指しています。中高一貫の共学校で進学実績も良く、渋谷教育学院幕張中学校・東邦大学付属東邦中学校と並び、「千葉御三家」とも呼ばれています。
市川中学校の入試傾向と対策について
市川中学校の入試は、1月20日と2月4日の2回に分けて実施されます。特に1回目の入試での合格を目指すことが重要です。2024年度のデータによると、前期試験の倍率は2.5倍で、比較的多くの受験者が合格しています。一方、後期試験は併願校の入試日と重なるケースが多く、倍率は9.9倍と非常に高いため、狭き門となっています。
試験は算数・国語・理科・社会の4科目で構成され、それぞれ100点満点、合計400点満点です。
2024年度の合格者平均点は240点であったため、全教科で平均6割以上の得点が求められます。これにより、基礎問題を確実に得点し、応用問題でさらに得点を重ねることが合格のカギとなります。また、2回目の入試は併願校との日程が重なる可能性が高く、受験者数が少ない一方で、非常に高い得点率が求められるのが特徴です。そのため、基本的には1回目の入試で合格を狙う戦略が現実的です。
①算数
問題の傾向
市川中学校の算数は、年度ごとの難易度の差が大きいのが特徴です。どの年度においても、序盤は取り組みやすい問題が並び、得点源となりますが、終盤にクセのある難問が出題されることがあります。序盤の失点は挽回しにくいため、特に標準レベルの問題を確実に得点する力が求められます。
また、図形分野の出題頻度が高く、作図を必要とする問題が見られる点も特徴です。
得点戦略
算数では7割以上を目指します。
以下のように配点ごとの得点割合を意識し、確実に点を積み重ねましょう。
1.基礎問題で確実に得点を取る
序盤の計算問題や標準レベルの図形問題は正答率が高く、全問正解を目指します。
数の性質や速さ、割合なども素直な問題が多い分野であり、ミスなく得点を重ねることが重要です。
2.標準的な応用問題で得点を安定させる
図形分野では標準的な問題に加え、やや難しい問題も経験しておきます。
作図問題は、過去問や専用の演習を通じて十分に対策を行い、ミスを防ぎます。
速さや規則性などの分野でも、無駄なく正確に解けるよう、問題ごとの理想的な解法を身につけます。
3.難易度の高い応用問題で部分点を確保する
終盤のクセのある問題については、全問正解を目指さず、部分点を狙う戦略が有効です。
特に図形分野では補助線や公式を活用し、時間内で解ける部分を確実に仕上げます。
差がついた1問
問題概要
牧草地に牛と豚を放ち、日替わりで草を食べさせる。
(1)1日に牛1頭と豚1頭が食べる草の量を求める。
(2)では牛が放たれた日数を求める。
(3)では、牛と豚を放つルールを基に、草がなくなる日数を考える。
解説
この問題は、ニュートン算の応用力を試す良問です。
(1)では、基本的な計算により、牛1頭と豚1頭が1日に食べる草の量を求めます。これは原理を正確に理解していればスムーズに解ける問題です。
(2)では、牛が放たれた日数を求める不定方程式に持ち込む必要があります。この過程で論理的な条件整理と、数値の試行錯誤が求められるため、多くの受験生にとって難易度が高かったと考えられます。
(3)は(2)が解けていれば取り組みやすい問題ですが、条件の解釈を正確に行い、牛と豚を放つルールを適切に適用する必要がありました。
②国語
問題の傾向
市川中学校の国語は、試験時間50分、大問3題で構成されています。出題内容は論説文、小説、漢字の読み書きが中心です。文章量は約10000~11000字と多く、五択の選択肢問題では選択肢が100字を超えることもあります。試験では、基本的な読解力、漢字や語彙力、迅速な情報処理能力が求められます。全体の難易度は標準的ですが、スピードと集中力が合否を分ける試験です。
得点戦略
国語では7割以上を目標に、以下の対策を進めましょう。
1.長文読解の基本を徹底する
論説文: 段落ごとに要点を整理し、重要な一文や言い換え箇所をマークする練習を重ねます。要旨を50~100字で簡潔にまとめる力を養いましょう。
小説: 場面を分け、登場人物の心理や心情の変化を意識的に読み取る訓練が必要です。
2.選択肢問題への対応を強化する
五択形式では根拠を素早く見つけるスキルが重要です。消去法や迷ったときの判断力を過去問で鍛えましょう。
3.記述問題の練習を積む
文中の抜き書きではなく、自分の言葉でまとめる練習が必要です。具体的な言葉で補いながら論理的に記述する力を磨きましょう。
4.漢字や語句問題を得点源に
漢字の読み書きや基本語彙の徹底的な復習を行い、確実に得点できるようにします。
市川中学校の国語では、速読力と正確性に加え、選択肢や記述問題での対応力が重要です。効率的に学習を進め、着実に得点を積み上げましょう。
差がついた1問
問題概要
女性が自立することを阻む『女らしさ』の正体と、男性が文化を規定する社会における女性の『他者性』について論じた文章を題材に、内容理解や要点整理を問う問題が出題されました。
特に、⑭段落で述べられている『女らしさの内部に矛盾を抱え込んでいる』という指摘に基づいて、現代社会との矛盾をどのように解釈するかが問われました。
解説
この問題は、文章全体の要旨や細部に注意を払いながら、矛盾点を整理して考察する力が求められました。特に、⑭段落の「女らしさ」の矛盾についての理解と、現代社会との関連を分析する必要があり、選択肢を正確に絞り込む思考力が問われました。
また、「男性が文化を規定する社会で女性が『他者』とされる背景」について、具体的な例を文中から引き出しながら要点を把握するスキルも重要でした。一方で、選択肢の中には紛らわしい表現が含まれており、正答を選ぶ際に細部まで注意深く検討する力が必要とされました。
③理科
問題の傾向
市川中学校の理科は、試験時間40分、配点100点、大問4題で構成されています。
出題は物理・化学・生物・地学の全分野から幅広く、基本知識に加え、長文リード文や図表を活用した応用問題が含まれます。
物理・化学分野の比重が高く、時間配分と総合的な思考力が求められる試験です。
得点戦略
理科で7割以上を目指すためには、以下の対策を行いましょう。
1.頻出テーマの復習を徹底する
生物: 光合成、呼吸、進化などの実験問題を重点的に復習しましょう。
地学: 天体や気象の基礎知識を押さえ、地層や地震の問題にも対応できる準備を進めます。
物理: 力のつり合い、電気回路など計算問題をしっかり練習します。
化学: 中和反応や金属の反応、ものの溶け方などの計算問題を正確に解けるようにしましょう。
2.記述・データ問題への対応に対応する
リード文やデータを正確に読み取り、論理的に記述する練習を重ねます。
3.得意分野を活かす
得意分野で確実に得点し、苦手分野での失点を最小限に抑えることが重要です。
4.時間配分を意識
試験時間40分は限られているため、過去問で解答ペースを練習し、時間内に全問に取り組む力を養いましょう。
基礎力と応用力をバランスよく磨き、計画的に学習を進めることで、確実に得点を積み重ねることができます。
差がついた1問
問題概要
2023年6月以降、新型コロナウイルスをはじめとする感染症が増加しました。これらに対し、抵抗力をつけたり高めるためにどのような対策が考えられるかを記述する問題。
解説
この問題は、理科の知識がなくても日常的な理解で対応できる内容でした。対策として、「予防接種」「衛生管理」「十分な栄養と休養」などを挙げればよく、特に日常的な思考力が試されました。
一方で、この問題は試験の最後に出題されており、時間切れで未解答の受験生も多かったと予想されます。また、具体例をどれだけ的確に挙げられたかで得点に差がついた問題でもあります。
本番でこのような問題を解くためには、時間配分を意識し、素早く要点を整理する練習が必要です。資料問題を解く際には、限られた時間内で効率よく回答をまとめる力を養いましょう。
④社会
問題の傾向
市川中学校の社会は、試験時間40分、配点100点、大問3~4題で構成されています。地理・歴史・政治経済の3分野からバランスよく出題され、2024年度は歴史が約5割、地理と政治経済が残りを分け合う形でした。統計資料や地図、グラフを活用した問題が中心で、記号選択や適語記入の形式が多く、記述問題も出題されます。資料や統計の読み取り力と、基本知識を組み合わせた応用力が問われます。
得点戦略
社会では7割以上の得点を目指し、以下のポイントを意識しましょう。
1.分野ごとの特徴を押さえる
地理: 統計資料や地図を用いた問題が多いため、地図の読み取りや統計の背景を理解する練習を積みましょう。国内外の貿易や産業データも重要です。
歴史: 年表を活用して時代の流れを整理し、人物・事件・文化を体系的に覚えます。図版や資料問題への対応力も重要です。
政治経済: 憲法や日本の政治制度を中心に、時事問題と関連付けて学習します。地方自治や選挙制度の基本を押さえましょう。
2.時間配分を意識する
資料の多い問題は時間がかかるため、解ける問題を先に進める戦略が有効です。過去問を使い、40分で全体を解き終えるペース配分を身につけましょう。
3.記述問題への対応を強化する
記述問題は50~60字程度でまとめる力が必要です。背景や理由を説明する問題が多いため、用語だけでなく、それに関連する情報を自分の言葉で説明する練習を積みましょう。
差がついた1問
問題概要
ペリー艦隊の一員として来日した羅森に関し、なぜペリーが羅森を同行させたのか、その理由や国籍について考えさせる問題が出題されました。
解説
この問題では、資料の読み取りをもとに、羅森を同行させた理由や彼の国籍について推測する力が問われました。羅森は中国人であり、英語を話せる通訳としてペリーに雇われたと考えられます。また、幕府の役人とは中国語で会話をした点も資料から読み取れます。
社会科の専門知識がなくても、資料を正確に読み解けば回答できる問題でした。ただし、試験時間が限られている中、この問題に十分に取り組めたかどうかで得点に差がついたと考えられます。資料の分析力と時間配分の工夫が、こうした問題を解く鍵となります。
⑤問題の傾向が似ている学校は?
市川中学校の入試傾向に似ている学校には、渋谷教育学園幕張中学校と東邦大学付属東邦中学校が挙げられます。いずれも千葉県の難関校であり、4教科すべてにおいて高い学力とバランスの取れた学習が求められる点が共通しています。
渋谷教育学園幕張中学校では、算数での図形問題や理科でのデータ分析を伴う問題が特徴で、市川中学校と類似しています。
東邦大学付属東邦中学校は、算数の応用問題や理科・社会での考察問題が多く、出題形式が市川中学校と似通っています。
両校とも併願校として人気が高く、受験対策を共有しやすい点も大きな特徴です。
市川中学校を受ける際の併願パターンについて
市川中学校を受験する場合、1月の地方校受験と2月の本命校受験を組み合わせるのが一般的です。
1月には東邦大学付属東邦中学校や渋谷教育学園幕張中学校を受験するケースが多く、これらは「千葉御三家」と呼ばれる難関校で、実力確認の場としても活用されています。また、埼玉や茨城の難関校を併願することもあります。
2月には市川中学校の前期試験(1月下旬)を軸に、他の千葉県内の学校と併願することが一般的です。さらに、東邦大学付属東邦中学校や渋谷教育学園幕張中学校を組み合わせて受験する例も見られます。
併願校の選定では、志望順位や実力を考慮し、負担を減らすスケジュール作りが重要です。
市川中学校の前期試験に合格できれば、他校受験の負担が軽減されます。事前に計画を立て、無理のない受験スケジュールを整えましょう。
市川中学校の受験対策方法
志望校合格に向けた時期ごとの学習内容や効果的な過去問活用法、保護者様のサポート方法を徹底解説します。
①時期別・教科別対策内容
4年生:基礎力の徹底
| 算数 | ・四則計算や簡単な文章題、基本的な図形問題を中心に、計算力と理解力を養います。練習問題を繰り返し解き、スピードと正確さを意識しましょう。 |
| 国語 | ・語彙や漢字の知識を広げるとともに、短文読解に慣れることを目指します。物語文や説明文の基本的な内容を読み取る力を身につけることが重要です。 |
| 理科 | ・植物や動物などの身近なテーマを通じて、観察力を育てます。簡単な実験の記録や結果の考察にも取り組み、科学的な思考を養いましょう。 |
| 社会 | ・地図や白地図を使い、日本地理の基礎知識を習得します。都道府県名や主要な地形、産業の特色を覚えることが目標です。 |
5年生:応用力の育成
| 算数 | • 割合や比、速さなど、入試に直結する重要単元を習得します。平面図形や特殊算は頻出のため重点的にも挑戦し、思考力を高めることがポイントです。 |
| 国語 | • 長文読解に取り組み、段落ごとの要旨を把握する練習を行います。説明文の要点整理や物語文の心情理解を中心に、記述式問題にも取り組み始めましょう。 |
| 理科 | • 力や光、水溶液の基本を押さえ、実験問題に対応する力を養います。グラフや表を使った問題にも慣れることが重要です。 |
| 社会 | • 統計やグラフを読み解く力を養い、日本地理の復習を進めます。歴史では、時代ごとの大きな流れをつかむことを目標とします。 |
6年生(4月~6月):基礎と応用の総復習
| 算数 |
• 市川中学校で頻出の割合や速さ、図形問題などの基礎を徹底的に復習します。 • 過去問演習を通じて、条件整理や応用力を鍛えることが重要です。 • 苦手分野を洗い出し、反復練習で克服する計画を立てましょう。 |
| 国語 |
• 長文読解の練習を重ね、段落ごとの要旨を的確に把握する力を養います。 • 語彙や漢字を継続的に学習し、記述問題にも徐々に取り組みます。 • 物語文と説明文の両方をバランスよく取り組むことが重要です。 |
| 理科 |
• 力や光、水溶液など、基礎的な知識の定着を図ります。 • 市川中学校の特徴である計算問題やグラフ読み取りに慣れることがポイントです。 • 実験や観察に基づく問題の対策も並行して進めましょう。 |
| 社会 |
• 日本地理では、産業や地形のつながりを意識しながら復習します。 • 歴史では、時代ごとの背景や関連人物を整理し、大きな流れをつかみます。 • 統計資料やグラフを使った考察問題にも慣れるよう、演習を繰り返します。 |
6年生(7月~8月):実践力の強化
| 算数 |
• 模試や過去問を通じて、時間配分を意識した実践練習を行います。 • 応用問題に重点を置き、特に図形や場合の数など難易度の高い問題に挑戦します。 |
| 国語 |
• 長文読解の演習を増やし、記述問題の精度を上げます。 • 読解スピードを意識しながら、本番を想定した時間内で解く練習を進めます。 |
| 理科 |
• 過去問演習や模試を通じて、グラフや表、時事問題を含む総合的な問題に取り組みます。 • 実験や観察に基づく問題の解き方を整理し、得点源にする練習をします。 |
| 社会 |
• 歴史の流れを再確認し、地理の応用問題にも取り組みます。 • 資料問題や時事問題を中心に、総合的な考察力を強化します。 |
6年生(9月~11月):志望校対策
| 算数 |
• 市川中の過去問に特化した対策を開始し、難問への対応力を高めます。 • 特に立体図形や相似、条件整理が必要な問題を集中的に練習します。 |
| 国語 |
• 過去問を使い、市川中の出題傾向を徹底的に分析して対策を進めます。 • 記述問題では、要旨を的確にまとめる練習を繰り返し行います。 |
| 理科 |
• 過去問で頻出のテーマを重点的に復習し、基礎を確実に固めます。 • 時事問題やグラフ分析の演習を繰り返し、応用力を高めます。 |
| 社会 |
• 市川中の出題傾向に合わせた統計資料やグラフ問題に慣れる練習を行います。 • 入試頻出の時事問題に重点を置き、模試の復習を活用して知識を固めます。 |
6年生(12月~1月):総仕上げと直前対策
| 算数 |
• 総復習と過去問演習を繰り返し、ミスを防ぐ練習を行います。 • 試験本番を意識して、時間配分の確認を徹底します。 |
| 国語 |
• 直前期は短めの文章や基本的な問題に取り組み、確実な得点を目指します。 • 苦手な記述問題を再確認し、最後の仕上げを行います。 |
| 理科 |
• 基礎的な知識の復習を行い、実験や観察の総合問題に取り組みます。 • 過去問で確認した頻出テーマをもう一度整理します。 |
| 社会 |
• 時事問題や基礎的な地理・歴史の復習を重点的に進めます。 • 模試や過去問の復習を活用し、解答の精度を向上させましょう。 • 統計や資料問題にも触れ、本番で対応できる力をつけておきます。 |
②市川中学校の過去問対策方法
過去問の効果的な使い方
過去問は、試験傾向を把握し、得点力を高めるために重要です。まず全体の形式や出題パターンを確認し、苦手分野を洗い出します。演習後は必ず解き直しを行い、正答の根拠を理解することで実践力を向上させましょう。
いつから解き始めればよいか
過去問の演習は、6年生の夏休みから始めるのが理想です。まずは時間配分を意識せず取り組み、問題形式に慣れます。その後、秋以降に本番同様の条件で解き、志望校に合わせた実践力を養う段階に移ります。
何年分を何周解けばよいか
志望校の過去問は5~7年分を3周以上解くのが効果的です。1周目は形式の理解、2周目は弱点克服、3周目以降はスピードと正確さを意識した仕上げを行います。余裕があれば、他校の類似問題も演習するとさらに力が付きます。
③保護者様にできるサポート内容
中学受験を控えた生徒様にとって、保護者様のサポートは大きな力となります。励ましや生活面でのサポートを通じて、安心して学習に取り組める環境を整えることが大切です。また、子ども自身が計画を立てて進められるよう、見守りつつ適切なタイミングで声をかける工夫も必要です。
実際の声かけや対応例
日々の努力を認める声かけ
「今日はどこが難しかった?」「ここができるようになってすごいね!」と具体的に話を聞き、日々の努力をしっかり認めましょう。
学習計画の確認
「明日は何を重点的にやるの?」と聞くことで、自分で計画を立てる習慣をサポートします。
試験直前の励まし
「これまで努力してきたことは絶対に役に立つよ」と自信を持たせる言葉を伝えましょう。
保護者様の温かいサポートが、子どもの意欲と安心感を支える大きな力になります。
まとめ
本記事では、各科目の傾向や得点戦略、過去問の活用法、併願校の選び方、保護者様のサポート方法を詳しく解説しました。生徒様が計画的に学習を進めるためには、保護者様の適切な励ましと環境づくりが大きな力となります。本記事の内容を参考に、合格に向けて確実な準備を進めていきましょう。
【参考文献】
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
市川中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら