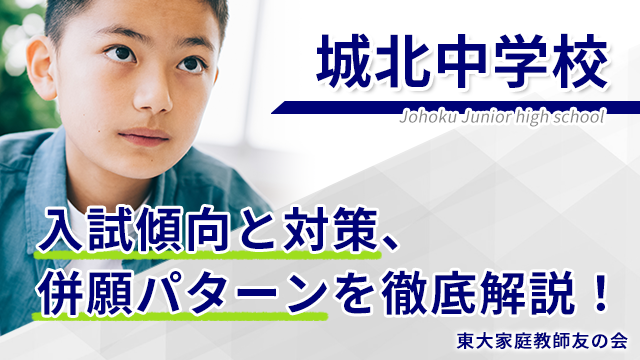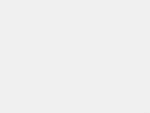1. 城北中学校とは?

23区内にありながら、校庭がとても広く、学校の敷地面積自体も40000平方メートルと、区内の学校とは思えない広さです(東京ドームが約46000平方メートルですから、かなり広いですね。)
難関大学へ向けて、長期休みの講習会や、生徒様からの希望補習など、勉強面も充実しています。厳しい指導も多少ありますが、基本的には面倒見が良い学校です。
2. 城北中学校の入試傾向について
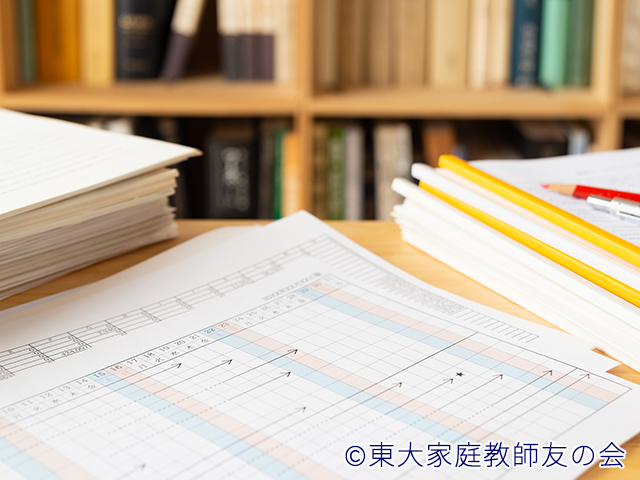
試験科目は、算数・国語・理科・社会の四科目です。試験時間は各々50分・50分・40分・40分、配点は100点・100点・70点・70点となっています。
これは、第一回~第三回まで共通です。回数が増えるにつれて、難易度は上がっていきます。
試験問題としては、算数で最も差がつきやすく、図形・速さ・数の問題が頻出です。国語は、文章が長く、設問には記述問題が多い形式です。
理科は、計算問題の比率が高く、理解を伴う問題も多いため、単なる暗記では歯が立ちません。社会は広範囲から標準的な知識問題が出題されます。地図を見る癖付けをして下さい。
①算数
例年、大問が5題出題されます。
大問1番は計算問題2問です。基本的な計算問題ですから、この2問を絶対に取れるように訓練して下さい。正確な計算には毎日コツコツ行うことが大切です。速さより、まずは正確性を大事にして取り組みましょう。
大問2番は小問集合で、半分以上は、図形、特に平面図形の角度や面積がよく出題されています。
図形以外では、線分図・平均・消去算・数の問題・場合の数など様々な単元が出されますが、どれも基本〜標準的な問題ですから、基本を大事に、確実に出来るようにしておきましょう。
大問3番〜5番は、速さ・数の問題・立体図形の出題頻度が非常に高いです。速さは、旅人算が多く出題されますが、通過・時計・流水算といった特殊算や点の移動が出題される事もあります。
ダイヤグラムの図が与えられて解く問題がほとんどです。2024年度第一回も、例年の傾向と変わらず、ダイヤグラムを用いた速さの問題、今回は流水算に関する問題が出題されました。
同傾向の問題でしたので、過去問をしっかり解き直している生徒様と、そうでない生徒様で差がついたものと考えられます。
数の問題は、規則性・数の性質・数に関する思考力問題などが出題されます。考えにくい問題でも、具体的に書き出してみると、紐解ける問題です。粘り強く取り組みましょう。
立体図形は、切断に関する問題が頻出です。過去問を辿ると似たような問題が出題されていますので、過去問で慣れていくと良いと思われます。展開図の問題が出題されることもあります。
②国語
例年、大問2題が出題され、大問1番が物語文、大問2番が漢字10問の出題です。城北中学校では、暫く物語文の出題が続いており、説明文・随筆文などは出題されていません。
物語文の文章は長く、速読と正確な読解力の双方が必要です。日頃の読書が重要となるでしょう。物語文の設問は、正誤選択・抜き出し・語彙・記述問題と、総合的な形式ですが、記述問題の数が多い事に特徴があります。
記述問題の字数は多くても80字程度ではありますが、少し特殊な問題が出題される事があります。例えば、2024年度第一回では、大問1番の問題11番で、「空欄に入る言葉を自分で考えて50字以内で書きなさい。」という問題が出題されました。
一見、難しそうではありましたが、内容理解が出来ていれば、解答出来る問題でした。
今回のような空欄に合うように文章を記述する問題は、城北中学校で頻出です。過去問で対策をしていれば、焦らず対処出来ますので、是非過去問で慣れて頂ければと思います。
③理科
大問の数は年度によってまちまちですが、配点としては、物理・化学・生物・地学がほぼ同比率となっています。全体的に計算問題の比率が高いのが特徴です。以下、それぞれの単元について、書いていきましょう。
物理は、満遍なく出題されておりまして、てこやばね・電気といった定番の計算問題が出題されています。
中には、中学校や高校で習う内容を、丁寧な導入文を読むことで解けるような、その場での対応を促す問題も出題されます。
2024年度第一回では、高校で習うドップラー効果に関する問題でした。ドップラー効果の内容は導入文に書かれた上で、内容をよく理解して設問を解く問題でした。
文章読解力と、物理の理解力、どちらも必要とされる問題でしたので、差がついた問題であったと思われます。
化学は、暗記分野と計算分野が半々程度の比率で出題されます。実験器具に関する問題もあります。計算問題については、標準的な問題はしっかり解ける実力がないと苦労するでしょう。過去問には似た形式の問題がありますので、演習すると良いでしょう。
生物は、男子校としては珍しく、昆虫に関する出題が少なく、代わりに植物・人体の出題が多い傾向にあります。基本的な暗記事項は必要ですが、考察問題が大きなウエイトを占めている問題で、やはり、生物の理解力が問われている問題です。
地学は、ここ2年間は天体の出題が多いですが、それより前は天気・地震・地層などがよく出題されていました。ですので、2025年度につきましても、満遍なく勉強をした方が良いでしょう。
地学も考察問題は出題されますが、どちらかと言うと、日頃の勉強内容がしっかり理解できているか、が問われています。普段の勉強の成果が試されると言えるでしょう。
④社会
例年、大問3題の出題で、大問1番が地理、大問2番が歴史、大問3番が公民となっています。漢字で答えさせる設問もありますので、しっかりと書けるように練習しましょう。以下、それぞれの大問の特徴を書いていきましょう。
地理は、標準的な知識を答えさせる問題が多く、地形・場所・雨温図・統計・農業・工業は毎年出題されています。2024年度は、導入文に城北中学校がある板橋区周辺の地理が問われました。
この形式は過去にも出題された事があったため、過去問をしっかり解き直していた生徒様と、そうでない生徒様で合否が分かれた可能性があります。今後も、同様な問題が出題されるかもしれません。対策はしておくべきでしょう。
歴史も、満遍なく標準的事項が問われます。それぞれの時代に何が起きたか、しっかりとした暗記が必要でしょう。出来事の並べ替え問題もありますから、年号暗記も必要です。歴史では、特に漢字指定の問題が多めですので、難しい感じも書ける様にして下さい。
公民は、憲法・国会・国際機関を中心に出題されます。多少、時事問題も出題されますが、特別な対策が必要なものではありませんので、あまり時間をかけなくて良いでしょう。裁判制度に関する問題は頻繁に出ておりますので、理解をしておいた方が良いと思われます。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
比較的似ているのは桐朋中学校です。国語の記述問題が多いことや、理科の問題について似ている部分も多く、参考になると思われます。
一方で算数に関しては、桐朋中学校と城北中学校では異なる点があります。それは、図形についてです。
桐朋中学校では、立体図形の問題がほぼ出題されませんが、城北中学校では、立体図形の問題が頻出です。そのため、その対策には本郷中学校の問題が参考になると思われます。
3. 城北中学校を受ける際の併願パターンは?

①1月
城北埼玉中学校・西部文理学園中学校・栄東中学校
1月は、練習として、城北埼玉中学校・西部文理学園中学校・栄東中学校が挙げられます。これらの学校で、しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
午前:城北中学校(1次)
午後:東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・2次)・獨協中学校(2次)
午前入試は城北中学校(1次)で決まりです。
午後入試は受験しなくても良いと思います。第一志望校となる城北中学校(1次)を受験後、相当に疲れると思います。
もし受験されるのであれば、東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・2次)は良いと思います。もしくは、抑え校として、獨協中学校(2次)も良いでしょう。
③2月2日
午前:城北中学校(2次)
午後:高輪中学校(算数選抜)
午前は城北中学校(2次)で決まりです。
午後は、算数に強い生徒様であれば、高輪中学校(算数選抜)が考えられます。ですが、無理はしなくて良いでしょう。
2日の午後入試を受けるのであれば、1日の午後入試の方をおすすめします。
④2月3日
午前:東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・3次)・成城中学校(2次)
午後:暁星中学校(2次)
3日午前は城北中学校と同じレベルの東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・3次)や成城中学校(2次)が良いでしょう。
一方、午後は暁星中学校が良いと思われます。難易度が少し高い点は難点ですが、国語の記述が多い暁星中学校は、城北中学校とマッチしています。
午前・午後どちらも受験するのは、体力的に難しいと思われますので、どちらか一方に絞って受験されるのが宜しいかと思います。
⑤2月4日
城北中学校(3次)・成蹊中学校(2次)・日本学園中学校(2次)・獨協中学校(4次)
4日は城北中学校(3次)で行きたい所ですが、3日までの受験がうまく行っていない状況ですから、抑え校を考えるという方針もあると思われます。
その場合、成蹊中学校(2次)が第一選択肢かと思われますが、もっと余裕を持ちたい場合は、日本学園中学校(2次)・獨協中学校(4次)が良いと思われます。
4. 城北中学校の受験対策方法

城北中学校は、昔から出題傾向に大きな変化はなく、算数で差がつきやすい傾向があります。算数では、標準的な問題が多いですが、速さ・数の問題・図形により力を入れる必要があるでしょう。図形では、立体図形の切断が重要ですから、十分な対策が必要です。
国語は、物語文が出題され、文章量が非常に多いです。設問は記述問題が中心です。日頃から読書を行い、文章題では要旨を書く練習をすると良いでしょう。
理科は、計算問題が中心ですので、問題集にある標準的な計算問題はしっかり解けるようにしましょう。暗記よりも理解が問われますので、何故そうなるのか、考えながら取り組みましょう。
社会は、全般的に標準的な内容が問われます。地理は地図帳を片手に場所を調べながら、歴史は時代と出来事を紐付けて、公民は国会・憲法・国際機関に力を入れて学習しましょう。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくと良いでしょう。城北中学校は、満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。
また、計算力も必須です。城北中学校では、大問1番に必ず計算問題が2題出題されます。速く、正確に計算が出来るように毎日トレーニングをして下さい。
国語も、カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにして下さい。文章を読んでから、要旨を50~100字で書いていくのが、将来の城北受験対策には良いでしょう。少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行いたい所です。
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
また、城北中学校の入試問題に対応するには、暗記だけでなく、身の回りの現象理解がとても大切です。これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察して下さい。
例えば、救急車の音は何故近づいてくると高くなるのか?など身近な内容について、考察してみると良いでしょう。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。都市の場所・地形・雨温図・農業・工業が頻出単元ですから、この時期にしっかり理解しましょう。ご旅行に行かれるのも大変重要です。旅行の思い出がそのまま地理の勉強にもなります。
(2)小学五年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにして下さい。
少し時間が経ってしまうと、出来なくなってしまう事も多いです。全体的に基本〜標準的な問題をしっかり解けるようにしていきましょう。速さ・数の問題・立体図形は難しい問題まで出来るようにしておきましょう。
国語は、物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を100字程度で書く練習をしましょう。書きたいポイントを箇条書きにしてから、記述するのが良いでしょう。読書は継続的に行い、漢字・語彙も忘れずに行って下さい。
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。計算問題はよく出題されておりますので、しっかり復習をし、標準的な問題は解けるようにして行きましょう。引き続き、単なる暗記ではなく、何故身近な現象が起きるのか、考えてみましょう。わからない事は、調べつつ、理解を深めて下さい。
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記を行って下さい。年号暗記も忘れずに行って下さい。主な出来事が何時代なのか、判断できるまで反復して下さい。写真や図の内容も忘れずに記憶して下さい。
(3)小学六年生(4月〜6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。特に、速さ・数の単元・図形に不安がある場合は、この時期に克服したい所です。過去問にも一度取り掛かってみましょう。
国語は、標準的な文章で、設問の解き方を確認して下さい。抜き出し問題は、同じような内容の段落から選ぶと正答に近づきます。練習をして、抜き出し問題に強くなりましょう。
理科は、引き続き、身の回りの事柄への理解を深めつつ、計算問題の力をつけて行きましょう。計算問題が苦手な生徒様は特に力を入れて復習して下さい。過去問にも取り掛かってください。
社会は、公民が始まります。国会・日本国憲法・国際機関については特に重要ですから、しっかり理解して下さい。時間を見つけて、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。
(4)小学六年生(7月〜8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。基本~標準問題対策として、「プラスワン」(東京出版)はおすすめです。秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。記述対策が最も重要です。記述問題がうまく書けない生徒様は、まず書きたいポイントを箇条書きにした後に答案作成をしていきましょう。語彙・漢字については、この夏休みで固めていきましょう。
理科も、過去問を3〜5回分解きましょう。理解不足の所は、基本に戻って理解をしていきましょう。計算問題については、少し難しい問題にも対応出来るようにしていきましょう。導入文を理解した上で、解答していく問題に慣れていきましょう。
社会も、過去問を3回分行いましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強して行きましょう。裁判制度については事例も含めて慣れていくと良いでしょう。裁判員裁判制度は頻出です。
(5)小学六年生(9月~11月)
算数は、過去問中心になりますが、特に解き直しに力を入れて下さい。立体図形の切断問題は苦労する生徒様が多いです。苦手であれば、特に力を入れて下さい。勿論、基礎の定着は日々行って頂く必要があります。
国語は、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なって下さい。過去問の解き直しも行いましょう。この時期でも、読書は継続して頂き、様々なジャンルに触れましょう。
理科も、やはり過去問を中心に行っていきます。過去問で出てきた内容については、暗記だけでなく、理解が出来ているか、保護者様で確認して頂くと良いと思います。解き直しも忘れずに行って下さい。
社会も、過去問は解きますが、それと同時に、全般的な復習も忘れずに行って下さい。この時期から「日本のすがた」(最新版)を利用した統計の勉強も本格的に始めて行きましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問の解き直し、速さ・数の単元・図形を含めた全般的な定着を行いましょう。この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、復習しましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、今まで習ってきた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認して下さい。計算問題も、標準的な問題や有名問題での取りこぼしが無いように復習をして下さい。
社会は、全般的な復習をしつつ、地理・歴史で出てきた場所の確認・統計の定着を行いましょう。
過去問を使用しながら、城北中学校にまつわる地理の復習も忘れずに行って下さい。
②城北中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
城北中学校は、全体として過去問と似た問題が出題されます。算数と理科の計算問題は似た出題されますので、なるべく遡って行い、解き直しもしっかり行って下さい。
社会についても、城北中学校周辺の地理や裁判制度など同じような問題が出題される事があります。
ですので、社会も過去問をしっかり行った方が良いでしょう。
国語については、形式に慣れて頂ければ、そこまで過去問を解く必要は無いでしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と理科については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。似たような問題が出題される傾向にありますから、出来るだけ過去問に触れて頂きたいためです。
一方、国語と社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。社会には上記の通り、一部同じような問題が出題される傾向はあります。ですが、算数・理科ほど重要度は高くありませんから、夏休みからで十分でしょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、速さ・数の単元・図形といった、よく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。従って、最低10回分、出来れば20回分解いておきたい所です。まずは時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は、記述問題に対処するための練習が必要です。従いまして、10回分解くと良いでしょう。2周解き直しが出来れば良いと考えます。その際、記述問題はポイントを箇条書き出来ているか、確認しながら行って下さい。
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すようにしましょう。計算問題については、数多く出題されますので、相当に練習が必要です。そのため、最低10回分、出来れば20回分解くと良いかと思います。
解き直しについては、計算問題の解き直しを中心に3~4周行いましょう。
社会は、出題形式にそれ程特殊性はありませんので、5〜10回分程度で良いでしょう。但し、上記のように、城北中学校周辺の地理と裁判制度については、繰り返し出題されております。それらを中心に解き直しを3周行い、入試に臨みましょう。
③保護者様にできるサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。すると、成績が下降して行きます。保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)計算力対策
城北中学校は、計算力が鍵を握ります。実際に大問1番は完全な計算問題です。毎日5問〜10問程度、四則演算の計算問題を解くと良いでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)立体切断対策
城北中学校は、算数で差がつきやすいことはお話ししましたが、特に立体切断が苦手な生徒様はとても多いです。やはり、イメージがつきにくい部分があるのでしょう。
そこで、保護者としましては、生徒様と一緒に、実際に行ってみると良いと思います。発泡スチロールや豆腐のような食材を始めとした、立方体や直方体の物を用意して頂き、問題で出題された通りに切断してみて下さい。具体的にイメージが出来てきますと、生徒様としても、今後解きやすくなると思われます。
まとめ
城北中学校は、過去問を重視した勉強が効果的です。特に算数・理科は過去問をベースに行って頂くと良いでしょう。
過去問を10回分、もしくはそれ以上解いて、解き直しもしっかりして、同じような問題が出題されましたら、必ず解ける状態にしておくことです。
国語は記述問題が多く、要旨を解答する問題もあります。日頃から文章の要約をする練習を積むと良いでしょう。
全科目的に、普段から土台となる基礎固めに重点を置いて、ミスで失点しない事を心掛けて下さい。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら