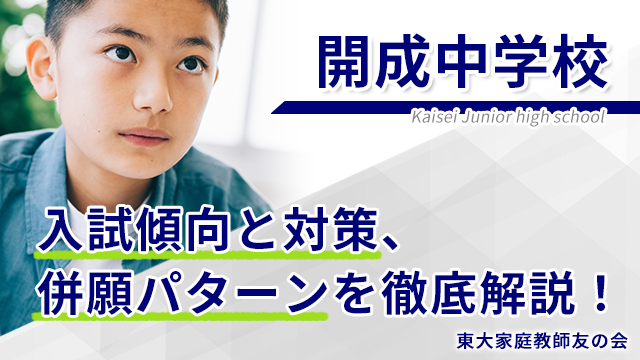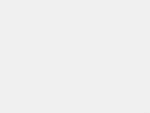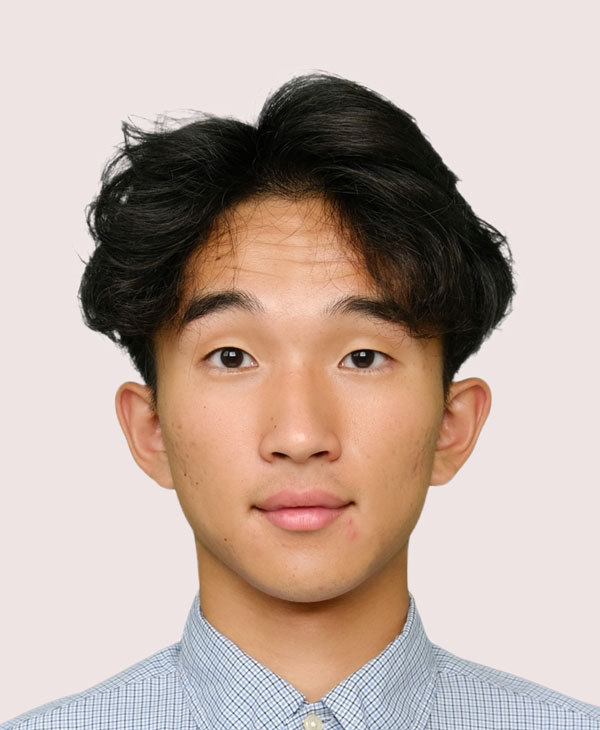1. 開成中学校とは?

言わずと知れた男子御三家の一角で、関東最高峰の私立学校。一学年400人の内、150人余り(現役・浪人含む)が東京大学に進学する優秀な生徒様の集団です。
開成中学校の特色としては、オリジナルプリントを使用した質の高い授業が展開されている点で、じっくりと思考力を鍛えることを主眼に置いています。中学入試試験も正に、思考力を問う試験となっていますので、入学後も更に生徒様の学力が向上していくことでしょう。
勉強面で目立つ開成中学校ですが、実は体育祭もかなり有名です。勉強集団とは思えない激しい体育祭で、多くの観客が詰めかけます。正に、文武両道を地で行く学校となっています。
2. 開成中学校の入試傾向について
試験科目は、算数・国語・理科・社会の四科目です。 試験時間は各々60分・50分・40分・40分、配点は85点・85点・70点・70点となっています。
算数で差がつきやすい傾向はありますが、国語でも算数と同じ位差がつくことがあります。 この二科目を中心に学習を進めましょう。
全体的な傾向としては、高度な読解力・論理的思考力・幅広い視野が挙げられます。 どの科目も試験直前の暗記程度では、歯が立ちません。じっくり考えて、粘り強く取り組むことが最も大事でしょう。 諦めずに取り組み、疑問があれば徹底的に理解出来るまで掘り下げることが大事です。
①算数
例年、大問3〜5題で出題されています。年度によって小問集合が出題されない場合がありますが、たとえ小問集合が出題されたとしても、楽な問題ではありません。 よく出る単元としましては、図形・規則性・場合の数・数の問題・速さです。原則、解法を記述することになりますので、式や解き方を簡潔に書けるように練習しましょう。問題文が長くなりがちなので、必要な数字には丸をつけるなど情報を漏らさないように注意して下さい。以下、詳しく解説していきます。
図形の問題は、立体図形から出題される事が多く、中でも立体切断の問題がよく出題されています。 平面図形が出題される場合は、相似・面積に関する問題が出題される事が多いです。 2024年度は今までの傾向通り、立体切断の問題が出題されました。難しい問題揃いの開成中学校ですから、立体図形の切断問題は、やはり対策をして出来るようにしておきたい所です。切断の問題は訓練すれば解けるようになっていく問題ですから、何度も繰り返して演習して行きましょう。
規則性・場合の数は、図形とセットで出題される事が多く、一見図形の問題が、よくよく具体的に考察してみると、規則があり、解答へと導ける問題です。
数の問題は、約数・倍数・推理問題に規則性や場合の数と絡む複合的な問題が出題されることが多く、思考・考察しながら解いていく問題です。見た目すぐに分かる問題ではありませんので、やはり具体的に考えながら解答していくことになります。
速さは旅人算・点の移動が出題されています。約数・倍数と絡む問題も多く出題されています。ダイヤグラムを書くのも有効な場合がありますので、図を書くことを意識しましょう。
以上、このように開成中学校の問題は複合的な問題が出題されています。複数の単元にまたがることが多いですから、先入観を持たずに、試行錯誤して解くようにしましょう。
②国語
例年、大問2題で、説明文1題、物語文1題の出題です。漢字以外は、どちらの文章も記述式問題しか出題されません。字数制限がない問題もありますが、その場合は行数指定問題です。1行30字程度を目安に書いていくと良いでしょう。
文章のレベルは高いので、日頃から読書を継続的に行い、読解力を強化していかなくてはなりません。ジャンルを問わず、読みこなせるようになりましょう。また、設問を解く際に、解答に必要なポイントを箇条書きしてから記述するようにしましょう。記述したものは添削してもらうと良いでしょう。添削してもらうことで、論理的に矛盾の無い文章を書けるようにしていきましょう。
2024年度では、2番の物語文が、いじめ・死・刺青など、小学生が読む文章としては、非常に考えさせられる、重たい内容でした。このような文章が出題されても、深く内容を理解出来る読解力が試されています。表面的ではない、真の国語力が必要です。
③理科
例年、大問4題の出題で、物理・化学・生物・地学がバランス良く出題されています。どの問題も、問題文が長く、考察問題が多い傾向にあります。記述問題は、ほぼ出題されません。
物理は計算問題が多いですが、記号選択問題も見受けられます。問題文が長く、理解を問う問題が多く、単なる計算力だけがあれば解ける問題ではありません。本質理解が必要です。
化学も、物理同様に、問題文が長いですが、化学は特に長く、考察問題が出題される傾向にあります。化学も計算問題だけではなく、理解を必要とする記号選択問題が多く出題されており、相当な学力が要求されます。 2024年度では、例年よくある長い文章からの考察問題ではなく、計算問題中心の比較的標準的な問題でした。勿論、標準と言っても、開成中学校として標準という意味ですから、難しい問題ではありました。ですが、日頃から計算問題を演習し、解答出来るレベルの生徒様なら高得点が取れる問題でしたから、差がついたと思われます。偏らずに学習をすることが重要です。
生物は、考察問題が出題される年度と、暗記問題中心の年度とあり、幅広く学習をする必要があります。どちらの問題が来ても良いように、手を抜かずに対策する必要があります。
地学は、考察問題と暗記問題が半々出題が多く、理解が必要な問題も勿論問われます。天体・天気・地層・地震の理解を深めましょう。
④社会
例年、大問2〜4題で、地理・歴史・公民・時事問題が出題され、公民のウエイトが低めです。時事問題は融合問題で出題されています。漢字指定の問題が出題される事がありますので、きちんと書けるようにしましょう。記述問題はあまり出題されません。
地理は、与えられた文章を元に、都道府県や地形について答えていく問題が出題されます。一般的な塾で習うレベルを超えた知識が問われる事も多く、例えば、為替レートや原油価格、EUの国々の場所など、日頃から新聞記事・ニュースを見聞きしたり、地図帳を細かく見るなど工夫が必要です。とにかく地理に興味を持って、どんどん吸収していく事が必要でしょう。知っている知識を繋げて答えを出していく問題が多いですので、一見知らないような問題も覚えた知識を総動員して取り組みましょう。
歴史も、与えられたいくつかの文章を元に、時代や出来事が問われる問題です。地理よりは対策がしやすく、塾で習う内容を細かく覚えていれば、対処出来る問題が多く、得点を積み上げたい単元です。年号暗記が必要な問題も出題されますので、しっかり覚えましょう。
公民は、憲法・国会・地方自治・国際機関といった重要単元については、標準的な内容を中心に暗記をしましょう。時事問題との融合も多い単元です。
時事問題は、年度によって変動はありますが、出題される時は全体の3分の1程度出題される事もあり、しっかりとした対策が必要です。ここ20年位の時事問題はチェックする必要があります。時事問題として、開成中学校が立地する東京都に関する問題もしばしば出題されています。
2024年度では、時事問題などが出題された大問4番で、東京都に関する地理が出題されました。具体的には文京区と台東区に位置する施設・地名を答える問題や、西東京市が合併する前にあった都市を答える問題が出題されました。このように、東京都に関する問題が出題される事がありますので、対策する必要があるでしょう。複数問出題されると差がつく問題になってしまいます。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
開成中学校ほど本格的な問題は、他校では出題されませんが、中では駒場東邦中学校が似ていると思われます。 算数で出題される立体図形の問題や、理科の問題は、開成中学校の問題の参考になるでしょう。過去問の量が足りない場合には、ご検討頂けると良いかと思います。
3. 開成中学校を受ける際の併願パターンは?

①1月受験校
|
栄東中学校・東邦大学附属東邦中学校・市川中学校・渋谷教育学園幕張中学校・灘中学校
|
1月は練習として、栄東中学校・東邦大学付属東邦中学校・市川中学校が挙げられます。
この中で、しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
渋谷教育学園幕張中学校・灘中学校は、受験しても良いのですが、もし不合格ですと、生徒様は相当に落ち込む可能性があります。生徒様の性格を踏まえてご検討下さい。
②2月1日
|
午前:開成中学校
|
午前入試は開成中学校で決まりです。
午後入試は受験しなくても良いと思います。第一志望校となる開成中学校を受験後、相当に疲れると思います。 もし受験されるのであれば、広尾学園中学校(2次)が良いと思います。
③2月2日
|
午前:渋谷教育学園渋谷中学校(2次)
|
午前は渋谷教育学園渋谷中学校(2次)が良いでしょう。
午後は広尾学園中学校(医進サイエンス)が良いと思われますが、1日の午後に受験されるのであれば、合格の場合、受験の必要はありません。休息に充てましょう。
④2月3日
|
筑波大学附属駒場中学校・早稲田中学校(2次)・海城中学校(2次)
|
開成中学校に合格しそうな生徒様は、思い切って筑波大学附属駒場中学校で勝負しましょう。
一方余裕の無い生徒様は、早稲田中学校(2次)・海城中学校(2次)が良いでしょう。
開成中学校対策とマッチするのは早稲田中学校の方になります。
⑤2月4日
|
芝中学校(2次)・城北中学校(3次)
|
3日までの結果が芳しくない場合、芝中学校(2次)、もしくはもっと安全に行く場合は、城北中学校(3次)が良いでしょう。
尚、2月5日には渋谷教育学園渋谷中学校(3次)がありますから、そこまで頑張ってみるのも手です。
生徒様のご様子でお考え下さい。
4. 開成中学校の受験対策方法
 最難関校である開成中学校の問題は、高度な読解力と論理的思考力が必要です。 また、幅広い視野に基づく問題も出題されますので、問題集だけやっていれば良いわけでもありません。
最難関校である開成中学校の問題は、高度な読解力と論理的思考力が必要です。 また、幅広い視野に基づく問題も出題されますので、問題集だけやっていれば良いわけでもありません。
最も差がつきやすい算数は、基礎をしっかり固めた後に、過去問・志望校別特訓中心に、演習をしましょう。図形・数の問題・規則性・数の問題が頻出単元です。
国語は、日頃からの読書・日記・文章の要約が必須です。つまり、付け焼き刃的な勉強では歯が立ちませんので、コツコツ積み上げていく必要があります。
理科・社会も勉強以外に日頃から行って頂きたいことがありますので、以下の説明を是非ご覧下さい。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾は、SAPIXやグノーブルなど最難関校向けカリキュラムがある塾が望ましいでしょう。
開成中学校では、高度な計算力が必要とされますので、計算力の強化も今のうちに行いましょう。
早く、正確に解く練習を毎日行って下さい。
国語も、カリキュラムをもとに行いますが、授業で扱った文章の要約をすると良いでしょう。
100字程度で書く練習をして下さい。
また、毎日の読書を心掛けて下さい。まずは、読みやすい文章を中心に読んでいくと良いでしょう。
読み手に伝える文章を書く練習として、日記を書くのも効果的です。ただ書くだけではなく、保護者様が添削してあげると良いと思います。
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
生物の暗記は特に重要ですから、自然に触れあいながら、体験として知っていくと良いでしょう。
また、今後に向けて身の回りの現象理解がとても大切です。
これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察して下さい。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。
授業で習ったことで満足せず、気になることを調べていくと良いでしょう。
地図の見方も重要です。縮尺や地図記号もしっかり定着させましょう。
旅行に行くのも大変良いと思います。記憶に残りやすいですし、旅行中に疑問に思うことも調べてみると良いでしょう。
ニュースを見たり、こども新聞を読むのも効果的です。時事対策はそう簡単にはいきません。この時期から行えると良いでしょう。
(2)小学五年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生の内容も適宜復習するようにして下さい。
同じ教材で復習すると、暗記っぽくなってしまう生徒様は、「プラスワン」「ステップアップ問題集」(各々東京出版)を使用して、別の角度から復習するのも良いと思います。
教材にある思考力問題は全部チャレンジしてみましょう。
国語は、物語文・説明文共に、生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、客観的に読む訓練です。
また、前学年同様、要旨を100字以内で書く練習をしましょう。
読書や日記は前学年に引き続き、継続して頂けると良いと思います。
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。非常に重要ですから、しっかり復習をし、発展問題まで解けるようにして行きましょう。地学・生物については、理解を中心に学習しましょう。暗記事項については、日々確認していくようにして下さい。
単にテキストに書いてあることで終わらせず、何故そのような現象が起きるのか、考えてみましょう。
わからない事は、調べつつ、理解を深めて下さい。
社会は、歴史が始まります。歴史は開成中学校で、重要な得点源になる単元です。
重要単語・年号の暗記は勿論ですが、流れの理解や背景知識を中心に学んで下さい。
絵や写真、史料など関係するものは、全て関連付けて理解していきましょう。
ニュース・新聞は継続して行って下さい。
(3)小学六年生(4月〜6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
この時期に過去問を解くのは難しいかもしれませんが、一度どのくらいのレベルなのか、身をもって知っていただく意味でも、チャレンジして頂ければと思います。
国語は、長い文章を正確に読める様にしていく時期です。
この時期でも、読書・日記の習慣は続けて下さい。
過去問にもチャレンジし、レベル感を知って頂ければと思います。
理科は、生物・地学の理解を総復習しつつ、計算問題の力をつけて行きましょう。
計算問題が苦手な生徒様は特に力を入れて復習して下さい。
志望校別特訓で出てきた内容についても復習しつつ、あやふやな所は調べ、納得していきましょう。
社会は、公民が始まります。開成中学校では、そこまで重要な単元ではありません。
基本事項をしっかりと理解・暗記出来れば良いでしょう。
地理・歴史の復習、志望校別特訓で出てきた内容の深堀りが出来ると良いでしょう。
(4)小学六年生(7月〜8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
特に、図形問題・速さ・数の問題・場合の数には時間をとって、復習・演習をして下さい。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。
語彙・漢字については、この夏休みで固めていきましょう。
語彙の問題は出題されませんが、語彙力があることが前提で、文章が読めるわけです。しっかり行いましょう。
理科も、過去問を3〜5回分解きましょう。その場で考えながら解く考察問題が多いので、しっかり情報整理して解く練習をして下さい。
また、理解していない単元があれば、この夏休みに徹底して行いましょう。
暗記事項もこの夏休みに覚えきるつもりで行いましょう。
社会は、過去問を3回分行いましょう。慣れる程度に行う位で十分です。
この夏休みは、全体の知識をしっかり総ざらいして下さい。
時事問題対策として、引き続き、ニュースを見て下さい。また、新聞についてですが、出来れば大人用の新聞に目を通すと良いでしょう。1面記事だけでも読めると良いと思います。
(5)小学六年生(9月~11月)
算数は、過去問・志望校別特訓が中心になりますが、それらの解き直しもしっかり行なって下さい。
演習量が足りないようでしたら、最高水準問題集(シグマベスト)で演習をするのが良いでしょう。
国語も、過去問・志望校別特訓を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なって下さい。
これまでの解き直しも行いましょう。
この時期でも、読書(出来れば日記も)は継続して頂き、様々なジャンルに触れましょう。
理科も、やはり過去問・志望校別特訓が中心になります。
これまでの解き直しも、必ず行いましょう。理解していない部分は早急に穴埋めしましょう。
この時期までに、考察問題への対応力をつけておきたいです。
社会も、過去問・志望校別特訓が中心になりますので、解き直し・暗記をしっかり行いましょう。
ここ20年程度の時事問題を知っていきましょう。
更に、時事対策として、大手塾から出版されている「重大ニュース」を、また統計対策として「日本のすがた」(最新版)を読み込んで下さい。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問・志望校別特訓の解き直し、重要単元を含めた全般的な定着を行いましょう。
図形・数の問題・規則性・場合の数になるべく時間をかけて復習しましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、過去問を遡りつつ、志望校別特訓・過去問での解き直しを行なって下さい。
暗記・理解のチェックは勿論ですが、計算問題の解き直しを必ず行いましょう。
社会は、今までの知識の総復習です。地図の見方や・緯度経度を含めた世界の国々の場所・雨温図・平均気温表・統計など手薄になりやすいですので、よく確認して下さい。
②開成中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
開成中学校は、形式は似ているものの、同じような問題が出題されるわけではありません。
しかし、演習するには過去問は格好の材料です。理系科目の算数や理科は、20年遡って頂きたいと思います。
一方、文系科目の国語・社会については、時間との関係上、10年遡れば良いかと思います。
一度解いたら、二度目以降は、原則、間違えた問題・不安な問題のみ解き直しを行ってください。
その際も大問一問毎に、時間を測って行うことで、より効果的になるでしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と国語については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。
二科目とも差がつきやすい科目ですから、早めに一度解くのが望ましいでしょう。
一方、理科と社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。
早めに始めようとしても、解けない問題も多いと思いますから、その位を目安に行ってみて下さい。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、時間が無ければ最低10年分、出来れば20年分解いておきたい所です。
同じ問題は出題されませんが、開成中学校の問題は、他の問題集や教材では中々補いきれません。
従って、過去問を出来るだけ解くのが宜しいかと思います。
出来なかった問題を中心に、3周は解き直しましょう。
国語は、過去問の傾向把握、解き慣れが重要になりますので、10年分が宜しいかと思います。
解き直しの際は、ポイントを箇条書きした上で、記述していきましょう。
解答と照らし合わせて、ポイントが合致しているか確かめましょう。
2周解き直せば十分です。
理科については、算数同様、他の問題集で補うのは難しいと思われます。
ですので、最低10年分、出来れば20年分遡りましょう。
解き直しは、算数同様、出来なかった問題を中心に3周行って下さい。
社会は、時事問題は2度出題されることがありません。
ですが、問題慣れや問題を通しての知識の確認は必要ですから、10年分行いましょう。
解き直しは、2周行えばよいでしょう。
③保護者様に出来るサポート内容
開成中学校は、最難関校ですから、勉強に費やす時間は相当なものになるでしょう。
その際に、常日頃から保護者様が出来る事を列挙していきたいと思います。
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)思考力強化
開成中学校のような難関校には、低学年のうちから塾の教材以外での思考力強化を考えましょう。
即ち、勉強としてではなく、楽しみながら思考力を強化する方法を考えましょう。
具体的には、パズル・タングラムなどで図形的思考力を、将棋・チェス・トランプ・algoなどで論理的思考力を養うことが重要です。
是非、保護者様も生徒様と一緒に遊んでみて下さい。
(3)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的な事でも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。
ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにして下さい。
例えば、
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」
「男女の格差社会ってどういう事なんだろうね?」
「原油価格が上昇しているっていうけど、なぜだろうね?どんな値段になっているんだろうね?」
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。
(4)理科の対策
開成中学校の理科は、これまでご説明している通り、考察問題による、理解を問う問題が多く出題されております。
保護者様としては、身近な事柄について、生徒様と会話をし、一緒に調べて理解を促すようにして頂けると宜しいかと思います。
例えば、
「洗濯物は干すと乾くのは何故だろうね?」
「ドライヤーの仕組みって知っている?」
「地震が起きる仕組みを一緒に調べてみようか。」
「月の形が毎日少しずつ違ってくるのはどうしてなんだろう。」
など、日常当たり前の事をしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。
まとめ
開成中学校合格のためには、高度な読解力・論理的思考力・幅広い視野の向上が欠かせません。
高度な読解力には、毎日の読書、新聞記事の読み込み、文章の要旨・日記を書いてみましょう。読解力に語彙力・漢字も欠かせません。必要な知識を入れることも忘れずに行って下さい。
論理的思考力には、算数・理科を中心とした複雑な問題をじっくり考えて、粘り強く取り組むことが一番です。先程述べた、高度な読解力も一躍を担うでしょう。
幅広い視野には、理科・社会において、身近な事柄やニュースに出て来る内容を当たり前と思わない事です。疑問に思う事を調べ、様々な角度から検証する事で、深い理解へと繋がります。そう言った姿勢が、算数・国語の実力向上へと導いてくれるでしょう。つまり、高度な読解力・論理的思考力にも効果があるということです。
このように、この3つの能力は相互に連関しているため、どれか一つでも欠けてしまうと、合格するに十分な力にはなりません。バランス良く伸ばすことをお考え頂き、合格へ向けて頑張ってください。
【参考文献】
開成中学校HP(https://kaiseigakuen.jp/)
開成中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
駒場東邦中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
開成中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら