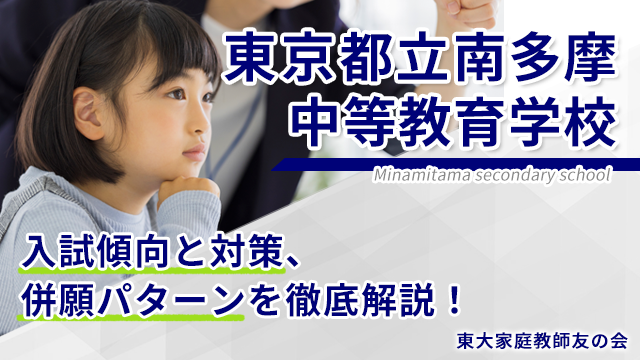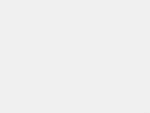1. 東京都立南多摩中等教育学校とは?

1891年に創設された八王子初の女学校を起源とする南多摩中等教育学校。「人間力の南多摩ー心・知・体の調和」を教育理念とし、様々な独自の教育活動をしています。
ここでは、南多摩中等教育学校の特色として、教育活動の柱とも言える「フィールドワーク活動とライフ・ワークプロジェクト」と「ワールド・ワイド・ラーニング」の2つについてご紹介します。
①DXハイスクールを活かしたフィールドワーク活動とライフ・ワークプロジェクト
南多摩中等教育学校は、ICTを活用した学びを強化する学校に対して、必要な環境の経費を支援する「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」の実施校に指定されています。
その事業を活かして整備された充実したICT環境を活用しつつ、前期課程ではフィールドワークを、後期課程ではライフ・ワークプロジェクトを通して、探究的な学びを実現させています。
学年ごとにテーマに沿って、ステップアップしながら探究活動を深化させていくことで、6年間を通して自分の興味関心や特性を深く理解するとともに、学びのスキルをかんようし、個々のキャリアデザインや進路実現につなげています。
②世界で活躍できるグローバルな人材を育てる「ワールド・ワイド・ラーニング」
大学の研修室訪問、地域や企業と連携しての講演会、先端技術の体験・見学などのほか、イタリアやベトナムの高校生とのオンラインでの国際教育など、より高度な学びを得られる仕組みによって、世界で活躍できる人材を育てる「ワールド・ワイド・ラーニング(WWL)」が行われています。
南多摩中等教育学校は、文部科学省による「ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業」の指定校に選ばれた10校のうちの1校です。
放課後には第二外国語講座があり、英語以外の言語に触れる機会があるほか、東京都が指定する海外学校間交流推進校にも指定されていることを活かし、海外の高校生を留学生として受け入れる活動を積極的に行っています。
2. 最新2025年度向け!東京都立南多摩中等教育学校の入学検査について

南多摩中等教育学校の入学検査は、一般枠募集のみです。ここでは、入学検査の内容や倍率などの概要、小学校での学習の様子をもとにした「報告書」の点数換算の方法に加え、2024年度の適性検査の問題を振り返り、合否を分けた問題や特徴的だった問題について解説します。
①入学検査の概要
南多摩中等教育学校の募集人数は160名で、入学者は、小学校5・6年生の学習の様子をもとに作成される「報告書」(360点満点を200点満点に換算、詳細はのちほどご説明します)と、2月3日の適性検査の総合得点により決定します。
適性検査は、南多摩中等教育学校の独自作成問題である適性検査Ⅰ(試験時間45分、100点満点)、都立中高一貫校の共同作成問題を使用する適性検査Ⅱ(試験時間45分、100点満点を200点満点に換算)の2科目行われ、適性検査ⅠとⅡの合計300点満点を、800点に換算します。
総合得点に占める適性検査Ⅱの大問3の割合が大きい点が特徴です。
2024年度の入学検査の倍率は3.67倍で、ここ数年は4倍程度で推移しています。
②報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の「各教科の学習の記録」を点数化したものです。
各教科の評定を、
評定3=20点
評定2=10点
評定1=4点
とし、それらの合計(360点満点)を200点満点に換算します。
総合得点に占める報告書の割合は20%と、都立中高一貫校の中では比較的少ない割合ですが、それでも日々の学校の学習にも手を抜かずにしっかりと取り組んでいきたいですね。
③適性検査Ⅰ
南多摩中等教育学校の適性検査Ⅰは独自作成問題で、文章の内容を的確に分析・考察するとともに、課題に対する考えや意見を明確かつ論理的に表現する力をはかります。
2024年度の出題の形式は、他の都立中高一貫校と同様に、2つの文章が出題される形式でしたが、2023年度、2020年度以前は、文章が1つの形式でした。どちらにも対応できるように、過去問は複数年分解いておくことをおすすめします。
ここでは、2024年度の適性検査の〔問題3〕、作文の問題について取り上げます。2つの文章を読み、その内容をふまえて、学校生活や日常生活の中で、何を大事にし、どのように行動していこうと考えるかを300字以上400字以内で書く問題でした。
作文の構成は、3段落構成が書きやすいです。
| 段落1 | 文章1と文章2を読んでわかったことを書く |
| 段落2 | 段落1で書いたことをふまえ、学校生活や日常生活の中で自分が大事にすべきだと考えたことを理由とともに書く |
| 段落3 | 段落1と2を踏まえて、どのように行動していくかを具体的に書く |
文章1では、1人称の世界観を反映した天動説が客観的な証拠や証明により地動説に取って代わられたことなど、天文学の歴史が人類の世界を広げたことが述べられており、文章2では客観的な世界観を獲得したとしても、世界に働きかけるには、その基礎となる1人称の世界が必要であることが述べられています。
そのことを踏まえ、3人称的なものの見方は、ものごとの広がりをもたらしてくれる一方で、そのような見方をするためには、1人称的な視点も必要であるこということを、学校生活や日常生活の中で起こりうる場面を想定して書けるとよいでしょう。
適性検査の作文では、自分の経験や考えを具体的に述べる必要があります。日頃から様々なことに対して、自分なりに考えを持ち、文章として書く練習をしましょう。
また、よい作文を書くためには、豊富な語彙力と、それを正しく運用する力も必要です。読書などでより多くの文章に触れることも、作文を書くうえで大切なことです。
④適性検査Ⅱ
適性検査Ⅱは都立中高一貫校の共同作成問題で、資料から情報を読み取り、課題に対して思考・判断する力、論理的に考察・処理する力をはかります。
大問1はマグネットシートを使った得点板の数字の作成をテーマに条件を整理しながら解く問題でした。大問2は公共交通機関の利用についての問題、大問3は摩擦に関する実験から、物体の性質を考察する問題でした。
ここでは、南多摩中等教育学校で配点が高く設定されている大問3について解説します。
〔問題1〕は、ペットボトルのキャップのみぞの摩擦のはたらきを、プラスチックの板やおもりなどを使ってモデル化した実験で確かめる問題で、表面のみぞの方向が回す方向に対して垂直であるペットボトルのキャップは、回す方向と平行にみぞがはいっているものよりもすべりにくくなると考えられる理由を説明する、というものでした。
実験1より、初めて板が動いた時のおもりを比べると、750gと1,000gのどちらの金属を載せたときも、おもりの数は手順6の板を用いた場合が最も多く、反対に手順8の板を使用した場合が最も少なくなっていることが分かります。
よって、糸を引く方向に対して垂直にみぞがあると、すべりにくくなることがわかります。ペットボトルのキャップのみぞも、手で力を入れる方向に対して垂直になっていることから、手順6の板のように、すべりにくくなっていると考えられます。
実験自体は複雑なものではありませんが、問題で何を問われているのかを見極め、必要な要素を盛り込んで答案を書けるかが試されていると言えます。記述の問題でできるだけ減点を少なくするためには、問題文をしっかり読み解く力も必要です。
〔問題2〕は、斜面をすべる物体の摩擦力が、接している面の材質にどのような影響を受けるのかを実験から考える問題です。6つの板の組み合わせの中から、すべり下りる時間が同じになると考えられる組み合わせを一つ答え、その理由を説明します。
問題に、「実験2では同じでなかった条件のうち、実験3では同じにした条件は何であるかを示して説明」することとあるので、対照実験について理解できているかと、それを言葉で説明できるかを試す問題です。
実験2は、斜面の面積は同じで、素材と重さが異なっていたが、実験3ではすべての組み合わせが同じ重さになっていると言えます。また、実験3の結果から、一番下が工作用紙でできた1号と3号のすべり下りる時間は同じですが、1号と、1番下がプラスチック材である6号では、時間は異なります。
よって、すべり下りる時間は重さには関係せず、斜面に接する素材によることがわかります。以上のことから、すべり下りる時間が同じになる組み合わせは、2号と5号、4号と6号と考えられます。
〔問題1〕と同様に、記述で説明する問題でしたが、それほど分量も多くなく、また計算も不要だったため、組み合わせを答えること自体はさほど難しくはなかったでしょう。
だからこそ、いかに減点されることなく理由を書けたかどうかで合否が分かれたと言えます。南多摩中等教育学校を目指す受検生にとっては、しっかり点数を取っておきたい問題でした。
⑤解いておきたい!出題形式の似ている学校
出題形式の似ている学校としては、適性検査・思考力型の入試問題を出題している学校が挙げられます。都立中高一貫校の共同作成問題や、独自作成問題を出題している学校の問題は参考になる部分も多いでしょう。
私立中学であれば、八王子実践中学校の適性検査型入試は、南多摩中等教育学校に準じた出題形式で作問されているので、南多摩中等教育学校の受検対策としても大いに活用できます。
3. 東京都立南多摩中等教育学校志望の生徒様におすすめ併願校紹介!

ここでは、ライターが過去に出会った生徒様の併願校を参考に、南多摩中等教育学校を目指す生徒様におすすめの併願校をご紹介します。
南多摩中等教育学校を志望している生徒様は、多摩地区の進学校との併願が目立ちます。特に多い併願先が穎明館中学校と八王子実践中学校です。
穎明館中学校は、1日と2日に4科の私立中型の入試を、1日、2日、4日に4科の総合型の入試を行っているので、私立中入試をメインに準備してきた生徒様、適性検査を中心に準備してきた生徒様、どちらも併願しやすい学校と言えます。お住まいに地域によっては、神奈川県の学校を受験する生徒様も多くいらっしゃいます。
併願パターンとして、下記では、入試の偏差値帯や進学実績などをもとにした併願パターンと、適性検査・思考力型の入試を行っている学校を受験する併願パターンの2タイプをご紹介します。各ご家庭の方針や生徒様との相性なども鑑みながら、併願校選びの1つの参考にしていただければと思います。
①偏差値帯を重視した併願パターン
こちらは、南多摩中等教育学校と比較的偏差値帯や進学実績が近い私立中学校を併願するパターンです。八王子にキャンパスを構える大学も多くあるためか、大学の附属校や系列校との併願も目立ちます。
(1)1月
・淑徳与野中学校
(2)2月1日
・穎明館中学校
・帝京大学中学校
・中央大学附属中学校
・日本大学第二中学校
(3)2月2日
・明治大学中野中学校
・明治学院中学校
・帝京大学中学校
・神奈川大学附属中学校
(4)2月4日以降
・成蹊中学校
・明治大学八王子中学校
②適性検査・思考力型入試を重視した併願パターン
こちらは、都立中高一貫校を目指している受検生を主なターゲットに行われる、適性検査型や思考力型、公立型などと呼ばれる入試を実施する学校を中心に併願するパターンです。
都立中高一貫校を志望する生徒様が併願校として選ぶことが多い宝仙学園中学校や開智日本橋中学校などを併願する生徒様も多いですが、南多摩中等教育学校を受験する生徒様に特におすすめしたいのは、八王子実践中学校の適性検査型入試(2月1日午前・午後。2月5日午前)です。
南多摩中等教育学校に準じた出題形式で作問されているため、直前の実践的な練習に役立つはずです。
(1)1月
・浦和実表学園中学校
(2)2月1日
・聖徳学園中学校
・八王子実践中学校
・宝仙学園中学校
・開智日本橋中学校
(3)2月2日
・桜美林中学校
・穎明館中学校
(4)2月4日以降
・八王子実践中学校
・穎明館中学校
・宝仙学園中学校
4. 必見!東京都立南多摩中等教育学校の受検対策

ここでは、南多摩中等教育学校の合格に向けて、具体的な受検対策方法として、いつ・どんな対策をしたらいいのか、過去問にはどう取り組むのかよいか、家庭で保護者様ができるサポートにはどのようなものがあるかなどをご紹介します。
①【時期・教科別】受検対策の紹介!
本格的に中学受検を意識し始めるご家庭も多い小学校4年生から入試直前期まで、時期別にどのようなことを意識して受検に向けた準備をしていくのがよいのか、その目安をお伝えします。
(1)小学4年生
学校での学習内容も少しレベルアップする4年生では、都立中高一貫校の入試に必要な思考力・分析力・表現力の土台となる国語・算数・理科・社会の4科目の学習内容を定着させることが大切です。それに加えて、この時期にご家庭での学習習慣をしっかりと身に付けさせましょう。
| 算数 | 桁数の多い計算や小数・分数を含む計算を速く・ていねいにできるように練習しましょう。展開図や見取り図など、受検でもよく出題される内容を学習するので、苦手な分野を作らないようにしたいですね。 |
| 国語 | ある程度まとまった分量の文章を読むことに慣れさせましょう。広く様々なジャンルの文章に触れ、要旨を捉える練習をしましょう。 |
| 理科 社会 |
学習の基礎・基本となる知識を固めましょう。 |
(2)小学5年生
都立中高一貫校の受検に必要な報告書の対象になるのは5年生と6年生の各教科の成績です。都立中高一貫校の受検を検討しているのであれば、すべての科目で学校での学習活動にも十分に取り組む必要があります。
| 算数 | 文章から条件を読み取って整理したり、論理的に考える力を身に着けましょう。同時に、基礎計算力も伸ばしていきましょう。 |
| 国語 | 「知っている」だけでなく「使いこなせる」言葉を増やせるよう、語彙の習得に努めましょう。適性検査では、自分の考えを自分の言葉で相手に伝わるように書く力が求められます。 |
理科 |
フィールドワークを通して様々な課題を発見することを大切にしている南多摩中等教育学校を目指すのであれば、身近なできごとや現象に対して興味・関心を持ち、様々な「気づき」を得られるようにしましょう。博物館や科学館などに出かけたり、図鑑や地図など、様々な資料に触れたりする機会を意識的に作ることをおすすめします。 |
(3)小学6年生(4月〜6月)
いよいよ勝負の6年生。生徒様の得意・不得意や南多摩中等教育学校の配点等も考えながら、準備を進めましょう。
| 適性検査Ⅰの対策 | 読解問題に力を入れましょう。特に、文章を正確に読み取る力は、適性検査Ⅱの問題を解いたりするうえでも重要です。 |
| 適性検査Ⅱの対策 | 実験や観察の過程を説明・分析したり、資料から分かることについて考察したりする問題の演習をしましょう。 |
(4)小学6年生(7月〜8月)
「受験の天王山」とも言われる夏。特に夏休み中は生活リズムを整え、目標を持って計画的に学習を進めましょう。
| 適性検査Ⅰの対策 | 問題3の作文の練習に力を入れましょう。1度解いただけで終わりにするのではなく、書いたものは何度も読み返しすいこうして、よりよい文章を書けるように練習しましょう。 |
| 適性検査Ⅱの対策 | 算数分野は、中学入試の定石と呼ばれるような問題は一通り解き終えておきましょう。理科や社会の分野にまたがる問題に関しては、複数の資料を総合的に活用する問題への対応力を身に着けるため、どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析し、記述式の問題でしっかり得点できるようにしましょう。 |
(5)小学6年生(9月~11月)
実はスランプに陥る生徒様も多い秋。モチベーションを保てるような工夫が必要ですが、いよいよ過去問に挑戦しはじめる時期でもあります。過去問の活用方法については、このあと詳しくお伝えします。
演習後は丸付けをするだけではなく、その問題の注目すべきポイントや別解など、自分の答案と解答・解説をよく見比べて、自分の苦手や弱点などの気付いたことをメモしながら学習を進めましょう。
(6)小学6年生(12月~1月)
受検直前期は、出題形式の似ている学校の過去問も活用しながら問題演習に取り組みましょう。
この時期は新しいことをインプットするよりも、記述問題でしっかり得点できるようにアウトプットする力を高めたり、間違った問題をていねいに復習するなど、得点力を伸ばせるように意識して学習に取り組みましょう。
②いつどうやるの?過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的は2つあります。1つ目は問題の出題形式を知り、傾向を掴むためです。もう1つは時間の感覚を掴むためです。適性検査は、問題文が長く、多くの作業が求められるため、いかに正確に・すばやく課題を処理していけるかが得点の鍵になります。
また、限られた時間の中でどの問題を優先し、どの問題を後回しにするのかを判断する力はもちろん、試験時間の始めから終わりまで集中力を切らさないようにする訓練も必要です。
ですので、
・過去問で解けなかった問題は今の時点での弱点!復習するポイントの発見に使用して、間違えた問題はよく復習し、できるまでチャレンジする
・時間を測って本番のスケジュール通りに解く
この2つを意識すると、過去問を最大限に活かせます。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
過去問を解き始めるのは、小学校の学習範囲が一通り終わり、間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある6年生の秋(9月から11月)ごろからをおすすめしています。
それ以降の期間は、間違えた問題にもう1回挑戦したり、他校の過去問から似たようなタイプの問題を解いて実践力を鍛えましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第1志望でしたら5年分程度、併願校として受験する場合も、2・3年分は必ず解いてみましょう。特に、南多摩中等教育学校の独自作成問題である適性検査Ⅰと、配点の大きい適性検査Ⅱの大問3は、手に入る分はできるだけすべて解いておくことをおすすめします。「すべて解いた」というだけでも、自信につながるはずです。
過去問は一度できた問題を何度も繰り返し解く必要ありません。できる問題を何度も繰り返し解くよりも、今できていないものを一つでも多くできるようにすることのほうが効率よく合格に近付けると考えるからです。できなかった問題の復習には徹底的に時間をかけ、できるまで挑戦しましょう。
③ご家庭で実践!保護者様にできるサポートとは?
(1)生徒様の「なぜ?」を大切にする
フィールドワークなどの独自の教育活動を通して、探究的な学習に力を入れている南多摩中等教育学校。課題発見力を育てることは、入学検査の突破に向けてはもちろんのこと、入学後の学習活動にも役に立つはずです。
生徒様が身近なできごとや現象に対して興味・関心を持ち、様々な「気づき」や「なぜ?」を得られるよう、博物館や科学館などに出かけたり、図鑑や地図など、様々な資料に触れたりする機会を意識的に作り、疑問に対しては親子一緒に向き合うことで、知識と経験の引き出しを増やしましょう。
生徒様の「なぜ?」に対して、保護者様は答えを教えるのではなく、あくまでも答えにたどり着くための伴走役に徹するように気をつけてください。
(2)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けをする
生徒様と向き合っていると、様々な場面でついつい、保護者様やご兄弟、他の生徒様と比較してしまいたくなってしまうときがあるものです。ですが、生徒様一人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気に火が着くタイミングは異なります。
他の人と比べたくなったり、口出ししたくなる気持ちはぐっと堪えて、生徒様ご本人の変化に目を向けましょう。そのことが、多感な時期の生徒様の自尊心を守ったり、親子間の良好な関係を築くことにもつながります。
受検期の親子関係は、その後も大きく影響する場合が多いです。中学受検が、親子の絆を強める1つのきっかけになるとよいですね。
(3)健康管理とメンタルサポートをする
小学校高学年は思春期に差し掛かり、気持ちが不安定になりやすい時期です。普段の学校生活に加えて受検勉強と、想像する以上に忙しく、大人が気が付かないところで不安を抱えていたり、プレッシャーと戦っていたりするものです。
だからこそ、生徒様にとって最も身近な存在である保護者様に力を入れていただきたいのが、健康管理とメンタルサポートです。
入学検査の本番だけではなく、その日に向けて生徒様がベストなコンディションで受検勉強に向き合えるように、食事や睡眠時間等のサポートはもちろん、ストレスや不安、心配事を抱えたときに相談しやすい関係性作りや、生徒様が一人で心を落ち着かせたり、集中したりできるような環境づくりをしてください。
まとめ
南多摩中等教育学校は、「人間力の南多摩ー心・知・体の調和」を教育理念とし、フィールドワーク活動やライフ・ワークプロジェクト、ワールド・ワイド・ラーニングなど、様々な独自の教育活動を行っている学校です。
各学年でテーマを設定し、段階的に探究活動を深化させていくことで、6年間を通して自分の興味関心や特性を深く理解し、個々のキャリアデザインや進路実現につなげています。
入学検査は一般枠募集のみで、調査書と適性検査の総合得点で入学者を決定します。適性検査Ⅰが独自作成問題、Ⅱは都立中高一貫校の共同作成問題ですが、適性検査Ⅱの大問3の配点が高く、この問題でしっかり得点できるかどうかが合格を左右すると言えます。
ご家庭では、生徒様がよりよい状態で本番を迎えられるよう、健康管理や精神面でのサポートに力を入れてください。また、身近な現象やできごとから生徒様が持つ「なぜ?」という疑問を大切にし、解決に向けた考えをサポートしてあげましょう。
入学後も、生徒様が自分から学習に向かう「向学心」を持てるように、生徒様の成長に目を向け、前向きな声掛けを心がけてください。合格に向けて頑張る生徒様、保護者の皆様を応援しています。
【参考文献】
・声の教育社「東京都立南多摩中等教育学校2025年度用スーパー過去問」
・都立南多摩中等教育学校ホームページ
・令和7年度東京都立南多摩中等教育学校学校案内
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら