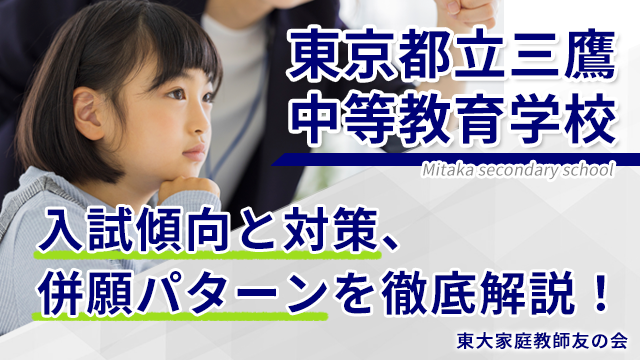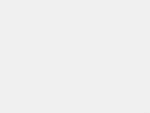1. 東京都立三鷹中等教育学校とは?

三鷹中等教育学校は、「気力を起こして我が身をためそう」を校訓とし、思いやり・人間愛をもった社会のリーダーの育成を基本理念にした教育を行っています。ここでは、三鷹中等教育学校の魅力である国際理解教育・学習指導・ICT教育についてご紹介します。
①日本の伝統文化の理解から始まる国際理解教育
三鷹中等教育学校の国際理解教育は、日本の伝統や文化を理解することから始まります。日本の良さを語れるリーダーの育成を目指して、能楽体験や農業体験など、様々な伝統文化体験のプログラムが用意されています。
また英語の語学力の向上だけでなく、海外修学修学旅行や海外ボランティア研修、他国の生徒との交流活動など、中高一貫校の長所を活かして広く海外に視野を向けられるような取り組みを充実させています。
②先進的で手厚い学習指導
独自の学習達成指標「三鷹スタンダード」を設定し、身に着けるべき学力を明確に示しています。基礎から応用まで、学習内容を確実に身に着けられるよう、習熟度別少人数指導や放課後の補習・個別指導、隔週での土曜授業などが行われます。
さらに、
・探究的な学び推進事業 |
などに指定されており、幅広い分野で先進的な学びを得ることができます。
③ICT機器を活用した多様な教育活動
「三鷹中等教育学校=ICT」というイメージを持つ方も少なくないほどのICT先進校です。「デジタルを活用したこれからの学び研究校」の指定を受け、すべての教科でICT機器を活用した授業を行うとともに、IntelやAdobe社と連携したメディアラボの設置、自由解放のPC教室などの環境が整っており、個に応じた学びと協働的な学びの両方を実現させています。
一人に1台貸与されるタブレットPCは、授業だけでなく家庭学習や生徒・保護者・教員との連絡などにもフル活用されています。
2. 最新!2025年度向け東京都立三鷹中等教育学校の入試傾向

三鷹中等教育学校は一般募集のみで、適性検査は他の都立中高一貫校と同様、2月3日に行われます。ここでは入試の概要や、小学校での学校生活の様子について記載された報告書の点数の換算方法、2024年度入試の適性検査で特徴的だった問題や合否を分けた問題について解説します。
①入試の概要
三鷹中等教育学校の募集人数は、160名です。2025年度から男女別定員の廃止が決まっているため、出願状況にも変動が見られそうです。
入学者は、小学校5・6年生の成績に基づく報告書と、試験日当日の適性検査の結果によって決定します。配点は、報告書(200点満点)、適性検査Ⅰ(45分、100点満点を300点満点に換算)、適性検査Ⅱ(45分、100点満点を500点に換算)の1000点満点です。
2024年度の倍率は4.81倍で、都立中高一貫校の中では最も高倍率でした。
試験問題は、適性検査Ⅰ・Ⅱの大問1が独自作成問題です。1000点満点のうち、半分の500点が独自作成問題の得点なので、三鷹中等教育学校の受検を検討するのであれば、独自対策問題の対策が必要不可欠になります。
②報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の成績を点数化したものです。
各評価の評定を、
|
評定3=40点 評定2=20点 評定1=5点 |
とし、それらの合計(640点満点)を200点満点に換算します。
③適性検査Ⅰ
三鷹中等教育学校の独自作成問題です。文学的文章が二つの出題される点が大きな特徴です。
文章1は、書道教室での指導を通して、文字や表情が生き生きしていく生徒たちを見て感心する主人公の様子が描かれており、文章2では「自信が持てるようになるあんバタートースト」を提供しているカフェの店主から、トーストの名前の由来を聞く主人公の様子が描かれています。
ここでは、適性検査Ⅰの配点の50%を占める、〔問題3〕の作文について解説します。
人が自信を持って生きていくためには、周囲の人とどのような関わりを持つことが必要だと考えるか、文章1、2の内容を踏まえ、三百六十字以上四百字以内で具体例を挙げて説明する、という問題です。
文章1は、適切なアドバイスをもらったり認められたりすることで、自分だけの個性に気付いたり、自分に自信を持てたりすることに繋がるという内容で、文章2は、自分の特性を活かすことが自信に繋がることに加えて、周囲の人によって自分のよさや自信が引き出されるという内容でした。これらをふまえ、周囲の人にヒントをもらったり刺激を受けたことが自信に繋がった体験などを具体的に上げて書きましょう。
全体の構成としては、
|
内容1:文章1、2の内容について簡潔に述べる 内容2:周囲の人との関わりが自信に繋がった具体例を述べる |
という、尾括型が最も書きやすいでしょう。〈きまり〉に示された条件に従って書くことに加え、誤字脱字がないかや、適切な言葉遣い・言葉選びができているかに気を付けましょう。
三鷹中等教育学校の作文では、自分とは異なる他者との関わりについて、自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。日頃から様々なことに自分なりの考えを持ち、それを文章として書く練習をしましょう。良い作文を書くためには、良い文章に多く触れることが大切です。特に文学的文章の出題が多い三鷹中等教育学校を目指すにあたっては、日頃から読書に親しむ姿勢を大切にしましょう。
➃適性検査Ⅱ
三鷹中等教育学校の適性検査Ⅱは、総合得点の50%(=500点分)を占めており、適性検査Ⅱの出来が合否を左右すると言っても過言ではありません。
問題は、大問1のみ独自作成問題で、500点のうち200点分と、大きな比重を占めています。大問1が「グリーンウォーク」という学校行事の準備をテーマにした、速さや条件整理などの算数分野の問題で、論理的な思考力や判断力をはかる問題です。大問2は社会分野からの出題で、公共交通機関の利用について、複数の資料や会話文から読み取れることや考えたことを表現する力が試されています。最後の大問3は理科分野からの出題で、摩擦についての実験のねらいや内容を読み取り、結果を比較して考えられることを記述する問題でした。
ここでは、独自作成問題の大問1について説明をします。
|
〔問題1〕
〔解説〕 |
三鷹中等教育学校では、図を書く問題がよく出題されていますが、グラフを書く問題はあまり出題頻度が高くありません。ですので、戸惑った受検生も多かったことでしょう。丁寧に問題文を読み、単位互換の計算が正確にできれば、決して難しい問題ではなかったはずです。
|
〔問題2〕
〔解説〕 |
円周率を使った計算は、三鷹中等教育学校では毎年出題されています。小数第二位まで計算しなければならないことから、計算の正確さが求められる問題だと言えます。
〔問題3〕は提示された3つの総合順位の決め方の案の中から、自分がイベントの参加者ならば、どの案が最もよいと考えられるかを記述する問題でした。複数の方法を比較して、どちらがより良いかを説明する問題は、2023年度も出題されています。
3つの案それぞれの各チームの得点は、資料から読み取り、計算することができますが、答えにたどり着くまでの作業量が多く、後回しにするのが賢明な判断でしょう。この問題は合否にはそれほど影響しない問題だったと考えられます。
〔問題1〕や〔問題2〕に似た形式の問題が、過去に共通問題で出題されているので、そういった問題に触れたことがあるかどうかが、問題に対処する時間や正確さを左右したと言えます。
⑤出題形式の似ている学校
出題形式の似ている学校としては、国公立中学校をはじめとする適性検査・思考力型の入試問題を行っている学校が挙げられますが、特に問題演習を行ううえで必ず解いておきたいのが、都立中高一貫校の共通作成問題です。
適性検査Ⅱの大問Ⅰは独自作成問題ですが、似たような出題パターンの問題が、過去に共通問題として出題されています。こういった問題に触れたことがあるかどうかで、問題に対処するスピードや正確さは大きく変わってくることでしょう。
また、独自作成問題を出題している千代田区立九段中等教育学校の問題なども、複数の資料の読み取りなどが課される問題が多く、似た出題傾向だと言えます。
3. 東京都立三鷹中等教育学校を受検する際の併願パターン紹介!

都立中高一貫は、2月3日に一斉に一般入試を行います。そのため基本的には私立中学を併願することになります。
ここでは、三鷹中等教育学校と近い偏差値帯の学校を併願するパターンと、適性検査・思考力検査型の学校を併願するパターンを想定し、ライターが過去に指導した生徒様の併願校も参考にしながら、おすすめの併願校をご紹介します。なお、この併願校情報は2024年度の入試をもとに作成していますので、2025年度の入試情報に関しては各校の募集要項を必ずご確認ください。
①同偏差値帯併願パターン
過去の生徒様の動向を見ると、総武線・中央線沿いに位置する学校が選ばれるケースが多いように感じます。
三鷹中等教育学校に通う生徒の75%は東京都市町村部から通学している生徒であるため、通いやすさを意識した併願校選びが行われているようです。
立地も踏まえたうえでのおすすめの併願校をご紹介します。
(1)1月入試
・市川中学校 |
(2)2月1日
・中央大学附属中学校 |
(3)2月2日
・大妻中学校 |
(4)2月4日以降
・成蹊中学校 |
②適性検査・思考力型入試を重視した併願パターン
こちらは、都立中高一貫校を目指している受検生をメインのターゲットに行われる、適性検査型や思考力型、公立型などと呼ばれる入試を実施する学校を中心に併願するパターンです。
宝仙学園理数インター中学校や広尾学園小石川中学校は、他の都立中高一貫校を受検する生徒様にも併願校としてよく選ばれている印象があります。
(1)1月入試
・市川中学校 |
(2)2月1日
・宝仙学園理数インター中学校 |
(3)2月2日
・ドルトン東京学園中等部 |
(4)2月4日以降
・東京都市大学等々力中学校 |
4. 東京都立三鷹中等教育学校の受験対策!

都立中高一貫校の中でも特に高倍率の三鷹中等教育学校。合格に向けて、いつどんな対策をしたらいいのか、過去問にはどのように取り組むのかよいか、家庭で保護者様ができるサポートにはどのようなものがあるかなど、具体的な受検対策方法について解説します。
①【時期・教科別】受験対策の紹介!
ここでは、小学校4年生から受検直前期まで、時期別・教科別にどのような点に注目して、何をしていけばよいのかをご紹介します。
(1)小学四年生
学習内容もレベルアップする4年生は、学力差が付きはじめる時期でもあります。この時期はまず、学習習慣を定着させることに加え、都立一貫校の入試に必要な、思考力・分析力・表現力の土台となる4教科の学習にしっかり取り組み、苦手を作らないことが大切です。
算数:都立一貫校の入試でも出題される、周期算や植木算などの学習に取り組み、桁数の多い計算や小数・分数を含む計算も、素早く丁寧にできるように練習しましょう。
国語:興味・関心を広げる意味でも、広く様々な本を読むようにしましょう。さらに、本の内容を簡潔にまとめられるようにしておくと、作文を書く際の練習にもつながります。また、習った漢字を使い読みやすい字で文字を書くように心がけましょう。
理科・社会:身近な事象に幅広く興味を持てるよう、様々な体験・経験ができるようにしましょう。科学館や博物館などに行って本物に触れる経験をするのも効果的です。
(2)小学五年生
都立中高一貫校受験に必要な「報告書」の対象になるのは、5年生からです。主要4科目に限らず、音楽や図工、家庭や体育、外国語なども含めてすべての科目において、学校の学習活動に十分に取り組み、評定をとっておくことが大切です。
算数:基礎計算の正確さとスピードを鍛えるとともに、論理的に考える力や条件を整理する問題の解き方などを身に着けましょう。
国語:知っている言葉を増やすだけではなく、使いこなせる言葉を増やせるよう、語彙の習得に努めましょう。学習に関わらず、幅広い分野の本を読むようにし、分からない語句や言葉は調べたりすることを習慣にしましょう
理科・社会:学校や塾で習ったことを丁寧に復習し、知識を問う問題には確実に答えられるようにしましょう。また、身の回りの気になる現象については、図鑑などを使って自分で調べたりできるようにしましょう。
(3)小学六年生(4月~6月)
いよいよ勝負の6年生の幕開けです。6年生でも引き続き、学校の学習もおろそかにしないようにしましょう。
算数:適性検査Ⅱの独自作成問題を意識し、条件を整理する問題や円周率を用いる問題、図やグラフを書く問題を中心に演習を重ねましょう。どのような方法をとれば正解にたどり着くことができるのか、考えた過程も書くようにすることが大切です。
国語:読解問題に力を入れましょう。特に、複数の文章から共通点を探したりするような問題は頻出です。文章の流れはもちろん、核となる登場人物の心情の変化を読み取れるようにしましょう。
理科:実験や観察の過程を説明したり、結果を分析・考察したりする問題の演習を行いましょう。重要なデータには印をつけるなど、速く・丁寧に解くためのコツを身に付けましょう。
社会:広く社会の問題に目を向けることができるよう、新聞やニュース、現代社会の問題を扱った小・中学生向けの新書などを読むようにするとよいでしょう。さらに、様々な問題に対して自分はどのように考えるか、どのような解決策が考えられるかなど、具体的に言葉にしてみると、適性検査Ⅱの記述問題はもちろん、作文の問題の対策にもつながります。
(4)小学六年生(7月~8月)
この時期の頑張りが合格を左右すると言っても過言ではない夏。特に夏休み中は、生活リズムを整え、目標を持って計画的に学習を進めたいですね。
算数:初見の問題への対応力を身に着けたい時期です。特に頻出の条件の整理、場合の数などの問題では、根気強く問題に取り組む力が求められます。時間が十分にある夏だからこそ、最後まで向き合う姿勢で臨みましょう。
国語:作文の対策に力を入れましょう。評論文では、読んだ文章のキーワードになる言葉を短くまとめる練習をしたり、筆者の主張を要約したりする練習をすると効果的です。
理科・社会:複数の資料を総合的に活用する問題の対策を行いましょう。どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析し、記述式の問題でしっかり得点できるようにすることが大切です。
知識のインプットは夏までに完成させられると、秋以降の演習に不安なく取り組んでいけるでしょう。
(5)小学六年生(9月~11月)
秋には、いよいよ過去問に挑戦しましょう。過去問の解き方については、このあと詳しくお伝えします。
演習後は丸付けをするだけではなく、その問題の注目すべきポイントや別解、など、自分の答案と解答・解説をよく見比べて、自分の苦手や弱点などの気付いたことをメモしながら学習を進めましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
受検直前期のこの時期は、過去問の復習はもちろん、出題形式の似ている他校の過去問なども活用しながら問題演習に取り組んで仕上げをしていきましょう。
1月入試を受験する場合は、受験に向けてのペース配分も含めて本番に向けて調整する練習をしましょう。
②【いつやる?どうやる?】過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的は2つあります。1つは、問題の出題形式を知ったり、傾向を掴むためです。もう1つは時間の感覚を掴むためです。入試本番では、決められた時間で少しでも多く点数を取る必要があります。
限られた時間の中で、どの問題を優先し、どの問題を後回しにするのかを判断する力はもちろん、試験時間の始めから終わりまで集中力を切らさないようにする訓練も必要です。
ですから、過去問に取り組む時には、入試本番と同じスケジュールで取り組んでみることをお勧めします。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある6年生の秋(9月から11月)ごろから過去問に取り組むことをお勧めします。
過去問を解いて見えてきた課題は、冬までにしっかり解消しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第一志望でしたら、5年分程度、併願校として受験する場合も、2・3年分は必ず解いてみましょう。三鷹中等教育学校の独自作成問題である適性検査Ⅰと適性検査Ⅱの大問1に関しては、独自作成が始まった平成28年度以降の問題をできるだけすべて解くことをお勧めします。
過去問は何度も繰り返し解く必要ありません。できる問題を何度も繰り返し解くよりも、今できていないものを一つでも多くできるようにすることの方が、合格への近道だからです。その分、過去問演習で間違えた問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度もチャレンジしてください。
③中受保護者必見!保護者様にできるサポートとは?
(1)読書経験を積ませる
三鷹中等教育学校の適性検査Ⅰでは、文学的文章が2題出題される点が他校とは大きく傾向の異なる点です。幅広く継続的に読書に親しむ姿勢を育てることで、文章を正確に読み取る力、豊かな表現力を身に着けられるようにサポートしましょう。
親も本を読む子どものほうが、まったく本を読まない親の子供よりもよく本を読む習慣があるという調査結果もあるので、保護者様が本を読む姿勢を生徒様に見せたり、親子一緒に本を読む時間を作ることで、生徒様にも自然と読書の習慣が身に着けられるのではないでしょうか。
親子で同じ本を読み、感想を交換し合ったりすることも、自分の意見を言語化するという点で、作文の練習にもつながります。
(2)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けを
生徒様と向き合っていると、様々な場面でついつい、保護者様やご兄弟、他の生徒様と比較してしまいたくなってしまいますよね。ですが、生徒様一人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気に火が着くタイミングは異なります。
他の人と比べたくなる気持ちをぐっと堪えて、生徒様ご本人の変化に目を向けるようにしましょう。そのことが、多感な時期の生徒様の自尊心を守ることにもつながります。
模試の結果一つをとっても、保護者様の声掛け一つで生徒様の受け止め方も変わってきます。生徒様が少しでも前向きな気持ちで自分から学習に向き合えるような声掛けを心がけましょう。
(3)健康管理とメンタル面のサポートをする
心身ともに大きく成長する大切な時期である小学校高学年。多感な時期であることに加え、普段の学校生活に加えて受験勉強と、大人が想像する以上に忙しく、負担の大きい受験生生活。大人の気が付かないところで不安を抱えていたり、プレッシャーと戦っていたりするものです。
だからこそ、健康管理とメンタル面のサポートは、保護者様にしかできない、最も力を入れていただきたいサポートです。
受験本番はもちろん、生徒様が一日一日をよりよい状態で過ごせるように、食事や睡眠時間等のサポートはもちろん、生徒様がストレスを抱えたりした際に相談しやすい関係性作りや、一人で心を落ち着かせたり、集中したりできるような環境づくりを行ってください。
最後に
三鷹中等教育学校は、「ICTと言えば三鷹中等」とも言われるほどに先進的なICT環境と日本を知ることから始まる国際理解教育、そして手厚い学習指導や多くの学校行事などが特色で、都立中高一貫校の中でも特に人気のある学校です。
入試は一般入試のみで、調査書(5・6年生のすべての科目が対象)と適性検査の総合得点で入学者を決定します。適性検査Ⅰと適性検査のⅡの大問1は、独自作成問題が使用されています。
合格のためには、総合得点の1000点分のうち200点を占める、適性検査の大問1が合否を左右すると言っても過言ではないでしょう。近年は都立中高一貫校の共通問題で過去に出題されたパターンと似たパターンがよく出題されているので、三鷹中等教育学校の過去問だけではなく、都立中高一貫校の共通問題の過去問も解いておくとよいでしょう。
心身ともに大きく成長する、多感な時期の生徒様。健康面やメンタル面での保護者様のサポートは必要不可欠と言えます。入学後も、生徒様が少しでも自分から学習に向かう「向学心」を持てるように、生徒様の成長に目を向け、前向きな声掛けを心がけるようにしましょう。
すてきな春を迎えられるよう、お祈りしています。
【参考文献】
・東京都立三鷹中等教育学校ホームページ
・東京都立三鷹中等教育学校学校案内
・東京都立三鷹中等教育学校youtube
・声の教育者「東京都立三鷹中等教育学校2025年度用スーパー過去問」
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら