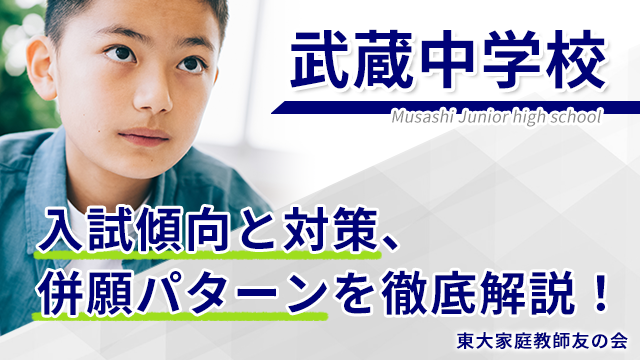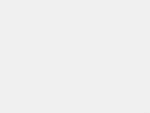1. 武蔵中学校とは?

開成中学校、麻布中学校と共に、男子御三家の一角を成す武蔵中学校。
東京都練馬区に校舎を構え、設立から120年以上経過する歴史ある中学校です。
中高一貫教育の中で、特に中学生の間は知的探究心を育む事に重点が置かれます。
例えば、中学一年生の時に、地学巡検として、箱根に行き、箱根山の地形や岩石を観察・スケッチをします。
また、中学三年生時には、天文実習として清里に行き、天体観測を行います。
校内でも、古文書を読んだり、実験をしたりと、物事の根本に当たることで、自ら調べる力を育みます。
制服が無く、自由な風土が特徴ですが、武蔵中学校の本来目指す先は学問の自由。
生徒様が教えられて学ぶのでは無く、自ら疑問を持ち、自由に自らで謎を解く、知的探究心を育む事を大切にしています。
武蔵中学校での学校生活は、今後大学生・社会人になった時に、大きく飛躍できる礎となるでしょう。
2. 武蔵中学校の入試傾向について

試験科目は算数・国語・理科・社会の四科目。
それぞれの配点と試験時間は以下の通りです。
|
・算数:100点(50分) ・国語:100点(50分) ・理科:60点(40分) ・社会:60点(40分)
|
非常に独特な問題が出題されますが、総じて言える事は、問題文が長い事・自分の考えを記述する事です。
どの科目も、問題文が非常に長く、試験時間内に内容を理解しながら問題を解くには、高度なレベルが要求されます。
また、生徒様ご自身の考え方を問われる問題が多く、単なる暗記だけではなく、日頃から常に問題意識を持って生活しているかが問われる試験となっています。
当たり前の事を当たり前だと思わずに、何故だろう?という疑問を持って探求していく。
そのような探求心旺盛な生徒様が武蔵中学校の入試問題にフィットするでしょう。
①算数
算数は、大問四問で出されることが多く、出題単元はある程度決まっています。
・平面図形
・場合の数
・数の性質・速さ
・割合と比
・仕事算
が頻出単元です。
それぞれの単元を詳しく見ていきましょう。
(1)平面図形
平面図形は毎年出題されており、相似と比を用いた問題や、面積の問題が多く出題されています。
大問で出題されることが多く、部分的に難度の高い問題も出題されておりますが、全く手を出せない問題はありません。確実に取れる所を取っていきましょう。
(2)場合の数
場合の数も、大問でほぼ毎年出題される論点です。
調べ上げて、漏らさず数え上げる・場合分けする問題が多く、完答するにはかなり困難な問題が出題されます。
図形・数の性質絡みの場合の数が出題されており、解法暗記では対応出来ない問題です。
文章の意味を取り違えてしまうと、致命的になりますので、しっかり確実に解く練習が必要です。
(3)数の性質
数の性質も、小問や場合の数との融合問題と合わせると、ほぼ毎年出題されている論点です。
最小公倍数・最大公約数の問題や、分数の性質、規則性、つるかめ算や不定方程式の問題などが見られます。
場合の数との融合問題は、難しい問題になりがちですので、過去問で慣れる必要があります。
(4)速さ
速さも大問でかなり出題されており、図や絵、ダイヤグラムを書いて内容理解する問題が相当に多く、最小公倍数が絡む問題もよく見ます。まれに、通過算や時計算といった特殊論点も出ています。
ちなみに、2024年度入試では、速さの問題が合否を分けたと思われます。ダイヤグラムを正確に書けると完答出来たはずですが、計算だけでゴリ押ししようと思うと、途中で混乱してしまう問題でした。
いかに分かりやすく図示するか、これがキーポイントとなります。
(5)割合と比
割合と比は、最近出題頻度が減っておりますが、依然として対策すべき単元と言えるでしょう。
過去10年の中で、食塩水や損益算の問題が大問で出題された年もあります。
平面図形に絡む比の問題は、毎年と言って良いほど出題されておりますので、比の問題全体としては、やはり重要論点です。
(6)仕事算
最後に、仕事算についてです。こちらは、出題される場合、よく小問で出されます。
仕事算の中でもポンプを使用した水槽の問題がよく出題されています。
毎年出るような単元ではありませんが、対策は必要と言えるでしょう。
尚、2023年には仕事算の一部であるニュートン算が大問で出題されました。
②国語
例年、大問一題で、物語文か説明文、まれに随筆文が出題されています。
設問の九割部分は内容理解を問う記述式問題で、残り一割程度は漢字や語句の問題となっています。
文章の分量は中学受験問題としてはかなり多く、何度も読み返す事はほぼ不可能です。
長い文章を集中力を切らさずに読む訓練は必須となります。
また、記述式問題は字数制限が無く、空欄が与えられているだけです。
設問毎に空欄の大きさは違いますので、どのくらいの分量を書けば良いのか、目安はあります。
しかし、小学生の生徒様にはとっつきにくい問題であることには違いありません。
長い記述を論理的に、矛盾無く書く訓練も必要となるでしょう。
2024年度入試では、昭和初期の文章が出題されました。仮名遣いや漢字表記は現代国語に修正されておりましたが、文体はそのままであったため、とっつきにくい生徒様が多かったと推測されます。
このような文章でも読みこなせたかどうかが合否を分けたのではないか、と考えます。
日頃から、時代を問わず、様々なジャンルに読み慣れることが必要でしょう。
③理科
大問三つで出題されることが多く、最後の三番の問題で通称「おみやげ問題」が出題されます。
生物・地学分野の出題が多く、次いで化学・物理の順番で出題されています。
どの分野でも記述問題は出されており、考察問題の比率が高い点に特徴があります。
一方、難関校特有の物理・化学の計算問題は過去には殆ど出題されておりません。
しかし、2024年度入試で、化学の計算問題が出されました。多くの生徒様は計算問題を疎かにしていたのではないか、と思われますので、ここが合否を分けたポイントだったと推測されます。
来年度に向けては、しっかり全体的に学習する必要があるでしょう。
生物・地学分野で特に言えることですが、高度な暗記も必要となります。
植物・動物・天体・地層・天気などが出題される場合、暗記が必要とされる記号問題が、必ずと言って良い程出題されます。
最後に、武蔵中学校特有の問題である「おみやげ問題」についてお話します。
毎年出題されておりまして、学校側が用意した物を考察して、自分なりの考え方を記述する問題となっています。
2024年度では、のり・リップクリームについての問題が出題されたように、身の回りのものを題材にすることが多く、他には、針金(2022年度)、磁石(2020年度)、虫眼鏡(2018年度)などが題材となっていました。
④社会
毎年、大問一題で、非常に長い文章やグラフ・図表などが前提として与えられてから、10問~15問程度の設問という構成です。
文章の内容としましては、ある一つの事柄についての歴史的推移が書かれていまして、例えば、教育制度(2022年度)・新聞(2021年度)・選挙制度(2016年度)などが過去に出題されました。
設問形式としましては、国語と同様、字数制限の無い記述問題が中心です。
社会に関する記述問題は勿論、「近年の投票率の低さはどのような問題をもちますか?」といった時事問題に関して、生徒様の考えを問う記述問題も出題されています。
2024年度では「ワークライフバランスを保つことが、現代社会が抱えるさまざまな課題の改善にどう結びつくのか、それらの課題のうちの1つをあげて説明しなさい。」という問題が出題されました。
時事問題で出てくる言葉を知っているだけではなく、その言葉の背景まで考えているかが問われる問題でした。
このような問題に対処出来ることが武蔵中学校合格の条件になってくるでしょう。
また、文章やグラフ・図表の内容を基に客観的に答える記述問題、即ち、国語に似た問題も出題されます。
国語が得意な生徒様には有利に働くでしょう。
記述問題が中心ではありますが、意外にも基本的な知識問題も、しっかりと出題されています。
ですので、単語レベルの暗記も決して疎かに出来ません。
最後に、高頻度で出ているものがありまして、それは日本地図の設問です。
地図帳片手に場所を確認する習慣をつけて下さい。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
武蔵中学校の問題は、非常に独特ですので、中々似ている中学校を探すのは難しいです。
ただし、中では麻布中学校は似ていると考えます。特に、国語と社会については、武蔵中学校と似ています。
武蔵中学校の過去問や志望校別対策の演習題に不足が生じた場合、使用してみては如何でしょうか?
3. 武蔵中学校を受ける際の併願パターンは?

①1月受験校
【受験校の例】
西武文理中学校・栄東中学校・東邦大学附属東邦中学校
1月は、練習として、西武文理中学校・栄東中学校が挙げられます。
その後、少し難易度を上げて、東邦大学付属東邦中学校を受けるのが良いでしょう。
しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
【受験校の例】
午前:武蔵中学校
午後:広尾学園
午前入試は武蔵中学校で決まりです。
午後入試は受験しなくても良いと思います。
第一志望校となる武蔵中学校を受験後、相当に疲れると思います。
もし受験されるのであれば、難易度は武蔵中学校並みですが、広尾学園中学校は考えられます。
③2月2日
【受験校の例】
午前:城北中学校(2次)・本郷中学校(2次)・桐朋中学校(2次)
2日の入試を抑え校としてお考えであれば、立地も近い城北中学校(2次)はおすすめです。
本郷中学校(2次)や桐朋中学校(2次)も考えられますが、難易度は高いため、対策は必要でしょう。
午後は、受けなくても良いと思います。
④2月3日
【受験校の例】
海城中学校(2次)・公立一貫校
武蔵中学校とレベル・入試傾向に最も近いのが海城中学校(2次)でしょう。
立地もある程度近いですから、併願校として適切だと考えます。尚、3日に海城中学校を受験されるのでしたら、2日は城北中学校でしっかりと抑えておくのが良いのではないかと思います。
それ以外ですと、入試傾向がある程度近い、公立一貫校も視野に入るかと思います。
⑤2月4日
【受験校の例】
城北中学校(3次)・芝中学校(2次)
2月4日受験をどう考えるかによりますが、抑え校としてお考えでしたら、城北中学校(3次)、武蔵中学校と近いレベルでお考えでしたら、芝中学校(2次)となるでしょう。
2日に本郷中学校(2次)や桐朋中学校(2次)を受験される場合は、4日は城北中学校(3次)が望ましいでしょう。
4. 武蔵中学校の受験対策方法

武蔵中学校を受験・合格するためには、どのような対策を取っていけば良いかを解説します。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
| 算数 |
塾のカリキュラム、もしくは「予習シリーズ」に沿って行って下さい。 平面図形・場合の数・数の性質を習う頃ですから、それらの単元は応用問題まで解けるようにして下さい。 また、今のうちに、文章に出てくる数字や登場人物に、印をつける癖付けをしておきましょう。 情報を整理するために、図や絵を書く訓練もしておくと良いでしょう。 |
| 国語 |
文章の読解は勿論ですが、要約を行う練習をして下さい。文章の長さにもよりますが、100字~150字程度を目安に取り掛かると良いでしょう。 また、読書は欠かさず行ってください。なるべく文章が長い本を読みましょう。 まずは、興味のあるジャンルからで構いません。スポーツや趣味の本でも良いですから、長い文章に慣れていきましょう。 漢字・語句も疎かにせずに行っていきましょう。 |
| 理科 |
夏休みの自由研究課題は必ず行いましょう。 また、日頃から疑問を持って生活して欲しいですね。 身の回りの当たり前にあるものに興味を持って、生徒様自身で調べると良いでしょう。 生き物を飼ったり、毎日の天気を記録するのも良いですね。 また、大手塾では、この学年で生物・地学分野を行います。暗記すべき事項は、しっかり覚えていきましょう。 ここを疎かにしますと、後で苦しくなります。 |
| 社会 |
地図帳を使用した学習が最も効果的です。 小学四年生になりますと、地理の授業が始まります。 都道府県について学習することになりますので、地形と合わせて、地図帳で場所を確認しましょう。 一度見ただけでは定着しませんので、繰り返し見ていくことがポイントです。 また、日頃からご家庭でニュースを見る習慣付けが出来ると良いですね。 ニュースの内容について、ご家庭で会話をしながら、理解を深め、疑問点を生徒様と一緒に調べると良いと思います。 |
(2)小学五年生
| 算数 |
速さ・比と割合・仕事算といった単元も始まります。 平面図形・場合の数・数の性質と合わせて、特に力を入れて学習して下さい。 これらの単元に苦手意識があるようでしたら、小学四年生に遡って復習をして下さい。 |
| 国語 |
前学年と同様に、要約を行いましょう。読書も欠かさず、出来れば毎日読む習慣付けが欲しいですね。 物語文・説明文問わず幅広いジャンルを読めるようにしていきましょう。 少し昔の文体の文章も読めるようになってくると、大変心強いです。 客観的に読むことを意識して、取り組んで下さい。 漢字・語句は、必ず前学年までの復習もお願いします。 |
| 理科 |
やはり自由研究課題は行いたいですし、引き続き、身の回りの物・現象に疑問を持ちつつ、探究心を持って、取り組んで頂く必要があります。 特に興味を持つものがあれば、とことんまで探求するのも、とても良い事です。 化学・物理分野も始まってきますが、とにかく仕組みの理解に努めて下さい。 公式暗記・計算方法の暗記は二の次です。 |
| 社会 |
引き続き地図帳を使用した学習を心掛けて下さい。 授業で数多くの地名が出てくると思います。 それらを全て地図帳で確認する位の気持ちが欲しいですね。 秋頃からは歴史が始まります。 一つ一つの単語暗記は勿論ですが、特に背景や流れを理解するようにして下さい。 |
(3)小学六年生(4月〜6月)
| 算数 |
これまでの復習を中心に少しずつ入試問題に慣れていく時期です。 夏休みから過去問演習に入れるように、苦手単元を無くしましょう。 |
| 国語 |
武蔵中学校の過去問を見始めると良いでしょう。 時間は測らなくても良いですから、解き切って頂き、現状の課題を把握して下さい。 漢字・語句の復習も忘れずに行ってください。 |
| 理科 | 中学受験の試験範囲が終わる頃だと思われます。算数同様、苦手単元を無くすことに力を注いで行きましょう。 |
| 社会 |
公民の授業に入ると思われます。公民の内容を行いつつも、地理・歴史の復習を行わないと、夏休みに大変なことになります。 多くの生徒様が地理・歴史を疎かにしますので、ここでしっかり復習をすれば、他の生徒様を引き離すチャンスとなります。 |
(4)小学六年生(7月~8月)
| 算数 |
武蔵中学校の過去問に入り始めましょう。 夏休み中に3~5年分は行いたい所です。解いたら必ず解き直しをしましょう。 また、過去問だけではなく、塾の復習は必ず行い、全体的に苦手単元が無いようにしていきましょう。 |
| 国語 |
時間を測りながら過去問を解きましょう。夏休みは忙しい時期ですが、読書の時間は少しでも取って頂きたいです。 漢字・語句については、夏休み中に定着させたい所です。 秋以降にまとまった時間は取れなくなりますので、この夏休みが勝負です。 |
| 理科 |
算数同様、過去問に取り掛かりましょう。やはり、3年分は解いて頂きたいですね。 暗記事項で漏れがあるようでしたら、この夏休みに定着させて下さい。また、計算単元についても、基本的な問題は解けるようにした方が良いと思われます。 |
| 社会 |
過去問に取り組んでみて下さい。理科同様、3年分解いて、形式に慣れていきましょう。 地理・歴史・公民の全体的な復習を行いましょう。その際、記述問題を意識して頂き、内容を口で説明出来る様に、練習しましょう。時事問題にも取り掛かりましょう。 |
(5)小学六年生(9月~11月)
| 算数 |
塾の志望校別特訓での演習を中心に、過去問も出来る範囲で解いていきましょう。 この時期は、新しい問題を解くだけではなく、解き直しにも相当程度時間を割いて頂きたい時期になります。 武蔵中学校の算数は、似た論点が出ますので、とにかく解き直しが肝心です。 問題量が足りないようでしたら、「ステップアップ演習」(東京出版)もおすすめです。 |
| 国語 |
算数同様に志望校別特訓と、過去問が中心です。 解き直しも大事です。要点をまとめられるように訓練しましょう。 この時期でも、読書と漢字・語句の確認に、少しでも時間を割いて下さい。 |
| 理科 |
志望校別特訓と、過去問が中心です。 この時期には、「おみやげ問題」への対処法をしっかりと学びたいですね。 書き方・考え方・時間の使い方等慣れで対処できる部分も多いのが、この「おみやげ問題」です。 「おみやげ問題」で足を引っ張らないことが極めて重要ですから、しっかりと特訓しましょう。 その他、全単元的な復習は勿論行って下さい。 |
| 社会 |
勿論志望校別特訓と、過去問に尽きます。 この時期は、長い文章・図表・グラフをどう読み取るのか、それをどう答案にしていくか、という技術的な部分を鍛えていく時期です。 武蔵中学校では、この手の問題で点を落とさないことが肝心です。 この読み取り問題で点を取れれば、社会全体の点数は安定してきます。 |
(6)小学六年生(12月~1月)
| 算数 |
他の併願校に備えた対策をしながらも、武蔵中学校での頻出単元である平面図形・場合の数・数の性質・速さ・割合と比・仕事算に特に注力して下さい。 もっと過去問を遡っていくのも良いかと思います。 とにかく、過去問で出題された問題は、全て解ける位まで、徹底的に行って下さい。 |
| 国語 |
制限時間内に解き切れるか確認する必要があります。 まだ触れていない過去問を使用して、数年分解いておくと良いでしょう。 しばらく触れていないと、いざ本番の入試で思うようにいかなかった生徒様を見てきました。入試本番の数日前には必ず1回分解くようにして下さい。 読書・漢字・語句は最後まで継続して行って下さい。 |
| 理科 |
どの単元も暗記すべき事項の復習をして下さい。 特に力を入れるべき分野は、生物・地学分野でしょう。 頻出単元の植物・動物・天体・地層・天気といった単元は共通点や相違点をまとめておくと、役に立つでしょう。 |
| 社会 |
歴史を中心に復習して下さい。特に江戸時代~昭和時代にかけての問題は毎年出題されています。 時事問題についても、最後までチェックをして下さい。現在の日本における問題点や課題を整理しておきましょう。 |
②武蔵中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
武蔵中学校は、他の中学校ではあまり見ない形式で、独自の入試傾向です。
そのため、過去問の重要性は他の中学校よりも増します。
基本的に全科目とも、一度目に解く際は正規の時間を測って解いてください。
但し、国語だけは、初めて解く際には時間を測らなくても結構です。
しっかりと答案を仕上げることに注力して下さい。
二度目以降は、原則、間違えた問題・不安な問題のみ解き直しを行ってください。
その際も一問毎に、時間を測って行うことで、より効果的になるでしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
勉強が進んでいる生徒様は、夏休み前〜始めていくと良いですが、遅くとも、夏休みが始まる頃には始めていきたい所です。
但し、どのような状況の生徒様であっても、国語だけは、夏休み前から始めた方が宜しいかと思います。
国語は、かなり重たい問題が出ますので、早めに見て頂いて、対策して頂く事をおすすめします。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、出る単元がおおよそ特定されておりますので、過去問を遡る意味があります。
従って、最低10年分、出来れば15年分解いておきたい所です。
まずは時間を測って解き、その後、出来なかった問題を中心に、大問1題につき10~15分程度で、解き直しをします。3周する事をおすすめします。
国語・理科・社会は全く同じ問題が出る可能性は極めて低いです。
よって、過去問の傾向把握、解き慣れが重要になります。10年分程度が宜しいかと思います。
但し、国語と理科の「お土産問題」につきましては、慣れるのに時間がかかるかもしれません。
その場合は、もっと遡って頂くのが良いでしょう。
解き直しは、算数同様、出来なかった問題を中心に行ないます。
時間を計らなくて良いですから、2週程度行えば良いでしょう。
③保護者様に出来るサポート内容
武蔵中学の問題は、物事に対して、生徒様自身の考え方を問う問題が多く出題されます。
常日頃から保護者様が出来る事を列挙していきたいと思います。
(1)生徒様に対する声掛け
例えば、ニュースを一緒に見ている時に、生徒様に対して、
|
「なんで今年の夏は暑いんだろうね」
|
と言った問いかけをしていくと良いでしょう。
そして、生徒様と一緒に調べて、会話をしていくと良いでしょう。
(2)自由研究
小学校で夏休みの課題として出される自由研究。武蔵中学校受験にはもってこいの題材です。
毎年、理科・社会といった内容についての自由研究課題を見つけ、提出するようにしましょう。
その際にも、保護者様からの「なんでそうなるんだろうね?一緒に調べてみよう。」と言ったお声がけをしながら、深掘りして進めてみて下さい。
自由研究そのものにも意味はありますが、文章をまとめる作業も大変重要です。
是非取り組んでみて下さい。
(3)書籍
武蔵中学校入試の根底にあるのは読解力。
しっかりとした長い文章を読み込む読解力が必要です。
生徒様が読みたい本であれば、生徒様にお任せすれば良いですが、それだと偏りが生じます。
保護者様として、ジャンルに偏りが無いように、本を選んであげる事も必要です。
物語文・説明文・随筆文・詩など、偏りなく選んであげて下さい。
忘れてはいけない点としては、少し昔の文章も読んで頂くこと。
現代文だけでなく、少し古い文体の文章も選んで頂けると良いでしょう。
2024年度入試では、昭和初期の物語文が出題されました。
まとめ
武蔵中学校は、御三家の一角だけあって、問題はとても難しいです。
単なる暗記勉強では、到底歯が立ちません。
ですので、受け身で勉強をしていくのではなく、身の回りにある当たり前の事に疑問を持ちながら、主体的に調べるよう心掛けて下さい。
そういった姿勢が勉強にも繋がっていきます。
武蔵中学校は、探究心ある生徒様を求めています。
生徒様自身が考え、解決を導き出していく、その手助けを保護者様に担って頂ければと思います。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
武蔵中学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら