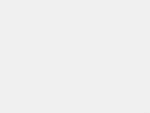1. 桜蔭中学校とは?
桜蔭中学校は1924年に創立された中高一貫の私立中学校で東京都文京区に位置しています。
中学受験御三家の1つに数えられる非常に偏差値の高い学校として知られており、東大合格者数は1学年の1/3程度であることから進学実績も充実しています。
桜蔭では「勤勉、温雅、聡明であれ。」という校訓が掲げられており、知性・上品さだけではなく社会で活躍できる自立した女性の育成を目指しています。
また、「礼と学び」を建学の精神として勉強だけでなく、自立した女性の育成を目的とした「礼法」の授業が100年にわたって実施されています。桜蔭では学識だけでなく品性も身につけた人間性の育成に力を入れています。
2. 桜蔭中学校の入試傾向について
各科目ごとの配点・試験時間は以下の通りです。
| 科目 | 配点 | 時間 |
| 算数 | 100点 | 50分 |
| 国語 | 100点 | 50分 |
| 理科 | 60点 | 30分 |
| 社会 | 60点 | 30分 |
国語・算数に比重を大きくおいた試験です。国語・算数では記述問題に重点を置いており、答えだけでなく解答までのプロセスが求められています。
そのため、勉強の際にはどのような流れで答えに至るのかを意識して取り掛かることが重要です。
また、理科・社会に関しては全分野が毎年出題されており、幅広い知識が問われる傾向にあります。知識の土台を活用した考察問題も出題されるため、早期に知識を身につけ、演習の時間を確保しましょう。
| 国語 算数 | 解答までのプロセスが重視されている |
| 理科 社会 | 幅広く、深い知識が求められている。 |
具体的に各科目の出題傾向について、確認しましょう。
①算数の出題傾向について
近年の入試は試験時間50分、大問4つで構成されています。
第1問の最初の数問は計算問題であるため、ここでミスは許されません。さまざまな分野の問題が扱われるため、全分野で標準問題をクリアさせましょう。
第2問〜4問では特定の分野からの出題となりますが、記述欄が用意されており自身の解答までのプロセスをしっかり図・式に表して説明する必要があります。
また、説明は簡潔にする必要があるため、日頃からの練習が必要不可欠です。
上図は過去5年間の出題分野を示したグラフです。まず、「立体図形」「速さ」「数の性質」「規則性」の分野で約6割を占めており、「立体図形」は毎年出題されている分野となります。
また、桜蔭では「推理・論証」の分野が多く取り上げられています。女子学院でも出題傾向の高い分野ですが、短時間で高い処理能力が求められ非常に難解な分野です。
出題の傾向は2025年以降も継続されると考えられるため、各分野の土台を築いた上で「立体図形」のような出題傾向の高い分野に特化して学習を進めることが効果的です。とくに「推理・論証」の分野はなれも必要な分野なので、解法プロセスのストックが必要です。
難易度としては標準的な内容も含まれているものの、ていねいな処理・計算が求められているため、レベルの高い試験です。
2024年度入試の大問3では「正三角形の転がり移動」に関する問題が出題されました。馴染みのある受験生も多いと思われるこの単元ですが、計算の工夫が非常に重要であり処理速度の速さが大きな差となります。
②国語の出題傾向について
近年の入試は試験時間50分、大問2つで構成されています。
例外はあるものの論説文(随筆文)、物語文の2題で構成されている年が多く、文量は8,000字程度と速読が求められます。
特徴的な点は記述問題の比重がかなり高いことです。一方、「選択肢」「抜き出し」「空所補充」等の問題はかなり少なく東大、京大をはじめとした難関大学の入試問題を意識した内容となっていることが伺えます。
2024年度入試の大問1(4)では200字程度の「説明記述」の問題が出題されました。この問題では設問への解答に加えその解答に至るまでのプロセスをまとめる必要があります。この作業を短時間でしなければならない桜蔭の国語は、非常にレベルの高い試験です。
知識問題としては、ほぼ例年「漢字」が5問程度出題されるのみです。文章レベルが高いことから、語彙力が必要とされているため、知識の強化も必要不可欠でしょう。
③理科の出題傾向について
近年の入試では試験時間30分、大問4つで構成されています。
物理・化学・生物・地学の4分野すべてから出題され、リード文や実験観察事項をもとに答えるような問題を中心に構成されています。
中には時事問題と絡めたような問題も出題され、2024年度入試の大問2では「発光ダイオード」と生物分野を絡めた問題が出題されました。この大問では与えられた実験結果から自分の知識と結びつけて考察する能力が要求されており、幅広い知識を前提として考察する能力も問われています。
しかし、標準的な難易度が多いので、確実に点数を取れるようするための「基礎固め」を着実に実行しましょう。
④社会の出題傾向について
近年の入試では試験時間30分、大問2〜4つで構成されています。
地理・歴史・公民の3分野すべてから出題され、全解答数は50前後と多いことからスピードの要求される試験であることがわかります。
「地図」「統計資料」「歴史史料」「写真」等の読み取りを中心とした問題が多いですが、近年では新大学入試制度を意識した「思考力・判断力・表現力」を問う問題も少しずつ見られています。この傾向は2025年以降も続くことが予想されます。
2024年度入試の大問1(1)では「武蔵野台地において茶が畑を区切るように植えられている理由」について問われる問題がありました。この問題では武蔵野台地の特徴等をふまえ考察する能力が問われており、演習を繰り返して問題になれる必要があります。
しかし、理科と同じく標準的な問題も多いことから「基礎固め」が最優先事項となります。これらの対策を早期に終え、演習の機会を増やすことが受験突破の鍵となるでしょう。
3. 桜蔭中学校の入試対策について
桜蔭に限った話ではありませんが、6年生前期までに基礎固めを終え、6年生後期で演習の効率を高められるかが受験攻略の鍵となります。基礎固めを盤石化させると、演習を復習する際に基礎に立ち返ることができ「応用力の向上」と同時に「基礎の復習」もできます。
これは全ての教科に対して同じことが言えます。
配点比率が高く、記述を重視する桜蔭の算数・国語は、非常に点差の開きやすい科目です。早期の基礎固めに加え、日頃からの勉強習慣も非常に重要になります。以下の習慣は身についているでしょうか。
| 算数 |
考えたことを式や図に残す作業をする
|
| 国語 |
記述問題の解答までのプロセスを理解してまとめる
|
これらの勉強法は記述対策としてはかなり効果的です。
算数において考えたことを残しておく作業は「間違えた理由の特定」も容易となり、勉強の効率が上がります。
国語においてもまとめる作業は、短時間で文章を書く能力の向上に直結します。
一方、理科・社会に関しては考察能力が問われる問題もありますが、出題傾向を考えてもまずは知識の土台を整えておくことが最優先となります。よって日頃からの知識の強化をコツコツ積み上げ、6年前期までに8割程度終えておくことが必要です。
①5年生まで
5年生では多くの塾で新たな分野の授業が展開され、授業進度に遅れることが今後の学習の足を引っ張る恐れがあります。まずは苦手分野を作らないことが最も重要です。
新たに習った分野の学習は、その週のうちに消化する習慣作りが必要です。
そのためには、各塾で1ヶ月に1回程度実施されている確認テストに照準を合わせた勉強が効果的となります。確認テストは基礎力の定着度合いの確認ができ、生徒様も目標意識を持ちやすいことから非常に有用です。
桜蔭を志望される生徒様は各塾で発表されている偏差値を目標におき、そこから逆算して勉強計画を立てると良いでしょう。
| SAPIX |
62 |
| 四谷大塚 |
71 |
| 日能研 |
68 |
| 算数 |
桜蔭の入試では記述問題がメインとなるため、日頃から考えの過程を「式」「図」に示す習慣が大切です。簡単な問題であったとしても問題の解き方を実際に書いて表すことで記述力の向上だけでなく、間違えた理由を特定できるというメリットもあります。 また実際に解けたとしても説明できなければその問題を理解したことにはなりません。「説明できるか?」を1つの基準として勉強を進めましょう。 |
| 国語 |
算数と同じく記述問題の比重がかなり多いことから、記述を意識した学習が必要です。 大前提として5年生の段階で記述問題の勉強は「量」より「質」が重要となります。多くの問題に触れるのではなく、1つの問題に対して解答までのプロセス、論理展開を意識して深ぼることが大切です。 実際記述問題には「型」が存在し、このような型を理解しストックしていくことで記述力を高めるので授業の解き直しを徹底的にしましょう。論理展開や解答までのプロセスを理解してもう一度自分の力でまとめ直すと効果的です。 一方、知識の強化も習慣化するようにしましょう。市販の参考書等を用いてコツコツと積み上げることが大切です。 |
| 理科 社会 |
授業で新たな分野を次々と学習することになるため、毎週知識の確認を徹底的にしましょう。その際に理由や背景も含めた説明ができることが大切です。 また覚える知識量が非常に多く、欠落しやすい科目となりますので定期的な復習を勉強計画に組み込むことをオススメします。とくに社会では「地理」「歴史」「公民」の3分野を順に学習していくため既習の分野を忘れてしまうケースが非常に多いです。 時間に余裕のある長期休暇の時間を使って一気に復習してしまうことが効果的です。 |
②6年生前期(4月〜7月)
6年生前期では「5年生の既習範囲をさらに深ぼる」イメージです。そのため引き続き「基礎固め」の勉強がメインになると言えます。
本格的に入試対策を始めなければならないと考える保護者様も多いかと思いますが、6年生前期の段階ではまだ基礎固めに重点を置くべきです。各塾で実施される志望校別判定テストもできなかった分野に着目し、補強していくことが必要です。
各塾の授業内でも復習の機会が増えてくると思いますが、その機会を有効活用して苦手分野の克服を徹底的にしてください。この際5年生の内容を復習する勉強も効果的です。
| 算数 |
5年生に引き続き「基礎固め」に特化した勉強が最優先となります。加えて、6年生の時期から習ったことをアウトプットする意識ができると良いです。 算数では分野別の復習が徐々にメインとなってきますが、解き方の流れを意識して「式」や「図」で整理できるかを意識しましょう。 |
| 国語 |
国語では5年生でストックしてきた記述の「型」を活用していくことで、入試への実践力が磨けます。新たに見つけた解き方は自分のストックに増やしましょう。 |
| 理科 社会 |
これまでと変わらず各分野の基礎固めを理由・解き方も含めてしっかり復習しましょう。 5年生のときと同じく確認テストに照準を置いた勉強計画を練り6年前期が終わる時点で苦手がない状態を作ることが理想です。 一方社会では新たに「公民」を習うことになりますが、桜蔭では「時事問題」に関する問題も出題傾向に挙げられます。よって公民の勉強に加えて時事問題に触れる機会を設けることも必要です。 また桜蔭では他分野の知識と結びつけるような応用問題も出題されるため、「異なる分野でつなげる」学習が効果的となります。 |
③6年生8月
どの塾も6年生7月の段階で入試範囲の学習を一通り終えることになります。夏期講習では入試範囲の復習がメインですが、ここが最後の基礎固め期間となります。
授業を通して各分野の標準問題を解き直し、苦手箇所がないか確認しましょう。
④6年生後期(9月〜)
多くの塾で各志望校別の対策講座が開講されることになります。この時期で6年前期までに築いた土台を用いて応用力を磨きます。そのため塾での実践演習、過去問、志望校別判定テストなど演習の機会がかなり増えることになります。
塾での実践演習では常に全力を注ぎ、時間配分感覚・傾向を掴むことを意識して問題に取り掛かってください。この際間違えた問題があれば「どの技術・知識を使えば解けたのか」「どうして間違えたのか」を明らかにすることが必要です。基礎に立ち返ることで基礎力の確認もできます。
一方で分野別の演習をおろそかにしてはいけません。家庭学習では実践演習の復習と分野別の補強をして、分野別の応用力の底上げもしましょう。とくに算数では出題される分野がしぼられており、分野別に補強をすると、合格力を伸ばせます。
⑤過去問の取り組み方
過去問は学校の入試傾向、難易度、時間配分を掴むことを目的として取り組みます。よって基礎力が身についた9、10月ごろからスタートすると良いでしょう。
また、問題・解答用紙の大きさを揃えるなど本番とできるだけ同じ条件で解きましょう。同じ条件下で過去問演習をすると、自分の課題が見つけやすくなります。
たとえば、考えの過程をうまく「式」や「図」にまとめられないのであれば、簡潔にまとめる訓練が必要となります。
このように目的を持って過去問に取り組んでいただき、解き終えたら日々の学習と同様に解けなかった問題について「どの技術・知識を使えば解けたのか」「苦手分野はどこか」等を整理しましょう。第1志望校に関しては5〜10年分程度、第2、3志望校は3年分解くことを推奨しています。
⑥保護者様ができるサポート
生徒様は4教科を効率よく学習しますが、各教科における勉強目的、勉強計画の整理が難しいです。そのため、生徒様と一緒に目標を立て、目標から逆算したスケジューリングが重要です。
とくに国理社では知識の強化を日々継続的に続ける必要があり、その習慣を作ってあげるようなサポートも必要でしょう。「○月のテストで△点を取ろう!」「計画通り進んでる?」などの声かけを通して生徒様と保護者様が共に目標に向かって進めるような環境づくりが必要です。
また、試験結果が悪くても「できなかったところを責める」ことは避けましょう。まずはできたところに注目して褒めてあげることが大切です。その上で苦手科目、分野を一緒に分析し、苦手克服のための勉強計画を練り直すことが重要です。
4. 桜蔭中学校の併願校について
桜蔭を受験される生徒様の代表的な併願校は、以下の通りです。
| 〜1月31日 | 栄東・浦和明の星・市川・東邦大東邦・渋幕 |
| 2月 2日 | 豊島岡・吉祥女子・ 洗足・白百合・渋々 |
| 2月 3日 | 慶應中等部・豊島岡・筑附女子・お茶の水 |
| 2月 4日 | 豊島岡・市川・浦和明の星 |
1月中の受験は必須と考えてください。
それは①安全校の合格を勝ち取る、②受験の緊張感になれるといった目的があるためです。生徒様の緊張感をなるべくなくすためにも早めに合格を得ておくことが大切となります。
桜蔭の合格判定が高く、他校の対策にも十分時間が取れる場合は渋幕、渋々などの難関中を併願校にして良いと思いますが、合格判定が低い場合は桜蔭の対策に比重を置き安全校を確実に取る戦略が有効です。
また、2月4日以降は倍率がかなり上がってしまうため、2月3日までの期間で確実に合格を勝ち取れるスケジュールを組むことが重要です。
まとめ
桜蔭の入試傾向と対策法について解説しました。
桜蔭に合格するためには「早期から基礎固めを徹底する」ことに加え、日頃の勉強方法が重要となります。自分の考えを「式」や「文章」にまとめて、記述力の向上させてください。
また、入試突破は生徒様1人ではなく、保護者様のサポートも大切となります。
保護者様にはスケジュール管理など影で支えていただき、生徒様と二人三脚で受験に向かって頑張っていただければと思います。
正しい努力で中学受験を成功させるために、勉強計画や勉強方法の参考にしていただければ幸いです。
【参考文献】
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
桜蔭中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら