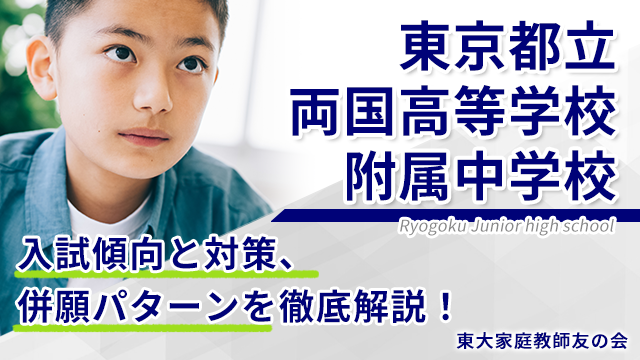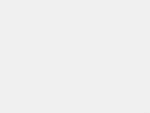1、東京都立両国高等学校附属中学校とは

両国高校附属中学校は、東京府立第三中学校として開校し、120年以上の歴史を持つ伝統校です。現役での国公立大学への進学率の高さは全都立高校の中でもトップクラスで、毎年、卒業生のおそよ3人に1人が現役で国公立大学へ進学しています。
ここでは、両国高校附属中学校の3つの特色をご紹介します。
①「自律自修」の校訓のもと育てる学力
「自律自修」とは、自らを厳しく律し、自ら進んで学ぶという意味で、自分で目標を設定し、その実現にむけて「授業を大切にする」ことを基本方針に、思考力や判断力を重視した指導を行うとともに、基礎基本の定着を重視しています。
すべての教科で対話的な学びを通した言語能力の育成を行っており、グループ活動やスピーチ、プレゼンテーション、ディベートやパネルディスカッションなどの活動も盛んです。
②独自のキャリア教育「志(こころざし)学」
総合的な学習の時間を利用して、将来、職業を通じて社会に貢献する志と使命感を身に着けるべく「志学」と呼ばれる独自のキャリア教育を実施しています。
発達段階に応じて、中学校では職場体験や卒業研究、高校では探究活動、各業界の第一線で活躍する社会人による講義などから、望ましい職業観を身に着け自らの「志」を実現する力を養います。
③世界を見据えた国際理解教育
英語の授業では日本人教員と英語話者の教員によるチームティーチングを行っているほか、放課後の添削指導、外部検定対策など、国際人として、お互いの文化や伝統を尊重しながら様々な分野で活躍できる人材の育成に力を入れています。
両国高校・附属中学校の国際教育の大きな魅力の一つは、中学3年生の夏に行われる、10日間の語学研修です。ホームステイや現地大学と連携したプログラム、現地中学生との交流などで、授業で身に着けた英語が通じるという経験が自信につながり、高校でのさらに高度な英語学習への原動力となります。
2、最新!2025年度向け東京都立両国高等学校附属中学校の入試傾向
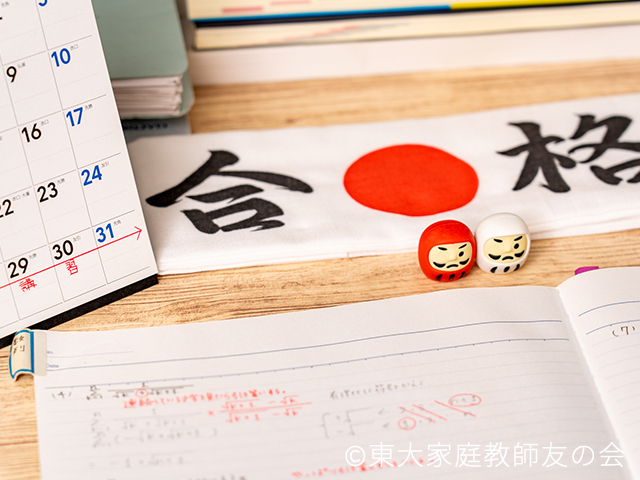
両国高校附属中学校の入試は、2月3日に行われます。ここでは入試の概要や、小学校での学校生活の様子について記載された報告書の点数の換算方法、2024年度入試の適性検査で特徴的だった問題や合否を分けた問題について解説します。
①入試の概要
両国高校附属中学校の募集人数は、男子80名女子80名の、合計160名です。入学者は、報告書と適性検査の結果によって決定します。
それぞれの配点は、報告書(200点満点)、適性検査Ⅰ(45分、100点満点を300点満点に換算)、適性検査Ⅱ(45分、100点満点を200点に換算)、適性検査Ⅲ(45分、100点満点を300点満点に換算)の1000点満点です。2024年度入試の倍率は男子が4.4倍、女子が3.9倍でした。倍率は近年、徐々に落ち着きつつあると言えます。
適性検査ⅠとⅡは都立中高一貫校の共同作成問題ですが、適性検査Ⅲは算数分野を中心とした独自作成問題です。都立中高一貫校の適性検査で試される「思考力・表現力・分析力」の土台として、国算数理4教科の学力が十分に身についていることが大前提となります。
②報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の学習の記録を点数化したものです。
各評価の評定を、
国語・算数・理科・社会は
評定3=55点
評定2=35点
評定1=4点
音楽・図画工作・家庭・体育は
評定3=45点
評定2=25点
評定1=4点
とし、その合計800点満点を、四分の一にして200点満点に換算します。
③適性検査Ⅰ
適性検査Ⅰは例年同様、読解問題と作文の形式でした。
文章1の出典は東直子『生きていくための呪文』で、春の短歌について、短歌から生まれる心情について筆者が述べた文章、文章2は藤田真一『俳句のきた道芭蕉・蕪村・一茶』からで、江戸時代の俳諧について松尾芭蕉が述べた言葉を説明したものでした。
|
ここでは、適性検査Ⅰの山場とも言える〔問題3〕の作文について解説します。文章1、2で読み取った内容に触れながら、これから学校生活で仲間と過ごしていく上で言葉をどのように使っていきたいか、自分の考えを400~440字で書きます。
まずは文章1、2のどちらの考え方を踏まえて書くのかを決める必要があります。
段落についての条件指定はありませんでしたが、文字数から考えても、 段落1:選んだ文章の筆者の主張と、そこからどのように言葉を使っていきたいかという自分の考えを述べる という、三段落構成の総括型が最も書きやすいでしょう。
問題に「これから学校生活で仲間と過ごしていく中で」とあるので、今後の中学校生活の中で仲間との関わる場面を具体的に想定して書くことができるかが重要です。また原稿用紙を正しく使えているか、適切な言葉遣いができているかにも気を付ける必要があります。
|
適性検査Ⅰの作文では毎年、自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。日頃から様々な事柄に対して、自分の考えを持ち、それを文章として書く練習をしましょう。良い作文を書くためには、豊富な語彙力とそれを正しく運用していく力が必要なので、使いこなせる言葉の量を増やしていけるように、日頃から読書に親しんだりする姿勢は大切にしましょう。
④適性検査Ⅱ
2024年度の適性検査Ⅱは、大問1がデジタル数字を題材にした算数の規則性に関する問題、大問2が公共交通機関の利用についての問題、大問3が理科分野からの出題で、摩擦についての実験や観察の問題でした。
|
ここでは、大問2の〔問題2〕について取り上げます。この問題は、ある町で「ふれあいタクシー」の取り組みが必要になった理由と、「ふれあいタクシー」導入の効果について、会話文と4つの図表から考えられることを説明する問題です。
「ふれあいタクシーの必要性」については、資料から路線バスの平日一日あたりの運行本数が減ったことに加えて、人口の減少、75歳以上の高齢者が人口に占める割合の増加が読み取れます。このことから、人口が減少し、路線バスの本数が減少したE町が、移動することに困っている人を対象にした交通手段を用意するため、などとまとめるとよいでしょう。
「ふれあいタクシーの効果」については、1か月に20回まで利用可能で、かつ一定額以上は町が利用料金を負担してくれるため、利用者の負担がそれほど大きくないことが読み取れると説明しやすくなるでしょう。実際に、E町の75歳以上の人の90%以上が利用していることから、75歳以上の多くが利用し、買い物や病院へ行けるようになったことをまとめます。
|
解答しなければならない内容を取りこぼすことがないように、まずは丁寧に問題文を読み込み、出題者が何を求めているのかを把握したうえで、論理的に考察し、的確に表現する力が必要になります。
会話文や資料自体はそれほど複雑ではありませんが、数値の読み取りの要素が強くなっている傾向があるので気を付けて取り組んでいきたいですね。
⑤適性検査Ⅲ
適性検査Ⅲは、両国高校附属中学校の独自作成問題です。算数が中心の出題で、一部で「ドロ沼問題」とも言われるほど、思考錯誤と手間がかかる問題が多い点が特徴です。
大問1は時間と規則に関する問題でした。〔問題1〕はシンプルな計算問題、〔問題2〕も標準的なレベルの消去算を使った問題なので、必ず正解しておきたい問題です。〔問題3〕は、レジのお金が条件に沿って変動した場合に、お金の枚数がどうなるかという問題で、戸惑った受検生も多かったことでしょう。ここでは、〔問題3〕はあと回しでもよい問題、と判断してよいでしょう。
|
大問2は場合の数と平面図形の問題で、両国高校附属中学校「らしい」問題だったと言えます。したがってここでは、大問2の〔問題2〕を取り上げて説明します。この問題は、ルールに従ってゲームを行う問題です。4色の折り紙を5枚ずつ計20枚用意し、4枚ずつ折り紙を取り出し、同じ色の枚数を得点とします。会話文を参考に、折り紙がどのように取り出されたのかを考え、答えます。
会話文から、みさきさんが2セット目を行うときに袋に入っている折り紙は8枚です。みさきさんが必ず3点以上になるためには、残りの紙の色は2色だけのはずです。
よって、
|
一見条件が複雑そうに見えますが、丁寧に状況を整理することができれば、正解にたどり着くことはそこまで難しくはありません。〔問題3〕は図形の要素も加わりより難易度の高い問題だったため、正解できた受検生は少ないでしょう。よって〔問題2〕までしっかりできたかどうかが合格を左右したと言えます。
適性検査Ⅲは、手間と時間のかかる問題が多いため、どの問題を優先して解くかを瞬時に判断できるかどうかも攻略するうえで重要です。また、手を付けたら答えが出るまで解ききる粘り強さと正確性が試されていると言えます。過去問なども活用し類題に多く取り組み、問題を見極める力を養いましょう。
⑥要チェック!出題形式の似ている学校は?
出題形式の似ている学校としては、適性検査・思考力型の入試問題を行っている学校が挙げられます。
他の都道府県の国公立中高一貫校の適性検査の問題を集めた問題集や、全て独自作成問題で試験を行っている千代田区立九段中等教育学校の問題などは、両国高校附属中学校の受検対策にも役立つでしょう。
3、東京都立両国高等学校附属中学校を受検する際のオススメの併願校!

都立中高一貫は、2月3日に一斉に一般入試を行うため、基本的には私立中学を併願することになります。
ライターがこれまでに出会ってきた両国高等学校附属中学校を志望している生徒様の多くは、立地と偏差値帯から、安田学園中学校と開智日本橋中学校を併願していました。特に安田学園中学校は、適性検査型の入試を複数回行っていることもあり、何度も出願していた生徒様が少なくありません。
ここでは、過去に受検した生徒様の動向や出題傾向などをもとに、オススメの併願校をご紹介します。なお、この併願校情報は2024年度の入試をもとに作成していますので、2025年度の入試情報に関しては各校の募集要項を必ずご確認ください。
①1月入試
|
・栄東中学校 ・市川中学校 ・浦和実業学園中学校 ・昭和学院中学校
|
埼玉県・千葉県の入試が行われ、首都圏の入試の前哨戦にも位置付けられている1月入試は、一月入試の定番校、栄東中学校や市川中学校の他にも、適性検査型の入試を行っている浦和実業学園中学校や昭和学院中学校がおすすめです。
②2月1日
|
・開智日本橋学園中学校 ・かえつ有明中学校 ・江戸川女子中学校 ・宝仙学園理数インター中学校 ・安田学園中学校 ・立教女学院中学校
|
特に併願者が多いのが、先ほども挙げた安田学園中学校と開智日本橋学園中学校。かえつ有明中学校や宝仙学園中学校は、他の都立中高一貫校を受験している生徒様にも併願先として多く選ばれています。
③2月2日
|
・桜丘中学校 ・宝仙学園理数インター中学校 ・淑徳巣鴨中学高等学校
|
1月入試も含めて、2月2日までに1校でも合格を掴んでおくと、より自信を持って本番に臨めるはずです。その点も意識して併願校を選べるとよいでしょう。
④2月4日以降
|
・東京都市大学等々力中学校 ・広尾学園小石川中学校
|
4日以降は、本番の手ごたえをもとに出願するか/しないかやどの学校に出願するかを決定してもよいでしょう。広尾学園小石川中学校は、他の日程でも受験していた生徒様が複数見られました。
4、東京都立両国高等学校附属中学校の受験対策方法

ここでは、両国高校附属中学校を受検するにあたり、
「いつ何をしたらいいの?」
「過去問の取り組み方は?」
「家庭でのサポートの方法は?」
といった、保護者様が気になる受検対策方法をお伝えします。
①時期別・教科別対策ポイント!
ここでは、小学校4年生から受験直前まで、時期別・教科別の受検対策方法をご紹介します。
(1)小学4年生
学習内容もレベルアップする4年生は、学力差が付きはじめる時期でもあります。この時期はまず、学習習慣を定着させることが重要です。学校や塾の宿題などのやるべきことに取り組む時間を確保し、苦手を作らないようにすることと、自分から学習に向かう「向学心」を育めるように心がけましょう。
|
算数:基礎的な計算力を身に着けるとともに、私立中入試でも都立中入試でもよく出題される、周期算や植木算などの学習に取り組みましょう。 国語:ある程度長さのある文章で、内容を正しく読み取れるようになることを意識しましょう。また、習った漢字を使って正しい文法で文がある程度の長さの文章を書くことができるようにしましょう。 理科・社会:身近な事象に幅広く興味を持てるよう観察・実験を行うなど、体験・経験を重視して楽しく教養を身に着けられるようにしましょう。
|
(2)小学5年生
中学受験の土台固めの時期でもある5年生。都立の中高一貫校受験に必要な「報告書」の対象になるのは、5年生からです。国語・算数・理科・社会の4科目に限らず、音楽や図工、家庭や体育、外国語なども含めてすべての科目において、学校の学習活動に十分に取り組み、評定をとっておくことが大切です。
|
算数:基礎計算の正確さとスピードを鍛えるとともに、論理的に考える力や条件を整理する問題の解き方などを身に着けましょう。 国語:知っている言葉を増やすだけではなく、使いこなせる言葉を増やせるよう、語彙の習得に努めましょう。学習に関わらず、幅広い分野の本を読むようにし、分からない語句や言葉は調べたりすることを習慣にしましょう。 理科・社会:学校や塾で習ったことを丁寧に復習し、知識を問う問題は確実に答えられるようにしましょう。また、身の回りの様々な出来事の規則性などに目を向けられるようになるとよいですね。
|
(3)小学6年生(4~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
|
算数:文章題を中心に、どのような方法をとれば正解にたどり着くことができるのか、過程も書くように意識しましょう。また、適性検査Ⅲを意識し、素早く正確な計算をより心がけていきましょう。 国語:読解問題に力を入れましょう。特に筆者の主張や表現の意味することがらを記述させるような問題は頻出ですので、答え合わせの際には、正解していたとしても必ず根拠を確認しましょう。 理科:実験や観察の結果を分析したり、考察したりする問題の対策を進めましょう。示されたデータが何を表しているのかを意識するとよいです。 社会:時事的な問題に対応できるよう、新聞やニュース番組を見るように心がけましょう。また、それに対して自分がどう思うかを誰かと話したり、文章として書いてみることも作文や記述問題の力につながります。
|
この段階で算数に対して苦手意識を持っている生徒様は、適性検査Ⅲ対策や入学後のことも考え、苦手を克服していけるようにしましょう。
(4)小学6年生(7~8月)
「夏は受験の天王山」とも言われる季節。特に夏休み中は、体調管理と生活リズムを整えて過ごしたいですね。
|
算数:初見の問題への対応力を身に着けたい時期です。特に頻出の条件の整理、場合の数などの問題では、根気強く問題に取り組む力が求められます。時間が十分にある夏だからこそ、最後まで向き合う姿勢で臨みましょう。 国語:作文の対策に力を入れましょう。評論文では、読んだ文章のキーワードになる言葉を短くまとめる練習をしたり、筆者の主張を要約したりする練習をすると効果的です。 理科・社会:複数の資料を総合的に活用する問題の対策を行いましょう。どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析し、記述式の問題でしっかり得点できるようにすることが大切です。
|
適性検査対策として、教科横断的な問題に取り組み、適性検査の形式に慣れることも必要です。
(5)小学6年生(9~11月)
冬が近づいてきたら、いよいよ過去問にも挑戦しましょう。過去問の解き方については、このあと詳しくお伝えします。
(6)小学6年生(12月~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、出題形式の似ている他校の過去問なども活用しながら、様々な問題に取り組んで仕上げをしていきましょう。間違った問題は復習も忘れずに行ってください。
②【いつやる?何周?】過去問対策方法は?
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的の1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。過去問で間違ったところは、その時点で復習が必要なポイントということです。残りの時間で復習し、もう一度解くことで、同じような問題に出会ったら確実に解けるようにしておくのです。
2つ目の目的は、時間の感覚を掴むためです。入試本番では、決められた時間で問題を解き終える必要があります。特に両国高等学校附属中学校の適性検査Ⅲは、入試の最後の時間で集中力も限界を迎えつつあるにも関わらず、忍耐強さが問われる手間がかかるような問題が出題されるため、まさに時間との戦いと言えるでしょう。過去問に取り組む際には時間の感覚を身に着けるために、入試本番と同じスケジュールで解くことをおすすめします。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、かつ間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある、6年生の秋ごろから取り組んでみることをお勧めします。過去問に挑戦して解けなかった問題は、直前期に向けてしっかり復習しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第一志望でしたら5年分程度、併願校として受験する場合でも、2・3年分は必ず解いてみましょう。両国高校附属中学校の独自作成問題である適性検査Ⅲは、独自作成が始まった平成28年度以降の問題をできるだけすべて解いてみましょう。
過去問は何度も繰り返し解く必要はなく、一周すれば十分です。もう既にできていることに時間を割くよりも、できないことを一つでも多くできるようにしたほうが、合格に近付けるからです。ですから、間違えた問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度もチャレンジしてください。
③保護者様がご家庭でできるサポートとは?
(1)自分の考えや経験を述べる練習をする
例年、適性検査Ⅰでは、自分の意見や経験を書く作文が出題されます。
「今日はどんな一日だった?」「それについてどう思った?」など、日々の家庭内の会話の中で、思考や経験の言語化を促しましょう。また、気持ちを言葉にすることがストレスの溜まりやすい受験生生活の中でよい感情の発散にもはずです。
(2)興味や関心の幅を広げ、様々な経験をする
適性検査の問題には、観察や実験、身近な出来事を取りあげた問題がよく出題されます。植物や野菜を育てたり、一緒に料理をしたり、多くの経験をさせて引き出しを増やすことも、保護者様だからこそできるサポートの一つでしょう。科学館や博物館を訪れたり百科事典などを読むのも効果的です。
(3)メンタルケア・体調管理のサポート
普段の学校に受験勉強と、想像以上に精神的にも身体的にも負荷のかかる受験生生活。その一方で、心身ともに大きく成長する大切な時期でもあります。
だからこそ、メンタル面のケアと体調管理は保護者様にもっとも力を入れていただきたいサポートです。受験本番はもちろんですが、日々安定した状態で生徒様が毎日を過ごせるように、食事や睡眠時間について親子で決まり事を作ったり、生徒様が安心して過ごせるような空間づくりを行っていってください。
5、最後に
両国高校附属中学校は、東京府立第三中学校として開校して以来120年以上の歴史を持つ伝統校です。現役での国公立大学への進学率の高さは全都立高校の中でもトップクラスであることから、「都立中御三家」の一つとされています。
生徒募集は一般枠募集のみで、報告書(200点満点)と適性検査Ⅰ(45分、100点満点を300点満点に換算)、適性検査Ⅱ(45分、100点満点を200点に換算)、適性検査Ⅲ(45分、100点満点を300点満点に換算)の1000点満点です。
適性検査ⅠとⅡは、都立中高一貫校の共同作成問題を使用していますが、適性検査Ⅲについては算数分野を中心とした独自作成問題で、手間と時間のかかる問題が多いため、粘り強さと計算の速さや正確さが試されていると言えるでしょう。過去問なども活用し、類題に多く取り組み、問題を見極める力を養いましょう。
併願校としては安田学園中学校と開智日本橋に出願するパターンが非常に多く見られます。特に安田学園中学校は、立地や偏差値帯はもちろん、適性検査型の入試を複数回行っており、受験スケジュールに組み込みやすいことも理由の一つでしょう。
受検に向け保護者様ができるサポートとしては、日常の出来事での経験や時事的な事柄への意見などを言語化する練習をすることや、生徒様の興味関心を広げるような取り組みが挙げられます。何より、精神面でのサポートが十分にできるよう、生徒様の様子を日頃から気にかけるようにしましょう。
【参考文献】
・東京学参「都立両国高等学校附属中学校2025年度【過去問8+5年分】(中学別入試過去問題シリーズ)」
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら