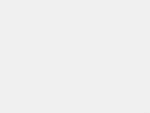1. 東京都立立川国際中等教育学校とは?

立川国際中等教育学校は、「国際社会に貢献できるリーダーとなるために必要な学業を修め、人格を陶冶する」ことを教育目標に据えており、日常の学校生活から国際感覚や多様性を尊重する姿勢を身に着けられるような取り組みをしています。
ここでは、学校の特色として、学校生活と語学教育、教養主義と進路選択についてご紹介します。
①多様性を肌で感じる日常生活
生徒の約2割が海外帰国・在京外国人生徒です。異なるバックグラウンドを持つ生徒たちが協働することで、多様性を肌で感じられます。海外研修の機会も多く、オーストラリア(全員参加、5年生)のほか、シンガポールやカンボジア、ニュージーランドなどでの研修に参加できます。
留学する生徒も多いことに加え、海外の留学生の受け入れも積極的に行っています。
②語学を強みにする教育
英語をツールとして使いこなせるよう、英語教育に力を入れています。約8,000冊の洋書の蔵書に加え、全学年毎週1~3時間、外国人の先生との授業があり、英作文の添削やエッセイライティングの指導を受けることもできます。
英語に関連した行事も多く、英語発表会(前期課程)、イングリッシュサマーセミナー(前期課程希望者)、英語合宿(2年)など、楽しみながら英語力を磨きます。さらに4年生では自由選択科目として、第二外国語も選択でき、フランス語、ドイツ語、中国語を学べます。
③文系だけじゃない!「教養主義」で多様な進路選択
「英語に強い=文系」のイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
立川国際中等教育学校では、5年生まで文系・理系を分けることなく、幅広く様々な科目を履修することで、英語を強みにしつつ、一人ひとりの興味関心や可能性を広げます。その結果医学部をはじめとする、いわゆる理系分野への進学者が約半数にのぼります。
キャリアの観点では、中高一貫教育を活かした先取り学習や習熟度別授業、チューター在中の自習室が平日は19時、土曜や長期休業中も18時まで利用できるなど、きめ細かく面倒見の良い指導が特徴で、行ける大学ではなく、行きたい大学を目指せる環境が整っています。
2. 最新2025年度向け!東京都立立川中等教育学校の入学検査について

立川国際中等教育学校の入学検査は、海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集の2つの募集枠があります。ここでは、各入試枠の概要や試験内容、2024年度の適性検査から、特徴的な問題や合否を分けた問題について説明します。
①海外帰国・在京外国人生徒枠募集
海外帰国・在京外国人生徒枠募集の受験に際しては、応募資格を満たしているかの確認を兼ねた事前相談が必要です。
1月25日に実施される作文(600点)と面接(パーソナルプレゼンテーションを含む、400点)の総合1,000点満点で合格者を決定します。募集人数は30名です。2024年度は男女合わせて56名が応募し、倍率は1.87倍でした。
(1)作文
作文の試験は45分間で、与えられたテーマに基づき、自分の考えを表現する力をはかります。英語か日本語のどちらかを選択できますが、課題は同じなので、自分がしっかりと考えを述べられるほうの言語を選びましょう。
2024年度のテーマは、自分のこれまでの経験を活かし、周りや地域にある社会問題を解決するためにチームを作るとして、「より良い社会をつくる」ためにチームでどのような活動をするかを400字~600字で書くという問題でした。
第1段落では、チームがどのような問題を解決するのか、第2段落では、チームがどのような人々に、どのような活動をするかを具体的に述べ、第3段落では、その問題の解決が地域や社会にどのような影響を与えたかを説明するという条件が提示されています。
構成は条件に従えばよく、比較的取り組みやすい問題だと言えます。チーム、つまり集団で課題に取り組むという設定なので、チームの中で自分がどのような役割を果たすのかや、チームだからこそ取り組める活動を挙げられているかが採点のポイントになります。
自分の住んでいる地域やゆかりのある場所の特徴や課題について、日頃から目を向けておきたいですね。
(2)面接
面接は、志望の動機、意欲等を総合的に判断します。2024年度は、受験生1名に対して面接官3名で実施されました。立川国際中等教育学校では、一般的に帰国生入試でよく問われる志望理由や今後の学校生活で力を入れていきたいことなどの質問に加えて、パーソナルプレゼンテーションがある点が特徴です。
パーソナルプレゼンテーションは例年、外国の文化について知っていることや自分が海外で体験したこと・学んだことなどをA3の大きさの紙1枚に発表資料としてまとめ、それを用いて5分以内で発表するというものです。
- ・日本と滞在していた国には、どのような違いがあるか
・その違いからどのようなことを経験したり学んだのか
・海外での経験を、今後にどのように活かしていきたいか - を自分の言葉で説明できるようにしましょう。
プレゼンテーションに関しては事前の準備ができるものですので、時間を測りながら、何度も練習を重ねましょう。
②一般枠募集
一般枠募集は、小学校5・6年生の成績に基づく報告書(360点満点を250点満点に換算)と、2月3日に実施される適性検査の結果(750点満点)の1000点満点で入学者を決定します。
適性検査はいずれも45分間で、Ⅰが独自作成問題で100点満点を250点満点に換算し、Ⅱが都立中高一貫校の共通作成問題を使用して、100点満点を500点満点に換算します。
募集人数は130名で、2023年度は3.65倍、2024年度は3.95倍と、倍率は4倍程度で推移しています。
(1)報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の「各教科の学習の記録」を点数化したものです。
各教科の評定を、
評定3=20点
評定2=10点
評定1=5点
とし、それらの合計(360点満点)を250点満点に換算します。総合得点に占める報告書の割合は25%です。国算理社以外の科目の学習にも取りこぼしなく取り組み、評定をとっておきたいですね。
(2)適性検査Ⅰ
適性検査Ⅰは、立川国際中等教育学校の独自作成問題です。文章の内容を的確に読み取ったり、自分の考えを論理的かつ適切に表現したりする力を試します。出典は戸谷洋志の「SNSの哲学リアルとオンラインのあいだ」で、読解問題が2問、作文の問題が1問という形式でした。
ここでは〔問題3〕の作文の問題について説明します。400字以上460字以内で、第一段落では、筆者が人間はどのような存在であると述べているかを説明し、第二段落で、筆者のような考え方は学校生活にどのように生かせるか、具体的な場面を一つ取り上げながら説明する、というものでした。
筆者はベルクソンの考えを引用しながら、生命である人間は、科学的な世界観では捉えきれないものであり、予見不可能な創造的進化を遂げる存在だと述べています。この考え方を学校生活の中で捉え直すと、生活の中で起きるできごとは1回1回違うものであり、それらによって自分自身に思わぬ変化が訪れる可能性がある、ということでしょう。
第1段落では、筆者の考え方を的確に読み取り、簡潔にまとめる力が求められました。日頃から文章の要旨を捉える練習をしておきたいですね。第2段落では、学校生活の中での具体的な場面を思いつけるかが鍵になります。事前に学校の教育活動などについてある程度知っている受験生には取り組みやすかったのではないでしょうか。
立川国際中等教育学校の適性検査Ⅰの文章の話題は多岐にわたります。文章のジャンルによって読解の精度に差が生じないように練習を重ねましょう。
(3)適性検査Ⅱ
適性検査Ⅱは都立中高一貫校の共同作成問題です。資料から情報を読み取ったり、課題に対して論理的に思考・考察する力を試します。
2024年度は、大問1がマグネットシートを使って得点板の数字を作成することをテーマにした算数の規則性に関する問題、大問2が公共交通機関の利用を題材にした資料の読み取りと分析についての問題、大問3が摩擦について調べる実験から、物体の性質を考える問題でした。
ここでは、総合得点に占める割合が20%(1,000点満点中の200点分)と非常に高く設定されている、大問1について説明します。
〔問題1〕は、太郎さんと花子さんの2人で「かく」作業と「切る」作業を分担して、マグネットシートから棒状のマグネットを作る作業を、できるだけはやく終わらせるための順番を考えます。太郎さんは「かく」のに10分、「切る」のに5分かかるのに対して、花子さんは「かく」「切る」どちらも7分かかります。
従って、太郎さんができるだけ多く「切る」作業を、花子さんができるだけ多く「かく」作業をすれば、最も短い時間で作業を終えられるはずですね。ただし「かく」作業の前に「切る」作業はできないので、太郎さんも花子さんも一番初めの作業は「かく」作業をすることになります。
よって、太郎さんは最初に「かく」作業をした後、「切る」作業を6回繰り返し、花子さんは「かく」作業を5回繰り返すと、40分ですべての作業を終わります。
〔問題2〕はルールに従って、得点板の数字を「456」から「987」に張り替えるときの最短の時間を求める問題です。
得点板を張り替える作業は、
・マグネットをつける作業
・マグネットを取る作業
・数字の書かれたボードを180度回転する操作
・2枚のボードを入れかえる操作
の4つの作業の組み合わせです。
最短の時間を求めるためには、元の数字にどう手を加えれば求める数字を効率よく作れるのか(たとえば「9」を作るには「6」を180度回転させるのが最短)を考えられるかが重要でした。
〔問題1〕〔問題2〕のどちらも、やみくもに手をつけるのではなく、どのように作業を組み合わせるのがよいのか、ある程度の目星をつけてから解き進められるとよいでしょう。
(4)出題形式の似ている学校は?
出題形式の似ている学校としては、国公立中学校をはじめとする適性検査・思考力型の入試問題を実施している学校が挙げられます。
都立中高一貫校で独自作成問題を使用している学校や、私立中学校で都立中高一貫校に準拠した入試を実施している学校もあります。そうした学校の入試問題も、問題演習に役立つことでしょう。
3. 東京都立立川国際中等教育学校志望の生徒様におすすめ併願校紹介!
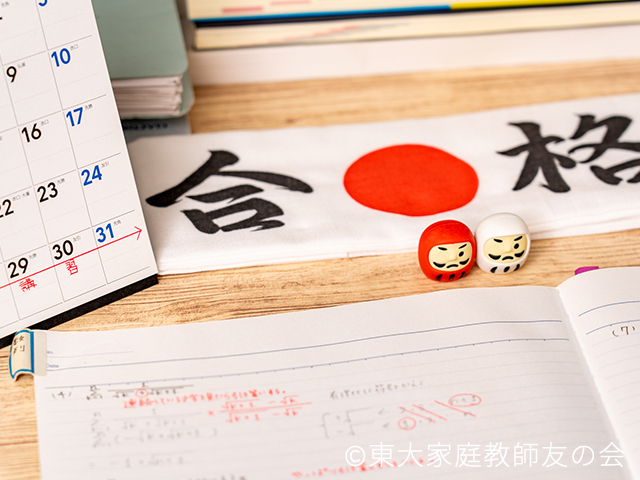
ここでは、ライターが過去に出会った生徒様の併願校を参考に、立川国際中等教育学校の一般枠募集の受験を検討するみなさんにおすすめの併願校をご紹介します。
立川国際中等教育学校を受験する生徒様の併願校は、他の都立中高一貫校を受験する生徒様と比較しても多岐にわたりますが、大学の附属学校や系列学校などを中心に併願校を決めるご家庭や、帰国生の割合が多かったり、国際教育に力を入れている学校を中心に併願校を決めるご家庭が多い印象を受けます。
帰国生・在京外国人生徒枠募集の受験を検討されているご家庭は、併願校も帰国生入試を受験する計画を立てていることでしょう。帰国生入試は一般入試とは募集時期や試験時期が異なるため、各学校の生徒募集要項をご確認ください。
①偏差値帯や進学先を重視するパターン
立川国際中等教育学校と偏差値帯が近かったり、学習や進学実績をもとに併願校を決めるパターンです。
(1)1月
・西武学園文理中学校
・浦和実業学園中学校
・立教新座中学校
(2)2月1日
・中央大学附属中学校
・国学院久我山中学校
・日本大学第二中学校
(3)2月2日
・明治学院大学中学校
・東京電機大学附属中学校
(4)2月4日以降
・成蹊中学校
・明治大学八王子中学校
・郁文館中学校
・東京電機大学附属中学校
②国際・英語教育に強い学校を重視するパターン
こちらは、帰国生の割合が比較的高い学校や、国際教育に力を入れている学校を中心に併願するパターンです。適性検査・思考力型の入試を実施していたり、英検などの試験の結果をもとに優遇措置を設けている学校もあります。
帰国生・在京外国人生徒枠募集の受験を検討されているご家庭にも、参考にしていただけるのではないでしょうか。
(1)1月
・西武台新座中学校
・浦和実業学園中学校
(2)2月1日
・頌栄女子学院中学校
・宝仙学園理数インター中学校
・桜美林中学校
・広尾学園小石川中学校
・三田国際学園中学校
・桐光学園中学校
(3)2月2日
・宝仙学園理数インター中学校
・ドルトン東京学園中等部
・大妻中野中学校
(4)2月4日以降
・桐蔭学園中等教育学校
・頌栄女子学院中学校
4. 必見!東京都立立川国際中等教育学校の受験対策

国際色豊かで、語学力を強みに世界で活躍できる人材の育成に力を入れている、立川国際中等教育学校。
ここでは、一般枠募集での合格を目指す生徒様が、どのような時期に、何を意識して学習していけばよいのかや、過去問にはいつ何周取り組むのかよいか、家庭で保護者様ができるサポートにはどのようなものがあるかなど、保護者様が気になる受験対策についてお伝えします。
①いつ・何をすべき?受験対策方法紹介!
ここでは、小学校4年生から受験直前期まで、時期別・教科別にどのような点に注目して、何をしていけばよいのかをご紹介します。
(1)小学4年生
4年生は学習内容が少しレベルアップし、クラスの中でも学力差が付き始める時期です。この時期は国算理社4教科の学習にしっかり取り組み、都立中高一貫校を目指すために必要な思考力・分析力・表現力の土台作りをしましょう。
| 算数 |
基礎的な計算力の向上に努めましょう。 桁数の多い計算や小数・分数を含む計算なども素早く丁寧にできるよう練習しましょう。 |
| 国語 |
興味・関心を広げるためにも様々なジャンルの本を読ませましょう。 読んだ後は、内容を簡潔にまとめたり、あらすじを話せるようにしておくと、読解問題の練習にもなります。 |
| 理科 社会 |
学習の基礎・基本となる知識を固めましょう。 そのうえで、身の回りの身近なできごとや現象に目を向けて興味関心を広げたり、気になったことを自分から調べてみたりする力を見に着けさせましょう。 |
(2)小学5年生
都立中高一貫校の受験の際に提出する報告書の対象は5年生からです。報告書は総合得点の25%を占めるため、日々の学校での学習活動にも十分に取り組む必要があります。
| 適性検査Ⅰ |
他の都立中高一貫校の独自作成問題や共同作成問題が2つの文章を読ませる一方で、立川国際中等教育学校では、比較的分量(4,000字程度)のある文章を一つ出題する流れが続いています。 つまり、長めの文章を集中力を切らさずに読み切る力が必要です。 適性検査Ⅱの情報を整理する力を見に着けるためにも、「読解」を意識してていねいに文章を読む力を伸ばしましょう。 |
| 適性検査Ⅱ |
文章から条件を読み取って整理したり、論理的に考える力を身に着けましょう。 とくに算数分野に関しては、5年生終了までの段階で、既習範囲の基礎学力は完成していることが望ましいです。 また、物事を様々な視点から捉えられるような練習をしましょう。 それが、適性検査を解く際に必要な発想力にもつながります。 |
(3)小学6年生(4月〜6月)
| 適性検査Ⅰ |
記述問題で得点を取ることに焦点を当てて練習を積み重ねましょう。 そのためには、答えの根拠を明らかにすることが必要です。 問題演習のあとには解答・解説をよく確認し、答えとなる理由を説明できるようにしましょう。 |
| 適性検査Ⅱ |
適性検査Ⅱで点数をとるためには、問題が何を求めているのか、条件は何なのかを文章から理解するという、読解力が必要です。 適性検査で頻出の会話文の中から条件を読み取って整理していく問題を中心に演習を重ねましょう。 さらに、時事的な内容の出題も意識し、広く社会の動きに問題に目を向けられるよう、新聞やニュース、現代社会の問題を扱った小・中学生向けの新書などを読むとよいでしょう。 世界で活躍できる人材の育成を目指す立川国際中等教育学校においては、入学後も社会課題に目を向ける視点はきっと役に立つはずです。 |
(4)小学6年生(7月〜8月)
とくに夏休み中は生活リズムを整え、目標を持って計画的に学習を進めましょう。
| 適性検査Ⅰ |
作文の問題に対応できるように、夏休みを通じて作文の書き方の基本を身に着けましょう。 |
| 適性検査Ⅱ |
一見複雑そうに見える適性検査の問題も、基本的な問題の組み合わせであることがほとんどです。 中学入試の定石と呼ばれるような問題は、夏休みで一通り解き終えましょう。 とくに複数の資料を総合的に活用する問題や実験を伴う問題は頻出です。 資料や実験から何が分かるのか、情報を適切に分析し、どのように考えたのかその手順も記録しましょう。 |
(5)小学6年生(9月~11月)
いよいよ過去問に挑戦する準備が整ってくる6年生の秋。過去問の活用方法については、このあと詳しくお伝えします。
問題演習の機会が増える時期ですが、演習後は丸付けをするだけではなく、解説からその問題の注目すべきポイントや別解などにも目を通して、自分の苦手や弱点などの気付いたことをメモしながら学習を進めましょう。
(6)小学6年生(12月~1月)
受験直前期のこの時期は、過去問の復習に加え、出題形式の似ている学校の過去問も活用しましょう。新しいことを身に着けるよりは、これまでやってきたことの仕上げをするようなイメージでいられるとよいですね。問題を解くときは時間配分も考えながら取り組みましょう。
②何年・何回解けばいい?過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的は2つあります。1つ目は問題の出題形式を知り、傾向を掴むためです。もう1つは時間の感覚を掴むためです。とくに立川国際中等教育学校の適性検査Ⅰは文章量が長く、短い時間の中でどれだけ正確に読解し、減点なく回答できるかが合格への鍵を握ります。
また適性検査Ⅱは作業量が多いため、45分の中でどの問題を優先し、どの問題を後回しにするのかを判断する力も必要ですし、最後まで集中力を切らさないようにする訓練も大切です。
ですので、
- ・過去問で解けなかった問題は今の時点での弱点!復習するポイントの発見に使用して、間違えた問題はよく復習する
・時間を測って本番のスケジュール通りに解く
この2つを意識すると、過去問を最大限に活せます。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある6年生の秋(9月から11月)ごろから取り組むことをお勧めします。
それ以降の期間は、間違えた問題にもう1回挑戦したり、他校の過去問から似たようなタイプの問題を解いて実践力を鍛えましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第1志望でしたら7年分程度解くことをお勧めします。併願校として受験する場合も、2・3年分は必ず解いてみましょう。過去問演習の際は、一度できた問題を何度も繰り返し解く必要ありません。
できる問題を何度も繰り返し解くよりも、今できていないものを1つでも多くできるようにするほうが効率よく合格に近付けると考えるからです。できなかった問題の復習には徹底的に時間をかけ、できるまで挑戦しましょう。
③ご家庭で実践!保護者様にできるサポートとは?
(1)広く様々なことに興味・関心を広げさせる
「教養主義」を掲げ、幅広く学ぶことで可能性と選択肢を広げることを目指す立川国際中等教育学校。ですので、生徒様に様々なことを経験させたり、興味や関心の幅を広げるような取り組みをご家庭でもされると、入学後の学校生活をより充実したものにつながるでしょう。
生徒様の一瞬の発見や疑問を見逃さず、将来に向けて大切な芽を育ててください。
(2)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けをする
生徒様と向き合っていると、つい保護者様ご自身やご兄弟、他の生徒様と比較してしまいたくなる時があるのではないでしょうか。ですが、生徒様は1人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気に火が着くタイミングは異なります。
他の人と比べたくなる気持ちは抑えて、生徒様ご本人の成長や変化に目を向けて、保護者様は常に生徒様の味方であるという姿勢で前向きな声掛けをしましょう。それが、多感な時期の生徒様の自尊心を守ることにもつながります。
(3)健康管理とメンタル面のサポートをする
思春期に差し掛かり、多感で繊細な年頃でもある小学校高学年。大人が想像する以上に忙しく、負担も大きいものです。大人の気が付かないところで不安を抱えていたり、プレッシャーと戦っていたりしています。
だからこそ、健康管理とメンタル面のサポートは、保護者様にしかできない、最も力を入れていただきたいサポートです。生徒様が1日をよりよい状態で過ごせるように、食事や睡眠時間等のサポートに加え、生徒様がストレスを抱えたり不安を感じたりした際にも話しやすい関係作りを心がけましょう。
その一方で、自律に向けて歩みはじめている時期でもあります、1人で心を落ち着かせたり、学習に集中したりできるような環境づくりをして、大人が先回りしすぎないことも大切にしてください。
まとめ
東京都立立川国際中等教育学校は、語学力を強みに幅広く教養を身に付け、人格を陶冶することで国際社会に貢献できるリーダーを育てることを目標にしています。帰国生や在京外国人生徒も多く在籍しているため、日常から国際感覚と多様性が養われます。
入学検査は海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集の2つの募集枠があります。海外帰国・在京外国人生徒枠募集を受験する際には、応募資格の確認を兼ねた事前相談が必要ですので、募集要項をご確認ください。
一般枠募集での入学者は他の都立中高一貫校と同様に、小学校5・6年生の成績に基づく報告書と、2月3日に実施される適性検査の総合得点で決定します。調査書の割合は25%、適性検査Ⅰは独自作成問題です。適性検査Ⅱの大問1、算数領域の問題の配点が20%と高いため、十分な対策をして試験に臨みましょう。
「教養主義」を掲げる学校ですので、ご家庭でも、生徒様の日常生活から興味・関心を広げる素地を育てられるよう、生徒様の感じた小さな発見や疑問も大切に育てられるようにしましょう。
また、生徒様ご本人の成長に目を向けた声掛けをして、健康面とメンタル面での後押しをしていただければと思います。合格を目指して頑張る生徒様と保護者様を応援しています。
【参考文献】
・声の教育社「東京都立立川国際中等教育学校2025年度用スーパー過去問」
・都立立川国際中等教育学校ホームページ
・令和7年度東京都立立川国際中等教育学校案内
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら