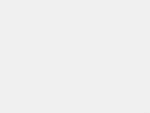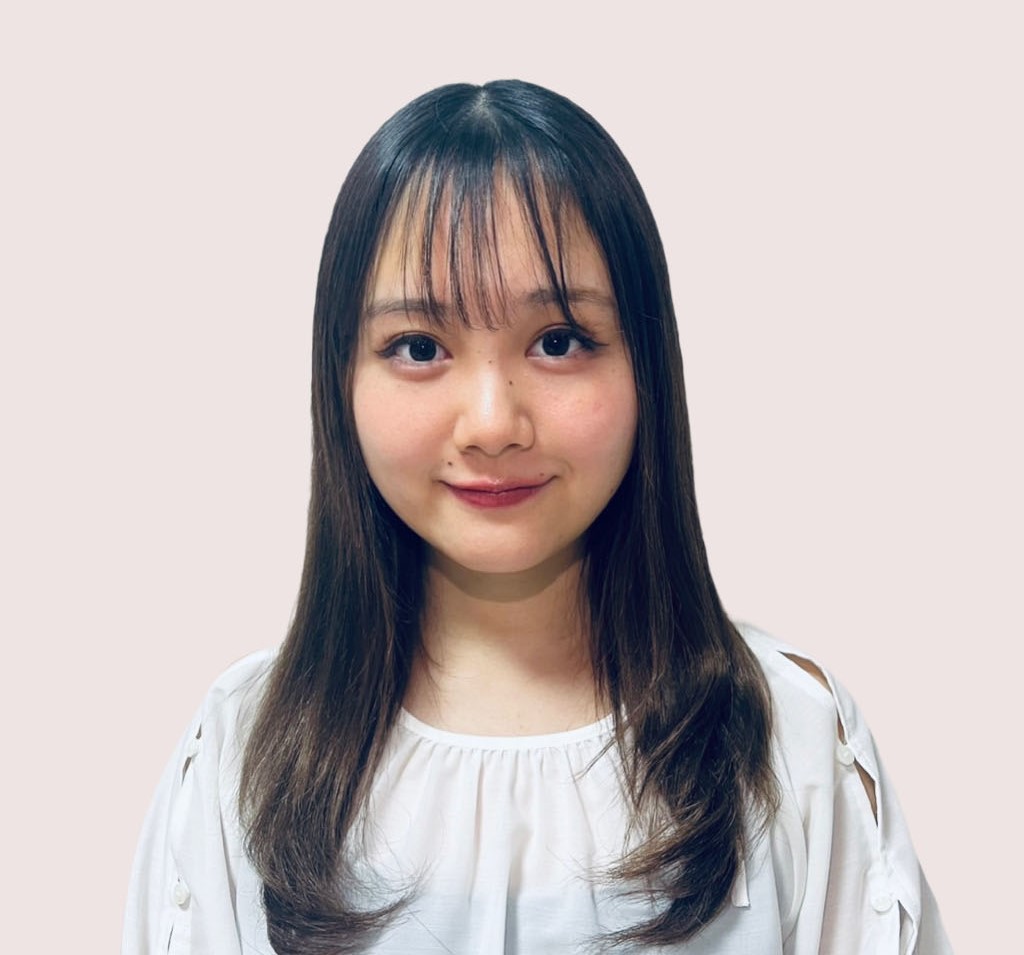1. 東邦大学付属東邦中学校とは?
東邦大学付属東邦中学校は、千葉県習志野市にある創立63年の伝統校です。「自然・生命・人間」を教育理念とし、生徒一人ひとりが主体的に学び、自ら考え行動する力を育むことを目指しています。
渋谷教育学園幕張中学校、市川中学校と並び、「千葉御三家」と称される中高一貫の共学校です。
2. 東邦大学付属東邦中学校の入試傾向について
入試全体の特徴や各科目の出題傾向、難易度について解説します。
①東邦大学付属東邦中学校の入試の特徴
東邦大学付属東邦中学校の入試は、前期試験と後期試験の2回に分けて実施されます。前期試験は1月21日、後期試験は2月3日に実施され、とくに前期試験での合格を目指すことが重要です。
2024年度のデータによると、前期試験の倍率は2.2倍で、約半数の受験者が合格しています。一方、後期試験は定員が少ないことから倍率が17.3倍と非常に高く、狭き門となっています。
試験科目は算数・国語・理科・社会の4科目で構成され、試験の形式や配点は以下の通りです。
- • 前期試験:各科目100点満点、合計400点満点
• 後期試験:算数・国語が100点満点、理科・社会は50点満点ずつで合計300点満点 - 2024年度の前期試験における合格最低点は264点であったため、全教科で平均7割以上の得点を目指すことが求められます。
また、後期試験は前期試験と比べて受験者数が少ない一方で、競争が非常に激しく、より高い得点率が求められることが特徴です。
②東邦大学付属東邦中学校の算数 問題の傾向と得点戦略
問題の傾向
東邦大学付属東邦中学校の算数は、計算問題→小問集合→応用問題の大問6題で構成され、試験時間は45分です。2024年度は全体的に取り組みやすい問題が多く、平均点が69.3点と高めでした。
試験では、基礎的な計算力、典型問題への対応力、そして図形や場合の数といった応用力が求められます。限られた時間内で得意分野を活かし、効率よく得点を重ねることが重要です。
得点戦略
算数では7割以上を目指します。
以下のように配点ごとの得点割合を意識し、確実に点を積み重ねましょう。
-
基礎問題で確実に得点を取る
計算問題は正答率が高く、全問正解を目標に短時間で確実に仕上げます。
仕事算は易しい典型問題のため、満点を確実に狙いましょう。 -
標準的な応用問題で得点を安定させる
場合の数は典型的な構成のため、ミスなく確実に得点します。
立体図形では、簡単な表面積や体積の問題を優先し、安定した得点を目指します。
解ける問題を選択し、無理なく得点を積み重ねることが大切です。 -
難易度の高い応用問題で部分点を確保する
平面図形は、相似や補助線を活用して部分点を狙います。
全問正解を目指すのではなく、得意分野に絞って効率的に得点します。
差がついた1問:大問4
問題内容
「1歩で1段または2段上がれる10段の階段を上がる際、(1)4段目までの上がり方の通り数、(2)10段目まで上がる際に5段目を踏まずに上がる方法の通り数を求める。」
解説
この問題は、場合の数の考え方を活用して解く典型的な応用問題です。とくに、(1)では規則性を見つけ、通り数を計算する論理的思考力が求められました。(2)では「5段目を踏まない」という条件を取り入れながら、解き方を工夫する必要がありました。
この問題は、一見シンプルに見えるものの、計算の正確性と条件を整理する能力が問われたため、受験生の思考力に大きな差が出た問題といえます。
③東邦大学付属東邦中学校の国語 問題の傾向と得点戦略
問題の傾向
国語の試験は試験時間45分、大問2題で構成されています。
出題内容は論説文と小説の長文読解が中心で、文章量は5,000~7,000字程度と中学受験では比較的短めです。
合格者平均点は7~8割と高めで、基本的な読解力と練習量が重要です。
得点戦略
国語では7割以上の得点を目標に、以下のポイントを押さえましょう。
-
長文読解の基本を徹底する
論説文: 段落ごとに要点を整理し、筆者の主張を把握します。
小説: 場面の変化や登場人物の心理を読み取り、中心テーマを見抜きましょう。 -
選択肢問題への対応を強化する
文中の根拠を素早く見つけ、消去法で正答を導く練習を重ねます。 -
漢字や語句問題を得点源にする
語彙や漢字を徹底復習し、基礎問題で確実に得点します。
差がついた1問:大問2
問題内容
受験期を迎えた主人公が、友人の絵麻と「努力」に関する意見の食い違いを通じて心情が揺れ動く場面を題材にした問題。絵麻の意見に反発し、わざと傷つけるような言葉を投げかけてしまった主人公が、気まずさを感じながらも普段通りの関係に戻ろうとする様子を問う問題が出題されました。
解説
この問題は、登場人物の心理の変化や関係性を、言動や会話の内容から読み解く力が問われました。とくに、主人公が絵麻にわざと傷つけるような言葉を投げかけた理由や、絵麻の意見に反発する心理の背景を分析する必要がありました。また、最後に二人の関係を修復しようとする様子を正確に読み取り、物語全体の流れを把握する力が重要でした。
このような問題は、登場人物の心理や物語全体のテーマを深く理解する力を養う練習が必要です。過去問や類似問題を使い、場面の変化や登場人物の心情をていねいに読み解く練習を積みましょう。
④東邦大学付属東邦中学校の理科 問題の傾向と得点戦略
問題の傾向
理科の試験は試験時間45分(前期)、30分(後期)で実施され、全分野(物理・化学・生物・地学)から幅広く出題されます。
基本知識を問う問題に加え、グラフや表、図を活用した応用問題が多いのが特徴です。また、時事問題が頻出するため、直前期にはその対策が必要です。
得点戦略
理科では7割程度の得点を目標に、以下のポイントを押さえましょう。
-
頻出テーマの復習を徹底する
生物: 植物の光合成や食物連鎖に関する問題を重点的に復習します。
地学: 天体や気象の基礎知識を押さえ、時事問題にも対応できる準備を進めます。
物理: 力のつり合い、てこ、ばねなどの計算問題を中心に練習します。
化学: 溶解度や化学反応の計算問題を正確に解けるようにします。 -
時事問題に対応する
環境問題や科学技術の最新情報をニュースや資料で確認し、総合問題で演習を重ねます。 -
得意分野を武器にする
苦手分野を克服するより、得意分野で確実に得点し、全体の点数を安定させます。
差がついた1問:大問4
問題内容
「66gの食塩を水100cm³に入れてかき混ぜると、29gが溶け残りました。水100cm³に食塩が限界まで溶けきったときの、食塩水1cm³あたりの重さは何gですか。小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで答えなさい。」
解説
この問題は、濃度計算の基礎的な考え方を活用して解く典型的な問題です。まず、溶けた食塩の量を計算し、次に全体の重さを求め、最終的に1cm³あたりの重さを算出します。一連の手順を正確に処理する計算力と、単位の扱いに注意を払う力が必要です。
とくに、溶け残りの量から「溶けた量」を計算するステップや、全体の重さを整理する手順でミスをする受験生が多く、この点で思考力の差が顕著に表れました。また、最後に小数第2位の四捨五入を求められる条件も含まれており、細かい計算ミスを防ぐ注意力も問われた問題といえます。
⑤東邦大学付属東邦中学校の社会 問題の傾向と得点戦略
問題の傾向
社会の試験は試験時間45分(前期)、30分(後期)で実施され、地理・歴史・政治経済の3分野からバランスよく出題されます。
資料や統計を活用した考察型の問題が多く、基本知識に加え、資料の読み取り力や論理的思考力が求められます。問題文量が多いため、効率的なスピード解答が必要です。
得点戦略
社会では7割以上の得点を目標に、以下のポイントを意識しましょう。
-
分野ごとの特徴を押さえる
地理: 日本地図や統計資料を基に、基本事項を地図と関連付けて覚えます。
歴史: 年表を活用して時代の流れを整理し、できごとの背景や関連事項を理解します。
政治経済: 憲法や政治の仕組みなどの基礎知識を正確に押さえます。 -
時間配分を意識した練習をする
簡単な問題から解き、時間を効率的に使う習慣を身につけましょう。 -
時事問題対策を欠かさない
環境問題や国際関係など、出題されやすいテーマを直前期に復習します。
差がついた1問:大問3
問題内容
「マンガ『はだしのゲン』を題材に、広島への原爆投下や日本国憲法前文、G7やTPPなどの国際条約に関する問題が出題されました。精神の自由、経済の自由など、日本国憲法の基本的人権についても問われました。」
解説
この問題は、政治経済分野の基礎的な知識を幅広く問う標準的な内容でしたが、設問の選択肢が複雑で、細かい知識と正確な判断力が必要でした。とくに、G7やTPPなどの加盟国を整理して答える問題や、日本国憲法の前文に関する問題で、知識の有無による差が顕著に表れました。
また、「精神の自由」「経済の自由」「身体の自由」を分類する問題では、基本的人権の体系的な理解が求められました。正解するためには、政治や憲法に関する基礎知識を正確に押さえつつ、資料問題への対応力を磨くことが重要です。
とくに、時事問題や国際条約に関する知識を普段から整理しておくことが効果的です。
3. 東邦大学付属東邦中学校を受ける際の併願パターンについて
東邦大学付属東邦中学校を受験する際は、1月の地方校受験と2月の本命校受験を組み合わせるのが一般的です。
1月には市川中学校や渋谷教育学園幕張中学校がよく選ばれます。これらは「千葉御三家」と呼ばれる難関校で、実力確認の場としても活用されます。また、埼玉や茨城の難関校を受験するケースもあります。
2月の本命校受験では、東邦中学校の前期試験(1月下旬)がメインとなり、同日に他の千葉県内の学校を併願する場合があります。2月上旬には渋谷教育学園幕張中学校や市川中学校の追加受験を組み合わせるケースも見られます。
併願校の選定は、志望順位や実力に応じたバランスが大切です。東邦中学校の前期試験に合格すれば、後期試験や他校受験の負担を軽減できます。併願スケジュールをしっかり計画し、最適な受験プランを準備しましょう。
4. 東邦大学付属東邦中学校の受験対策方法
志望校合格に向けた時期ごとの学習内容や効果的な過去問活用法、保護者様のサポート方法を徹底解説します。
①時期別・教科別対策内容
(1)小4:基礎力の徹底
| 算数 |
四則計算や簡単な文章題、基本的な図形問題を中心に、計算力と理解力を養います。 練習問題を繰り返し解き、スピードと正確さを意識しましょう。 |
| 国語 |
語彙や漢字の知識を広げるとともに、短文読解になれることを目指します。 物語文や説明文の基本的な内容を読み取る力を身につけることが重要です。 |
| 理科 |
植物や動物などの身近なテーマを通じて、観察力を育てます。 簡単な実験の記録や結果の考察にも取り組み、科学的な思考を養いましょう。 |
| 社会 |
地図や白地図を使い、日本地理の基礎知識を習得します。 都道府県名や主要な地形、産業の特色を覚えることが目標です。 |
(2)小5:応用力の育成
| 算数 |
割合や比、速さなど、入試に直結する重要単元を習得します。 図形や場合の数などの応用問題にも挑戦し、思考力を高めることがポイントです。 |
| 国語 |
長文読解に取り組み、段落ごとの要旨を把握する練習をします。 説明文の要点整理や物語文の心情理解を中心に、記述式問題にも取り組み始めましょう。 |
| 理科 |
力や光、水溶液の基本を押さえ、実験問題に対応する力を養います。 グラフや表を使った問題にもなれることが重要です。 |
| 社会 |
統計やグラフを読み解く力を養い、日本地理の復習を進めます。 歴史では、時代ごとの大きな流れをつかむことを目標とします。 |
(3)小6(4月~6月):基礎と応用の総復習
| 算数 | 四則計算や割合、速さ、場合の数、図形問題などの基礎単元を総復習します。 |
| 国語 | 長文読解の練習を重ね、段落ごとの要旨を的確に把握する力を養います。 |
| 理科 | 力や光、水溶液などの基本単元を復習し、グラフや表を読み解く力を強化します。 |
| 社会 | 日本地理や歴史の復習を進め、重要事項を確実に覚えます。 |
(4)小6(7月~8月):実践力の強化
| 算数 |
模試や過去問を通じて、時間配分を意識した実践練習をします。 応用問題に重点を置き、とくに図形や場合の数など難易度の高い問題に挑戦します。 |
| 国語 | 長文読解の演習を増やし、記述問題の精度を上げます。 |
| 理科 | 過去問演習や模試を通じて、グラフや表、時事問題を含む総合的な問題に取り組みます。 |
| 社会 | 歴史の流れを再確認し、地理の応用問題にも取り組みます。 |
(5)小6(9月~11月):志望校対策
| 算数 | 東邦中の過去問に特化した対策を開始し、難問への対応力を高めます。 |
| 国語 | 過去問を使い、東邦中の出題傾向に特化した練習を進めます。 |
| 理科 | 過去問で頻出のテーマを確認し、苦手分野を重点的に克服します。 |
| 社会 | 東邦中の出題傾向に合わせ、統計資料やグラフ問題への対応を強化します。 |
(6)小6(12月~1月):総仕上げと直前対策
| 算数 | 総復習と過去問演習を繰り返し、ミスを防ぐ練習をします。 |
| 国語 | 直前期は短めの文章や基本的な問題に取り組み、確実な得点を目指します。 |
| 理科 | 基礎的な知識の復習をして、実験や観察の総合問題に取り組みます。 |
| 社会 | 直前期は時事問題や基礎的な地理・歴史の復習を徹底します。 |
②東邦大学付属東邦中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
過去問は、試験傾向を把握し、得点力を高めるために重要です。まず全体の形式や出題パターンを確認し、苦手分野を洗い出します。演習後は必ず解き直しをして、正答の根拠を理解することで実践力を向上させましょう。
(2)いつから解き始めればよいか
過去問の演習は、小6の夏休みから始めるのが理想です。まずは時間配分を意識せず取り組み、問題形式になれます。その後、秋以降に本番同様の条件で解き、志望校に合わせた実践力を養う段階に移ります。
(3)何年分を何周解けばよいか
志望校の過去問は5~7年分を3周以上解くのが効果的です。1周目は形式の理解、2周目は弱点克服、3周目以降はスピードと正確さを意識した仕上げをします。余裕があれば、他校の類似問題も演習するとさらに力が付きます。
(4)保護者様にできるサポート内容
中学受験を控えた生徒様にとって、保護者様のサポートは大きな力となります。励ましや生活面でのサポートを通じて、安心して学習に取り組める環境を整えることが大切です。また、子ども自身が計画を立てて進められるよう、見守りつつ適切なタイミングで声をかける工夫も必要です。
実際の声かけや対応例
日々の努力を認める声かけ
「今日はどこが難しかった?」「ここができるようになってすごいね!」と具体的に話を聞き、日々の努力をしっかり認めましょう。
学習計画の確認
「明日は何を重点的にやるの?」と聞くことで、自分で計画を立てる習慣をサポートします。
試験直前の励まし
「これまで努力してきたことは絶対に役に立つよ」と自信を持たせる言葉を伝えましょう。
保護者様の温かいサポートが、子どもの意欲と安心感を支える大きな力になります。
まとめ
本記事では、各科目の傾向や得点戦略、過去問の活用法、併願校の選び方、保護者様のサポート方法を詳しく解説しました。
生徒様が計画的に学習を進めるためには、保護者様の適切な励ましと環境づくりが大きな力となります。本記事の内容を参考に、合格に向けて確実な準備を進めましょう。
【参考文献】
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東邦大学附属東邦中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら