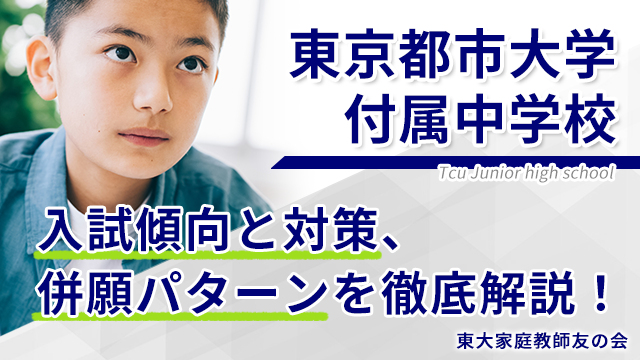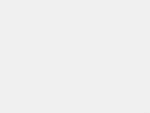1. 東京都市大学付属中学校とは?

2009年に武蔵工業大学付属中学校から現在の名前に名称変更。その後、少しずつ難易度が上がっていき、現在では進学校の一角として人気の高い中学校です。合言葉は「勉強も部活も100対100」。約9割の生徒様が部活に入り、勉強との両立を図っています。
同校では、受験段階からⅡ類とⅠ類に分かれており、Ⅱ類の方が難易度が高いです。中学一年生の段階では、Ⅱ類が2クラス、Ⅰ類が4クラス構成となっており、その後の状況で、Ⅱ類を増やすこともあるそうです。授業としては、進度に違いは無いものの、Ⅱ類の方が発展的な内容まで扱います。
2. 東京都市大学付属中学校の入試傾向について
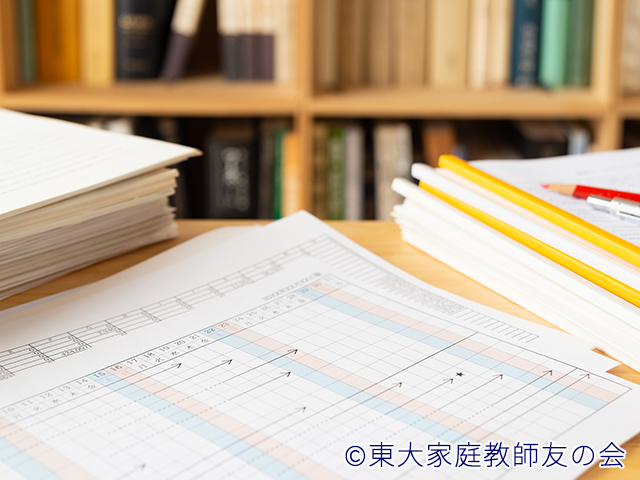
第一回・第三回・第四回がそれぞれ、算数・国語・理科・社会の4科目の試験です。
第二回が算数・国語の2科目の試験となります。
また、グローバル入試が第三回と同じ日程で行われ、算数・国語・英語の3科目の試験です。
試験時間は第一回・第三回・第四回が共通で、算数50分・国語50分・理科40分・社会40分、配点は各々100点・100点・75点・75点です。
第二回の試験時間が算数・国語各々50分、配点は各々100点です。
グローバル入試の試験時間は算数・国語・英語各々50分、配点は算数100点・国語50点・英語100点です。
第一回~第四回で出題形式の変化はほぼ無く、昔からの出題形式が踏襲されている学校です。
算数の難易度が高い上に、差がつきやすく、標準的な問題でいかにしっかりと点数を取るかが鍵となります。
図形・数の問題・速さが頻出単元で、図形が全体の半分ほど出題されます。
そのため、図形の問題を中心に対策をするのが良いでしょう。
総じて、試験時間が短く感じられる試験です。素早く、正確に解ける様に演習して下さい。
①算数
例年、大問が5題出題されます。問題傾向は昔から変わらず、また、第一回~第四回までの傾向も変わりません。
大問1番は小問集合で、約8題の設問があります。計算問題・単位問題・食塩水・図形が頻出です。基本~標準的な問題が出題されますので、完答を目指していきたい所です。
大問2番以降は、単元別の問題となっています。図形の問題が最もよく出題され、次いで数の問題・速さです。以下、詳しく見ていきます。
図形は、平面図形・立体図形どちらも出題されることが多く、小問と合わせると、全体の半分程度が図形の単元です。
平面図形は、面積比・相似の問題が多く出題されます。標準~やや難しいレベルの問題です。一方、立体図形では、切断・展開図・回転体・体積などが出題されています。一見難しい問題が出題されることもありますが、よくよく考えると標準的な問題であることも多いです。
2024年度第一回でも大問4番で立体図形の問題が出題されました。水の体積の問題で、一見、難しい問題に見えますが、実際にはそこまで難しいわけではなく、標準~やや難しいレベルの問題でした。見た目に惑わされずに、考える習慣が出来ていた生徒様は対処出来た問題で、差がついた問題であったと考えられます。
数の問題は、規則性・場合の数・約数・倍数・思考力問題と多岐に亘ります。完答を目指したい問題もありますし、思考力問題でやや難しい問題も出題されます。問題のレベルに応じて、最後の設問は飛ばすなど、臨機応変な態度が求められます。
速さの問題は、グラフ(ダイヤグラム)を伴うことが多いです。標準的な問題が出題されることが多いですから、完答を目指していきたい単元です。強化すべき単元と言えるでしょう。
②国語
例年、大問3~4題の出題で、説明文、物語文、詩が大問で1題ずつ出題されます。漢字・語彙・文法問題が独立して大問とされる場合があり、その場合に大問が4題になりますが、実質的には変わりありません。また、第一回~第四回まで出題形式に大きな変更はありません。ちなみに2024年度は大問数が4題で統一されていました。
説明文・物語文共に文章量は多く、制限時間を考えますと、かなり速く読まなくてはなりません。幸い、記述問題が非常に少ない学校ですから、書く内容で悩む必要は、あまりありません。大問最後には要旨を答える記号選択問題がありますから、日頃から要旨を読み取る練習は行う必要があります。
詩は東京都市大学付属中学校の大きな特徴です。他校ではあまり見かけないため、対策が疎かになりがちですから、東京都市大学付属中学校を受験すると決めたら、すぐに取り掛かりましょう。詩で重要なのは表現技法・見た目の形式(カタカナが使われている、など)・季節です。詩が苦手な生徒様は、まずここから始めて行きましょう。
2024年度第一回も、詩は出題され、表現技法や季節といった基本的な設問が出題されていました。生徒様で詩が得意な方は中々いらしゃいません。ですから、基本的な所をしっかり取れれば、差はつきにくいです。逆に、上記のような表現技法の設問で落としてしまうと、差がついてしまいます。基本的な対策をしっかりと行っていきましょう。
③理科
例年、大問4問の出題で、物理・化学・生物・地学がバランスよく出題されています。全体的に難しい問題も多く、考察問題や実験問題が中心となっています。全単元で計算問題が出題されることもあり、時間内で解き切るのは大変な作業です。
物理は、てこ・ばね・電気・光・音など満遍なく出題されています。考察問題が中心で、中学校や高校で習う内容を誘導文によってわかりやすくした問題が出題されることがあります。
2024年度第一回でも、高校物理で習う箔検電器に関する問題が出題されました。文章や資料をしっかり読み解きながら解く問題でしたので、対応出来た生徒様とそうでない生徒様で差がついた問題だったと思われます。
化学は、知識問題と計算問題がどちらも出題されます。表やグラフを用いた実験問題が出題されますので、総合的な実力がないと解けない問題です。
生物は、知識問題も出題されますが、実験・考察問題が中心です。計算問題が出題されることもありますので、抵抗感なく行えることが大切です。
地学も、生物同様、知識問題が出題されますが、やはり考察問題が中心です。天気・天体の問題が出題されることが多く、やはり計算が絡む問題も出題されます。地学だからと言って、計算が出題されないと思わない事です。
④社会
例年、大問3題で出題されることが多く、1番が地理、2番が歴史、3番が公民・時事問題となっています。記述問題はほぼ出題されませんが、漢字指定の問題がありますので、難しい漢字も書ける様にした方が良いでしょう。
地理は、幅広く学習を進めた方が良いですが、特に、人口・面積・雨温図・都市の場所・地形など、地図帳に載っているものが数多く出題されています。地図帳の地図の部分は勿論ですが、その他の統計に関わるページも全て確認した方が良いでしょう。
歴史も、幅広く知っておく必要があります。ある出来事が、何時代に起こったのかをスラスラ言えるように対策を行いましょう。また、出来事の順番を答える問題がありますから、年号暗記も必須です。有名な出来事については、年号もしっかりと暗記しましょう。
公民・時事問題についてですが、公民分野は憲法・国会・国際機関を中心として出題されます。基本的な問題が多いですから、細かく暗記する必要はないでしょう。
一方、時事問題はしっかりとした対策が必要です。公民よりも出題される設問数が多めで、2024年度第一回でも、同様の傾向でした。この回は、新聞記事をベースとした問題が出題されましたので、日頃から新聞に目を通していた生徒様と、そうでない生徒様では、大きく差がついた問題だったと思われます。
入試回数によっては、時事問題のみが出題されることもありますので、時間を掛けて対策を行って下さい。尚、時事問題と絡めて、一般常識問題(彼岸は何月か?還暦とは?など)が出題されることがあります。
⑤英語
グルーバル入試では英語が出題されます。問題は、英検準二級程度、日本で言う所の高校中級程度のレベルの問題が出題されます。
問題は大問が5題程度出題され、大問1・2番が文法と語順整序の問題。残りの大問3題が文章題となっています。
英検準2級の問題が参考にはなりますが、文法問題には時間を掛けて取り組んだ方が良いでしょう。動詞を中心とした語法や熟語の対策も行って下さい。
⑥問題の形式等が似ている学校は?
算数や理科の計算問題、記述問題の字数が少なめな点など、巣鴨中学校は似ている点が多いと言えるでしょう。但し、東京都市大学付属中学校特有の問題もありますので、あくまで参考という形で考えて下さい。
3. 東京都市大学付属中学校を受ける際の併願パターンは?
①1月受験校
|
城北埼玉中学校・大宮開成中学校・西武学園文理中学校・栄東中学校
|
1月は練習として、城北埼玉中学校・大宮開成中学校・西武学園文理中学校・栄東中学校が挙げられます。
しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。栄東中学校が少し高めですから、無理はせず、受験しない選択肢はあると思います。
②2月1日
|
午前:東京都市大学付属中学校(1次) 午後:東京都市大学付属中学校(2次)
|
午前入試・午後入試共に東京都市大学付属中学校で決まりでしょう。2次では、算数・国語の2科目入試となりますが、算数・国語が苦手であっても、受験したい所です。
③2月2日
|
午前:巣鴨中学校(2次)・世田谷学園中学校(2次)・安田学園(3次)
|
2日午前の入試は、巣鴨中学校(2次)・世田谷学園中学校(2次)がおすすめですが、この後も東京都市大学付属中学校を受験することになると、抑え校を受験しないことに不安を感じられるかもしれません。そこで、安田学園(3次)を受験するのも良いと思います。
2日午後は、次の日も受験がありますから、受けなくて良いと思います。休養に充てて下さい。
④2月3日
|
午前:東京都市大学付属中学校(3次)
|
3日午前は、東京都市大学付属中学校(3次)で決まりです。午後は、暁星中学校(2次)がありますが、レベルが高く、試験傾向もマッチしておりませんので、受験しなくて良いと思われます。
⑤2月4日
|
日本学園中学校(2次)・獨協中学校(4次)
|
4日を受験するということは、ここまでの状況が芳しくないということです。ですから、抑え校を考えていきましょう。
日本学園中学校(2次)・獨協中学校(4次)が宜しいかと思います。
2月5日に東京都市大学付属中学校(4次)がありますから、最後まで諦めずに頑張りましょう。
4. 東京都市大学付属中学校の受験対策方法

東京都市大学付属中学校は、試験日によって受験傾向に変更は無く、算数で差がつきやすい傾向があります。
算数は、標準~やや難しい問題で、図形・数の問題・速さが頻出です。
図形で約半分出題されますから、特に力を入れる必要があります。
国語は、記述問題が少ないものの、詩が出題されるのが特徴です。
全体の文章量が多いですから、制限時間内に終えるには苦労を強いられます。
理科は、実験・考察問題が多く、普段から考える癖付けが必要です。
暗記よりも理解が問われますので、何故そうなるのか、考えながら取り組みましょう。
社会は、時事問題の比率が高く、ニュース・新聞が重要となります。
全体的に幅広く学習することが必要です。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくと良いでしょう。
東京都市大学付属中学校は、小問で満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。
図形問題では応用問題にも挑戦し、強くしておきたい所です。
また、計算力も必須です。東京都市大学付属中学校では、計算問題が出題されますし、どの問題も高い計算力が必須です。
速く、正確に計算が出来るように、毎日トレーニングをして下さい。単位計算も重要です。
国語も、カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにして下さい。
文章を読んでから、要旨を50字程度で書いていくのが、読解力向上に良いでしょう。
少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行いたい所です。
また、詩の対策も必要です。表現技法を定着させ、出来れば詩集も読むと良いでしょう。「ウイニングステップ小学四年生物語と詩」(日能研ブックス)といった問題集で詩に慣れるのも良いでしょう。
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
また、暗記だけではなく、身の回りの現象理解がとても大切です。これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察して下さい。
可能でしたら、自由研究にも是非取り組んでみて下さい。
今の段階で、「スーパー理科事典」(受験研究社)のような図鑑を眺めるのも効果的です。考察問題・実験問題の下知識となるでしょう。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。
地図帳の雨温図や統計部分にも目を通すと良いでしょう。
一般常識問題に対応出来る様に、昔から使われている言葉を知っていきましょう。
(2)小学五年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにして下さい。
少し時間が経ってしまうと、出来なくなってしまう事も多いです。
図形・数の問題・速さには特に力を入れて頂き、応用問題まで解けるようにしていきましょう。
国語は、物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。
生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を100字程度で書く練習をしましょう。
正誤選択問題では、しっかりと文章に戻って、正しいかどうかの判断をするようにして下さい。
読書は継続的に行い、漢字・語彙・文法も忘れずに行って下さい。詩集を読むのも良いでしょう。
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。東京都市大学付属中学校では、よく出題されておりますし、難易度も比較的高い問題が出題されます。
引き続き、小学四年生の暗記事項を復習しながら、新しい内容も覚えて行って下さい。
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記を行って下さい。
出来事の整序問題が出題されますので、年号暗記も忘れずに行って下さい。
この時期から時事問題に対応出来る様に、ニュース・新聞を見る様にすると良いでしょう。
(3)小学六年生(4月〜6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
特に、図形・数の問題・速さに苦手意識がある場合、この時期に強化して下さい。
過去問の問題を一度解いてみて下さい。
国語は、標準的な文章で、設問の解き方を確認して下さい。
この時期は、特に抜き出し問題に力を入れて頂きたいと思います。
似ている内容を把握できるか、そこから抜き出せるか。また、要旨把握型の抜き出し問題であれば、要旨をしっかり掴んだ上で適切に抜き出せるか、練習しましょう。
算数同様、過去問を一度解いてみて下さい。
理科は、引き続き、計算問題の力をつけて行きましょう。
計算問題が苦手な生徒様は特に力を入れて復習して下さい。
過去問は、一度この時期に解いてみて頂けると、夏休みが有効活用出来ると思います。
社会は、公民が始まります。基本的事項は押さえつつ、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。
時事問題対策として、ここ20年程度の時事について押さえておくと良いでしょう。
(4)小学六年生(7月〜8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
基本~標準問題対策として、「プラスワン」(東京出版)はおすすめです。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
図形・数の問題・速さについては、引き続き重要視して取り組んで下さい。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。
詩については、表現技法や季節の確認をしつつ、他の過去問を使用しても良いでしょう。芝浦工業大学附属中学校や青山学院中等部の問題は良い教材になるでしょう。
語彙・漢字・文法については、この夏休みで固めていきましょう。
理科も、過去問を3〜5回分解きましょう。暗記出来ていない部分は、この夏休みに対処しましょう。
計算問題については、少し難しい問題にも対応出来るようにしていきましょう。
社会は、過去問を3〜5回分行いましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強して行きましょう。
歴史の流れを再度理解し直し、年号暗記を固めていきましょう。
地図帳・ニュース・新聞は引き続きよく見て知識を広げましょう。
(5)小学六年生(9月~11月)
算数は、過去問中心になりますが、特に解き直しに力を入れて下さい。
図形・場合の数・速さを含めた演習には「ステップアップ」(東京出版)もおすすめです。
国語は、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙・文法の強化も忘れずに行なって下さい。
過去問の解き直しも行いましょう。
この時期でも、読書は継続して頂き、詩も含めた様々なジャンルに触れましょう。
理科も、やはり過去問・解き直しを中心に行っていきます。
計算問題が出来るようになると、理科の点数は高いレベルで安定します。
理科事典・図鑑を見る時間も設けましょう。
社会も、過去問とその解き直しが中心です。
「日本のすがた」の最新版を使用して、地理の統計対策にも力を入れましょう。
時事問題も大手塾から出版される「重大ニュース」を確認しましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問の解き直し、特に図形・数の問題・速さにはかなり力を入れて下さい。
この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。
基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、全般的な復習をしましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙・文法の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、今まで習ってきた内容や、過去問の内容の復習です。理科事典・図鑑で最後の知識整理です。
計算問題は、過去問の解き直しや、問題集に出てくる標準~やや難しいレベルまで解ける様に、復習をして下さい。
生物や地学分野での計算も解ける様にしましょう。
社会は、引き続き「日本のすがた」の最新版や地図帳を使用して、多くのデータに関する知識を蓄えましょう。
出来る限り、時事問題・常識問題対策を行いましょう。
②東京都市大学付属中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
東京都市大学付属中学校は、算数が最も差がつきやすい科目です。
大問で出題される単元はある程度決まっていますから、過去問を遡ることが効果的です。
理科の計算問題も、算数同様にできるだけ遡って演習しましょう。
どちらも解き直しが大変重要となってきます。
一方、国語と社会は形式に慣れることが大切で、そこまで遡る必要はないでしょう。
但し、国語の詩は遡って行うことをおすすめします。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と国語については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。
この2科目が受験生間の差がつきやすいです。
理科も出来れば夏休み前から始めましょう。難しい問題が多いですから、早めに状況を把握しておくと、夏休みの勉強が効果的になるでしょう。
社会は夏休みからで良いでしょう。形式に慣れて頂ければ良いと思われます。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、図形・数の問題・速さといったよく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。
従って、最低10回分、出来れば20回分解いておきたい所です。
まずは時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は、制限時間内に終えるには大変だと思われます。
時間内に解ける様に、最低5回分、出来れば10回分解くと良いでしょう。但し、詩については遡れるだけ遡ると良いでしょう。
2周解き直しが出来れば良いと考えます。
理科も、制限時間内に終えるには苦労を強いられます。計算問題を中心に似た問題も出題されます。
そのため、最低10回分、出来れば20回分解くと良いかと思います。
解き直しについては、計算問題の解き直しを中心に3~4周行いましょう。
社会は、形式に慣れるために、最低5回分、出来れば10回分解くと良いでしょう。
時事問題で再度出題される可能性は極めて低いです。2週解き直しが出来れば良いでしょう。
③保護者様に出来るサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)思考力強化
東京都市大学付属中学校の算数・理科対策として、低学年のうちから塾の教材以外での思考力強化を考えましょう。
即ち、勉強としてではなく、楽しみながら思考力を強化する方法を考えましょう。
具体的には、パズル・タングラムなどで図形的思考力を、将棋・チェス・トランプ・algoなどで論理的思考力を養うことが重要です。
私も、上記のような遊びを両親と共に行うことで、強化していきました。
是非、保護者様も生徒様と一緒に遊んでみて下さい。
(3)理科の対策
東京都市大学付属中学校の理科は、これまでご説明している通り、理解を問う問題が多く出題されております。
保護者様としましては、身近な事柄について、生徒様と会話をし、一緒に調べて理解を促すようにして頂けると宜しいかと思います。
例えば、
「洗濯物を干すと乾くのは何故だろうね?」
「シャボン玉の仕組みを一緒に考えてみようか」
「地震が起きる仕組みを一緒に調べてみようか」
など、日常当たり前の事をしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。
是非、保護者様と一緒に考察してみて下さい。
まとめ
東京都市大学付属中学校は、全科目的に難しい問題が多く、時間内に終えるには苦労をさせられます。日頃から、視野広く、考える習慣付けが必要な学校です。一番差がつく科目は算数です。図形が約半分出題されますので、十分な対策が必要でしょう。
難しい問題が多いとお話していますが、見た目の難しさに惑わされない様にして下さい。よく考えれば標準的な問題も多いため、諦めない姿勢が肝心です。これは、全科目的に言えますので、問題文をよく読んで、しっかり考えましょう。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東京都市大学附属中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら