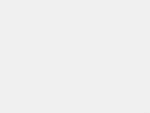1. 早稲田中学校とは?

中学受験難関校の一つである早稲田中学校。
1895年に設立され、早稲田大学系列の附属校として、高い人気を誇っています。
大きな特色としては、学年の約半数は受験をする事です。
学校名を見ると、全員が早稲田大学に進学するかと思われますが、実際には受験校色が強い学校です。
早稲田大学の推薦を考えながら、大学受験も目指す生徒様が大半という状況です。
実際に、私の教え子も早稲田中学校から東京大学に進学致しました。
ですので、附属校という考え方ではなく、進学校という認識で入学される方が正しいと思われます。
早稲田中学校の特徴的な行事は利根川歩行。
中高六年間を通じて、利根川上流~下流の千葉県犬吠埼まで歩きます。
高校三年生に犬吠埼到達時は大きな達成感と感動に包まれます。
最近は利根川ではなく、荒川で行う学年もあり、学年毎に計画を練ることが出来ます。
2. 早稲田中学校の入試傾向について

第一回・第二回共に、算数・国語・理科・社会の4科目の試験です。
それぞれの配点と試験時間は以下の通りです。
|
・算数:60点(50分) ・国語:60点(50分) ・理科:40点(30分) ・社会:40点(30分)
|
第一回・第二回で出題形式の変化はほぼ無く、昔からの出題形式が踏襲されている学校です。
算数と、理科の計算問題で差が付きやすく、基礎〜標準的な問題をいかに取りこぼし無く取っていくかが最大の課題です。
また、問題量に対して試験時間が短いですので、速く、正確に解く練習は欠かせません。
①算数
早稲田中学校の算数は、過去から今まで、大問5問の形式に変更はありません。
これは、一次試験・二次試験共に同じです。
大きな傾向としては、図形の割合が高く、平面図形・空間図形双方共に、しっかりとした対策が必要な学校です。
基本~標準的な問題が多いですが、図形はやや難易度が高いです。
大問1は、別々の小問3つの問題で構成されており、計算問題・割合と比・場合の数・推理問題などがよく出題されますが、満遍なく出題されております。
この小問3つを確実に取れるかどうかが合否の分かれ目になってきます。
大問2では、平面図形が出題されまして、小問3題で構成されます。
角度・面積・回転体の3題が出題されることが多く、2題取れると後の展開が楽になるでしょう。
大問3〜大問5も各々小問3題構成となっています。
やはり多様な問題が出題されておりますが、速さ・立体図形は高頻度で出題されております。
速さは流水算・時計算・通過算といった特殊論点もよく出題されており、注意が必要です。
立体図形は立体切断の問題が多く、しっかりとした対策が必要でしょう。
ちなみに、2024年度第一回入試で、合否を分けた問題としては、第5問の立体切断の問題だと思われます。
苦手な生徒様ですと全滅した可能性がある一方で、しっかりと対策をしていた生徒様は2問は解けたのではないか、と考えられます。
立体切断はよく出題されますので、時間を取って取り組んで下さい。
②国語
国語は、大問2問出題され、説明文と物語文が1題ずつの構成です。
設問は、漢字・語彙・記号選択・記述問題がバランス良く出されております。
記述問題は出題されるものの、字数は多くても60字程度ですから、長い記述問題ではありません。
設問は標準的なものが多いですが、文章自体が難しい事もあります。
読書を継続的に行い、難解な文章も読めるようにして行きましょう。
ちなみに、2024年度第一回入試で、合否を分けた問題は大問2番でしょう。
この問題は説明文ではありますが、随筆文的な文章でもあり、読みやすいものの、設問になると解きづらいという問題でした。
また、文章中にサッカーの例が上がっており、サッカーがわからない生徒様には何を言っているか、イマイチ良くわからなかったようです。
読書で様々なジャンルの文章に触れつつ、勉強以外にも多くの事に興味を持って生活することが必要ですね。
③理科
大問は4問で構成されており、物理・化学・生物・地学がバランス良く出題されております。
物理では、計算問題が中心に出され、てこ・ばね・浮力・電気と満遍なく出題されているのが特徴です。
計算問題にしっかり対処出来るように、演習を積んでください。
化学でも、やはり計算問題が中心で、与えられている表やグラフを分析しながら、気体の発生量や中和を計算する問題が出題されています。
似たような問題が出題されることもありますので、過去問の解き直しは必須です。
尚、2024年度第一回入試では、典型的な化学の計算問題が出ました。
この問題でしっかりと点数を取れたかどうかが、合否を分けたと思われます。
生物は、昆虫・植物を中心に、細かい暗記事項が出題されています。
考察問題も必ず出題されておりますので、単なる暗記だけではなく、理解も必要です。
地学では、太陽・月・星・惑星といった天体と、地震・化石などを含めた地層が良く出題されます。
天気が出題される事もあります。全体を通して、記述問題はあっても1.2問程度で、字数も多くはありません。
特別な対策は必要無いでしょう。
④社会
大問3〜4問で出題されます。
地理・歴史・時事問題の出題が多く、公民の出題は少なめです。
大問の1〜2問は歴史での出題、残りの大問は、地理のみ、もしくは時事問題を題材とした総合問題です。
地理は、全般的に出題されておりますが、特に雨温図と統計に注意して下さい。
どちらもほぼ毎年出題されています。
特に統計は、「日本のすがた」の最新版でしっかり確認すると良いでしょう。
歴史も全般的に出題されておりますが、江戸時代以降が特に重要です。
出来事の並び替え問題は必ず出題されますので、年号の暗記をしっかり行いましょう。
公民は、基本的な単語の暗記は必要です。国際関係は細かい所まで、しっかり暗記を行いましょう。
時事問題は、他の中学校と比べて力を入れる必要があります。
細かい事項まで問われておりますので、各大手塾などから出版されている「重大ニュース」など、本を一冊しっかりと仕上げて下さい。
新聞を読む・ニュースを見るのも効果的です。
尚、2024年度第一回入試では、時事問題による総合問題が、大問3番で出題されました。
ウクライナ問題・ジェンダーギャップ・広島サミットなどが問われ、時事対策をしているかどうかがポイントとなりました。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
同じ位のレベルでは芝中学校が、そして少し低いレベルですと城北中学校が似ていると思われます。
但し、どちらの学校も、算数の立体図形と理科の計算問題が、早稲田中学校とあまり似ておりません。
そのため、それらについては、駒場東邦中学校の問題が参考になると思います。
早稲田中学校よりも難しい問題ですが、チャレンジするには良い問題だと思います。
過去問を解き尽くして、まだ余力が有れば、行なってみて下さい。
3. 早稲田中学校を受ける際の併願パターンは?

①1月受験校
【受験校の例】
西武文理中学校・栄東中学校・東邦大学附属東邦中学校
1月は、練習として、西武文理中学校・栄東中学校が挙げられます。
その後、少し難易度を上げて、東邦大学付属東邦中学校を受けるのが良いでしょう。
しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
【受験校の例】
午前:早稲田中学校(1次)
午後:巣鴨中学校(算数選抜)・東京都市大学附属中学校(2次)
午前入試は早稲田中学校(1次)で決まりです。
午後入試は受験しなくても良いと思います。
第一志望校となる早稲田中学校を受験後、相当に疲れると思います。
もし受験されるのであれば、東京都市大学附属中学校(2次)は抑え校として良いでしょう。
算数に自信がお有りでしたら、巣鴨中学校も良いと思います。
③2月2日
【受験校の例】
午前:午前:城北中学校(2次)・本郷中学校(2次)・桐朋中学校(2次)
2日の入試を抑え校としてお考えであれば、城北中学校(2次)はおすすめです。
試験の傾向も比較的似ています。
本郷中学校(2次)や桐朋中学校(2次)も考えられますが、難易度は高いため、対策は必要でしょう。
午後は、受けなくて良いと思います。
④2月3日
【受験校の例】
早稲田中学校(2次)
3日は早稲田中学校(2次)で決まりです。
⑤2月4日
【受験校の例】
城北中学校(3次) ・芝中学校(2次)
2月4日受験をどう考えるかによりますが、抑え校としてお考えでしたら、城北中学校(3次)、早稲田中学校と近いレベルでお考えでしたら、芝中学校(2次)となるでしょう。
2日に本郷中学校(2次)や桐朋中学校(2次)を受験される場合は、4日は城北中学校(3次)が望ましいでしょう。
4. 早稲田中学校の受験対策方法

全体として、基礎〜標準的な問題を取りこぼし無く、しっかりと得点していく事が肝心です。
計算間違い・見間違い・勘違いといったミスを極力減らしていく事が肝心です。
算数と、理科の計算問題で差がつきやすいですので、特に力を入れて対策する必要があります。
また、科目問わず、生徒様の広い視野を必要とする問題が出題されます。
ニュース・新聞などからジャンル問わず、新しい情報を入手し、興味を持つことが大事です。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学四年生
| 算数 |
塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。 塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくと良いでしょう。 早稲田中学校は、満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。 特に平面図形は大切な単元ですから、力を入れて学習して下さい。 また、計算力も必須です。早稲田中学校の問題は、時間との勝負です。 速く、正確に計算が出来るようにトレーニングをして下さい。 |
| 国語 |
カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにして下さい。 要旨を50~100字程度で書いていくのが、読解力向上に良いでしょう。 少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行いたい所です。 |
| 理科 |
生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。 暗記と共に、理解が伴うと、今後の学習に活きてきます。 |
| 社会 |
地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。 また場所毎の雨温図や産業を理解していくと良いでしょう。 |
(2)小学五年生
| 算数 |
引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにして下さい。 少し時間が経ってしまうと、出来なくなってしまう事も多いです。 1ヶ月以上触れていない単元は都度、解き直しを行なって下さい。 |
| 国語 |
物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。 生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を100字程度で書く練習をしましょう。 読書は継続的に行い、漢字・語彙も忘れずに行って下さい。 |
| 理科 |
物理・化学の計算問題が始まります。 非常に重要ですから、しっかり復習をし、難しい問題まで解けるようにして行きましょう。 地学分野は天体や地層といった理解を伴う単元が出てきます。 単なる暗記ではなく、仕組みを理解しましょう。 |
| 社会 |
歴史が始まります。歴史は早稲田中学校で重要な論点になります。 年号暗記をしながら、流れを掴めるようにして下さい。 |
(3)小学六年生(4月〜6月)
| 算数 |
前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。 過去問の問題をいくらか解ける時期になりますので、一度解いて頂くと宜しいかと思います。 |
| 国語 |
標準的な文章で、設問の解き方を確認しましょう。 類比・対比・例示などをしっかり意識して、設問に解けるようにして行きましょう。 |
| 理科 |
生物・地学の暗記を総復習しつつ、計算問題の力をつけて行きましょう。 計算問題が苦手な生徒様は特に力を入れて復習して下さい。 |
| 社会 |
公民が始まりますが、早稲田中学校でのウエイトはそう大きくありません。 公民の基本は押さえつつ、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。 |
(4)小学六年生(7月~8月)
| 算数 |
過去問を3〜5回分解いていきましょう。 また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。 秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。 過去問を解いて、大問1番の小問3つが得点できない場合、「プラスワン」(東京出版)で基本的な問題を総復習して下さい。 |
| 国語 |
過去問を始めていきましょう。 やはり3回分位は解いて、形式に慣れましょう。語彙・漢字については、この夏休みで固めていきましょう。 |
| 理科 |
過去問を3〜5回分解きましょう。 特に、計算問題に対応出来るか確認して下さい。 早稲田中学校の計算問題は、似た問題が出題される事があります。しっかり解けるようにしましょう。 |
| 社会 |
過去問を3回分行いましょう。 慣れる程度に行う位で十分です。 この夏休みは、全体の知識をしっかり総ざらいして下さい。 時事問題にも取り組み始めましょう。 |
(5)小学六年生(9月~11月)
| 算数 |
過去問中心になりますが、特に図形・速さの復習には力を入れましょう。 過去問の解き直しをしっかり行なって下さい。 大問1番の小問3つを取れる様にしましょう。 |
| 国語 |
過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なって下さい。 志望校別特訓・過去問の解き直しも行いましょう。 この時期でも、読書は継続して頂き、様々なジャンルに触れましょう。 |
| 理科 |
やはり過去問中心ですが、暗記の確認、計算問題の強化を引き続き行いましょう。 地学分野が疎かになりやすいですので、天体・地層を中心に理解出来ているか、確認して下さい。 |
| 社会 |
過去問を解きますが、それ程解かなくても良いでしょう。 過去の時事問題は、ほぼ出ません。今までの知識や、時事問題の学習に力を注ぎましょう。 ニュース・新聞に触れる様にして下さい。 |
(6)小学六年生(12月~1月)
| 算数 |
過去問・志望校別特訓の解き直し、図形・速さを含めた全般的な定着を行いましょう。 この時期も、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。 単元問わず、基本~標準的な問題を解き直ししましょう。 |
| 国語 |
時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。 漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。 |
| 理科 |
過去問を遡りつつ、志望校別特訓・過去問での解き直しを行なって下さい。 とにかく計算問題で差がつかないように、繰り返し反復して下さい。 物理・化学だけ過去問を遡るのも効果的です。 |
| 社会 |
歴史・時事問題を中心に復習をしつつ、統計対策です。 「日本のすがた」の最新版を使用して、多くのデータに関する知識を蓄えましょう。 |
②早稲田中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
早稲田中学校は、問題量の割に、時間が少ない科目が多いため、速く、正確に解く事が重要になります。
そのため、しっかりと時間を測り、ケアレスミスなく得点できるか、が鍵となります。
特に、算数の大問1番で、しっかり小問3問を正解出来るか、ここが最も大切な点になってきます。
算数と理科の計算問題に力を入れて、取り組んで下さい。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と理科については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。
回数をこなしたいですし、似た問題が出る事もあります。
一方、国語と社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。
この2科目は、出題形式が特殊なわけでは無いですので、回数もそれ程こなさなくて大丈夫です。
(3)何年分を何周解けばよいか
| 算数 |
図形・速さ・場合の数など、よく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。 従って、最低10回分、出来れば20回分解いておきたい所です。 まずは時間を測って解き、その後、しっかりと3周は解き直しをしましょう。 |
| 国語 |
文章題が2問出ますので、正確さを失わずに素早く読解する必要があります。 慣れるために、最低5回分、出来れば10回分程度解くと良いでしょう。 2周解き直しが出来れば良いと考えます。 |
| 理科 |
算数同様、計算問題に似た問題が出る事があります。 最低10回分、出来れば20回分解くと良いかと思います。 計算問題の解き直しを中心に3周行いましょう。 |
| 社会 |
素早く解く事は他科目と共通しております。 但し、時事問題を中心に、同じ問題はあまり出題されません。 過去問自体は5〜10回分程度で良いでしょう。 解き直しは2周程度で良いと思われます。 過去問を多く解く位でしたら、時事対策を行って下さい。 |
③保護者様に出来るサポート内容
早稲田中学校は、難関校ですから、しっかりとした勉強時間を確保しないといけません。
しかし、成績がうまく上がらない事もあるでしょう。
常日頃から保護者様が出来る事を列挙していきたいと思います。
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題が出来なくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。
ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
|
「少し前の単元に戻ってやってみようか。」 「ゆっくり基本からやり直してみよう。」
|
と生徒様を責めずに、ご対応して下さい。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)計算力対策
早稲田中学校は、計算力が鍵を握ります。
速く、正確に解くためには、計算力は欠かせません。毎日5問〜10問程度、四則演算の計算問題を解くと良いでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。
正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。
今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的な事でも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。
ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにして下さい。
例えば、
|
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」 「男女の格差社会ってどういう事なんだろうね?」
|
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。是非、取り組んで頂ければと思います。
まとめ
早稲田中学校は、基礎〜標準的な問題が多く出題されますので、取りこぼしの無い様に解いていく事が大変重要です。
普段の学習から、基礎を徹底する事を心掛けて、ミスの無いように訓練をして行きましょう。
ここでのミスは致命的になってしまいます。
一方、難しい問題も勿論出題されまして、特に算数の図形問題と理科の計算問題です。
よって、これらの問題を解けるようにしなければ、合格を手繰り寄せることは出来ません。
確実な計算力を身につけつつ、過去問での演習・解き直しを繰り返し行なって下さい。
とにかく、最重要は基礎固めであることは忘れないで下さい。
合格する生徒様は確実な基礎力を基に、難しい問題が解ける様になっております。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
早稲田中学・高等学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら