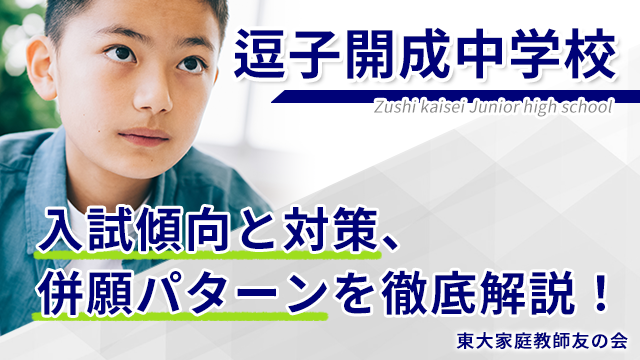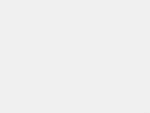1. 逗子開成中学校とは?

逗子開成中学校は、逗子海岸の近隣に位置し、その立地を活かした「海洋教育」や総合学習「人間学」などのユニークな教育が行われていることに加え、近年進学実績が大きく伸び、中学受験でも年々注目が高まっている学校の一つです。
ここでは、逗子開成中学校・高校と東京の開成中学校・高校との関係や、逗子開成中学校の魅力をお伝えします。
①開成中学校の分校として開校⁉意外な逗子開成中学校の歴史
「開成」という名称から、東京の西日暮里にある開成中学校・高等学校を連想される方も少ないことでしょう。
逗子開成中学校は、1903年に開成中学校の分校「第二開成中学校」として、その歴史をスタートしました。しかし、わずか6年後の1909年には独立し、逗子開成中学校に改名しました。
以降、両校は別の学校として歴史を刻んできています。ですが、逗子開成の校章には、開成の校章にも使われている「ペンと剣」が描かれており、わずかながらにこの歴史を感じることができます。
また、1904年に開成中学校、第二開成中学校の校長をしていた田邊新之助により創設された鎌倉女学校とは、現在も兄弟校として様々な交流があります。
②逗子開成の教育の柱の一つ「海洋教育」
逗子開成中学校では、逗子の海を利用した「海洋教育」を教育の一つの柱としています。
海洋教育特例校として、海について様々な視点で学び、考えていくだけではなく、中学1年生の後期では、グループでヨットを制作し、中学校の3年間、1年に2回ずつ帆走実習が行われます。
また、中学3年生の夏には、全員が逗子湾での遠泳にチャレンジします。
入学するときは泳げなかった生徒も、この遠泳を目指して練習を積み重ね、毎年全員が約1500メートルを泳ぎきり、精神力を鍛えるとともに、仲間との絆を深めていきます。
③生涯学び続けるための総合学習「人間学」
高校卒業後も自ら学び続ける力を身に着けるため、中学1年生から高校2年生まで、「人間学」と呼ばれる様々なプログラムに取り組みます。
教科の枠を超え、発達段階も考慮しながら、多角的に物事を見る視点や対話する力、自ら問いを立て、解決する力などを身に着けていきます。
様々な学びを通して自分自身を見つめることを通じて、人生の岐路に立った際に自ら考え、よりよい決断をするための力を養います。
2. 【最新】2025年度入試向け!逗子開成中学校の入試傾向

2025年度の入試は、帰国生入試が2024年12月26日に、一般入試が2025年の2月1、3、5日の3回にわたって行われます。
ここでは、各入試の概要や各科目の出題傾向、2024年度入試で「差がついた問題」や「特徴的だった問題」、それらの対策方法についてお伝えします。
①逗子開成中学校の入試概要
(1)帰国生入試
帰国生入試は、2024年12月26日に行われます。出願に際し、提出書類の一つとして作文が課されており、「海外生活で学んだこと」について学校指定の様式に直筆で600字で書く必要があります。
試験日当日の試験時科目は、国語・算数の2科目か、英語・算数の2つの受験パターンから選択することができます。
すべての科目が試験科目60分の100点満点で、合計200点満点の入試です。昨年度の帰国生入試の実質倍率は2.00倍でした。
(2)一般入試
一般入試は全日程、国語、算数、社会、理科の4科目です。国語・算数が試験時間各50分で各150点満点、社会・理科が試験時間40分で各100点満点の、合計500点満点です。
2024年度入試では、1日の1次入試が実質倍率2.04倍、3日の2次入試が4.77倍、5日の3次入試が4.24倍でした。
学校のホームページで公開されている募集要項には、各日程の入試の教科別の合格者最高点と合格者平均点、受験者平均点が掲載されていますので、過去問を解く際の参考にしてください。
②算数
算数の問題は例年、大問5題で構成されており、2024年度の1次入試では、
|
大問1:四則計算と逆算 大問2:応用的な小問集合の問題 大問3:植木算とつるかめ算 大問4:条件の整理 大問5:周期算
|
が出題されました。
大問2の応用小問では、単位の計算や仕事算、体積、整数の性質、割合と比、相当算、調べなど幅広い分野からの出題が見られました。
頻出の分野として注目したいのは、図形の問題です。点の移動や回転体の体積、相似比を利用したものなど、様々な出題パターンが見られます。特に、角度や長さ、面積に関する問題は毎年すべての回で出題されています。どの問題も、ひとひねり加えられており、応用力が重視されていることが伝わります。
速さに関する問題では、グラフとの融合問題として出題されることが多い傾向があります。
ここ数年は、2次入試、2次入試で周期算が、3次入試は約数や倍数の問題が出題されていますので、受験する日程に合わせて過去問にチャレンジしてみましょう。
問題のレベルとしては、標準からやや難しめだと言えるでしょう。応用問題でもしっかり得点できるようにしておくことが合格点をとるためには必要です。途中の考え方も書く問題が毎回1題出題されているので、問題を解く際には、途中式や考えた過程も分かるように書く癖をつけましょう。
ここでは、2024年度の2次入試の大問5の問題を取り上げて説明します。
|
一辺の長さが64センチ、各面と内部は白色の立方体があり、指示の通り、「切り開く作業」を繰り返し行います。
「切り開く作業」は、
<手順1> 立方体の高さを2等分するように切り込みを入れ、半分だけ上からキリ、さらに下の面に対して水平に切り込みを入れる
上半分を開く
切り開く前の立体の上の面が白色なら、切り口をすべて黒く塗り、切り開く前の立体の上の面が黒色なら、切り口に色は塗らない
というものです。
問1では「切り開く作業」を2回繰り返したときの下の面の面積を求めます。問題の図から、「切り開く作業」を1回行うと、下の面の面積が作業前の2倍になることがわかるでしょう。 したがって求める面積は、一辺の長さが64センチの正方形の面積の4倍となります。
問2では「切り開く作業」を3回繰り返した時の、立体の下の面の白い部分の面積と黒い部分の面積の比を最も簡単な整数の比で答えます。 問1より、下の面積の面積はもとの正方形の8個分になります。2回目の上の面の色は、問題に描かれている図からも白だと分かるので、3回目の作業によって、白い部分の面積が増えることになります。したがって、6:2=3:1だと分かります。
問3は、立体の高さが1センチになるまで「切り開く作業」を繰り返すとすると、何回作業を行う必要があるかと、「切り開く作業」を最後まで行ったとき、立体の下の面の白い部分の面積と黒い部分の面積の比をもっとも簡単な整数の比で答えます。
ただし、問3に関しては、答えだけではなく、考え方も書くように求められています。
「切り開く作業」を1回するごとに、図形の高さは半分になっていきます。したがって、高さが1センチになるのは作業を6回繰り返した時だとわかります。次に、下の面の白い部分と黒い部分の面積がそれぞれ正方形何個分にあたるかを考えます。
問1、2を参考にしながら、作業の回数と正方形の数、白の数と黒の数で表を作成すると、求める面積比を導くことができるでしょう。
式だけでなく、考えた過程が伝わるように書くと、答えまでたどり着けなかったとしても、部分点がもらえた可能性は高いです。
図形の高さが1センチになるのが、作業を6回繰り返した時だというところまではたどり着きたい問題です。
|
この問題を解くためには、一見複雑に見える「切り抜く作業」の条件を正確に理解し、規則性に気付くことが必要です。
このように、逗子開成中学校の入試問題では、図形と他の分野の内容を関連させたような問題も出題されるので、様々な演習問題に触れて、柔軟に問題を捉えられるように練習しましょう。
③国語
国語の問題は例年、大問3題で構成されています。
2024年度の一次入試では、
|
大問1:漢字の読み書き・ことわざ 大問2:随筆(ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ著/鎌田陽司『懐かしい未来ーラダックから学ぶ』より、約2300字) 大問3:小説(司馬遼太郎『関ケ原』約2500字)
|
という構成でした。
大問1の知識問題では、毎年全ての回で、漢字の読み書きと慣用句・ことわざの問題が出題されています。
大問2・3の読解問題の出典は、中学入試でよく見る作者のものもあれば、海外の作品の翻訳本、50年以上前の作品や歴史ものなど、幅広いジャンルが見られます。
文章量は、大問2・3合計で3500字~5000字程度と、比較的短い点が特徴です。
主題や要旨、内容理解の問題に関しては必ず出ているほか、ここ数年、2次入試では文脈や段落の構成の問題が出題されています。
2024年度入試で受験生に差がついた問題として、1次入試の大問2の問四について説明します。
|
課題文は、インドの伝統的な文化が残っていたインドのラダックの町に魅了されていた筆者が、近代的な西洋文化の流入により変化していく町の様子を見て考えたことを綴ったものです。
傍線部の2段落前には、「ラダックの人々は伝統的に、身近で得られる資源を驚くような知恵と技術によって利用し、快適でうらやましいほど安全な生活を実現していた」とあります。
それが、傍線部のあとの部分で、開発によって、「経済への依存や伝統文化の拒否、環境の劣化」につながったと書かれています。
以上を、問いの答えに合うようにまとめていきます。 |
この問題は、傍線部の前と後、両方の要素を解答に盛り込まなければならないことに加えて、字数の制限がなかったことから、答えにくさを感じた受験生が多かったのではないでしょうか。
逗子開成中学校の国語の問題には、記号選択式の問題だけではなく、書き抜きや記述問題など、さまざまなパターンが見られます。
特に記述問題は、字数制限があるものとないもの、どちらも出題される可能性があるため、両方に対する対策が必要です。
文章の細部まで的確に読み取れるかどうかを試されるこうした問題への準備としては、3000字程度のやや短めの文章で主題を読み取り、自分の言葉でまとめる練習をしてみましょう。
また、様々な課題文に対応するため、中学入試でよく取り上げられる筆者や作品を読むことももちろん大切ですが、日頃から幅広い話題や種類の文章に触れておくことが効果的でしょう。
④理科
理科は大問4題構成で、年度や入試回によって出題分野には異なるものの、生物・物理・化学・地学のそれぞれからおおむねバランスよく出題されています。
2024年度の1次入試は、
|
大問1(地学):流れる水のはたらき 大問2(生物):ヒトの血液循環 大問3(化学):水溶液の性質(ろ過、中和) 大問4(物理):球の運動
|
という構成でした。
生物は、森林のでき方やジャガイモの育ち方など、あまり他校では見られないような、特徴的な問題も見られます。
人体に関しては、3回の入試のうち、必ずいずれかの回では取り上げられると考えてようでしょう。ですので、しっかりと準備しておくことをおすすめします。
化学に関しては、食塩水の濃度や中和反応など、比較的中学入試で頻出の内容が出題されます。特に水溶液の性質については毎年出題されています。
物理は、力学分野からの出題が多いですが、幅広く様々な分野から出題されています。
地学に関しては、地層や岩石、流れる水のはたらき、火山や地震などに関連した問題がよく出題されている傾向があります。
回答のしかたも、選択肢を記号で選択する問題と用語や計算結果を書く問題だけではなく、1~2行程度の短めの記述問題や作図など、様々なパターンがあります。
特に化学と物理では計算問題が出題されることが多いので、十分な対策が必要です。
ここでは、2024年度の問題から、2次入試の大問3、日食や月食についての問題について説明します。
|
問1は、日食と月食のしくみについて述べた述べた文の空欄を補充する問題です。基本的な問題だったと言えるでしょう。 問2は、日本のある地点で日食を観察することができたときの地球にできた影のようすを表したものとして、最も適切なものを選びます。
この問題を解くためには、算数的な思考力が必要です。自分の視点と月・太陽の模型の中心を通る直線と、月と太陽の模型の接線とでできる三角形の相似を利用して解きます。
問5は、日本で日食が起きる回数は年間平均2.2回、月食が起きる回数の平均は年間1.4回とされており、日食や月食が毎月のように起こらないのはなぜか説明する、という問題でした。
問6は、地上からは常に静止しているように見える人工衛星が、赤道上空を高度を一定に保ち、秒速3kmで飛行しています。地球が半径6400kmの完全な球で、自転周期を24時間とすると、この人工衛星の高度は何kmになるか、円周率を3として求める問題です。
秒速3Kmで飛行している静止衛星は、1日に3×60×60×24=259200Km飛行するので、その公転軌道の半径は、259200÷3÷2=43200Kmです。したがって求める静止衛星の高度は、43200-6400=36800Kmと分かります。
|
一見難しそうに見えますが、問題の誘導にしっかり乗り、丁寧に計算することができれば、決して解けない問題ではなかったでしょう。
しかしながら、問4以降の問題がどれだけ解けたかが受験生に差をつけたと言えそうです。
このような問題でしっかり合格点をとるためには、基礎を固めることはもちろん、応用的な問題を扱った問題集などに挑戦してみると良いでしょう。
⑤社会
逗子開成中学校の社会の問題は、地理・歴史・公民の各分野の総合問題を大問1つずつ出題する形式と、3つの分野の総合問題を1題出題する形式の2つのパターンがあります。例えば、2024年度の1次入試は、
|
大問1:自然災害を題材にした地理の問題 大問2:災害年表を題材にした歴史の問題 大問3:災害対策を題材にした公民の問題
|
でした。
しかし2023年の1次入試は、沖縄を題材にした総合問題でした。前者の出題形式の場合は、他の中学校の問題でもよく見かけるパターンですが、後者はあまり出会わないパターンなので、戸惑う受験生も多いかもしれません。だからこそ、過去問題を利用してこのパターンの出題形式に慣れておきましょう。
回答の形式も、選択肢の中から記号を選択して答える問題、ならびかえ、用語を答える問題、記述問題などバラエティ豊かです。
用語の記入には漢字指定のものもあるため、知識は漢字で正確に覚えるようにしましょう。記述問題には字数制限はなく、長めの問題も見られます。
地理・歴史・公民ともに、幅広い分野から出題されています。地理は、日本の国土や自然、気候、農林水産業、工業に関しては、毎年、ほぼすべての回で出題されています。
また1次入試ではここ数年、資源や交通、通信、貿易の問題が連続で出題されているので、2025年度も注意が必要でしょう。
歴史については、テーマ史ではなく、総合的な問題として幅広い時代から出題されています。どの時代も、まんべんなく学習しておくことが大切です。
公民分野は、憲法や三権分立についての問題が頻出です。
2024年度の入試で特徴的だった問題として、1次入試の大問3の問6を取り上げます。
課題文の「地域の住民通しで協力して助け合う「共助」、政府や地方公共団体による被災者への援助や支援である「公助」も極めて重要です」という部分に関連して、避難所での生活の「困りごと」を描いたイラストを見ながら答える問題でした。
|
【イラストA】については、描かれている避難所内の問題点を一つ上げ、わかりやすく説明したうえで、自分がこの避難所に避難した場合に、問題解決にためにどのような行動ができるか、「共助」の視点から述べる問題でした。
イラストには、避難してきた外国人が、避難所の日本語の案内が理解できずに困っている様子が描かれています。身振りや手ぶりを用いる、絵を描いて示す、スマートフォンの翻訳機能を使用する、通訳ができる人を探すなどの解決策が考えられますね。
【イラストB】に関しても、イラスト内に描かれている問題点を一つ上げて説明したうえで、今度は自分が避難所を運営する立場であったら、問題の解決のためにどのような行動ができるかを「公助」の視点から述べる問題です。
イラストには、避難してきた赤ちゃん連れの親子が、赤ちゃんの夜泣きやおむつの交換に苦労している様子が描かれています。
避難所の多くは学校の体育館や公民館などで、仕切りがない場所が多いため、子ども連れの家族は周囲への配慮をしなければいけません。
|
海に近く、日頃から地震を中心に防災対策に力を入れている逗子開成中学校ならではの問題だったと言えるでしょう。
この問題を解くためには、まず、イラストがどのような問題を表しているのかを簡潔に説明することと、それぞれの立場(視点)からの解決策を述べることができているかがポイントになります。
2つのパターン、どちらにも対応できるよう、両方の過去問題に必ず取り組んでおきましょう。
3. 逗子開成中学校を受験する場合の併願パターン

逗子開成中学校の一般入試は、2月1日・3日・5日と奇数日に行われます。
全体的な傾向としては、逗子開成が第一志望の生徒様は、すべての回に出願している傾向がある点、鎌倉学園と併願するケースが多い点が特徴のように感じます。
逗子開成と鎌倉学園は、距離的には近いために比較されやすいものの、校風が異なるため、どちらの学校を志望する生徒様も、実際に学校を見てみることをお勧めします。
逗子開成中学校の併願先としてよく名前を見かける学校としては、共学ですが校風が似ている感じがある、という理由から神奈川大学附属中学校が挙げられます。また、山手学院中学校も受験している生徒様が多い印象です。
近年、全体的に逗子開成中学校を受験する生徒の受験者層が高くなっていることから、併願校もそれに従って変化しているように感じますし、1日や2日などの早い段階で合格を掴んでおくことが大切でしょう。
ここでは、1月入試、2月1日(午後)、2日、3日、4日・5日に分けて、ライターがこれまでに出会った生徒様の情報などももとに、併願先として考えられる学校を紹介します。
①1月入試
1月に入試を行う学校は千葉県・埼玉県の学校が中心となるため、湘南地区の生徒様にとっては通学に時間を要する学校が多いことでしょう。
ですので、あまり受験していないように思います。逗子開成中学校が第一志望の場合は、あくまでも1月入試は前哨戦と考えるのがよさそうです。
1月入試の併願校としては、
・栄東中学校
・開智中学校
などが挙げられます。
②2月1日(午後)
1日は1次入試が行われます。
午前中に1次入試を受験した後、午後入試で、
・山手学院中学校(特待)
・神奈川大学附属中学校
の名前がよく挙げられていました。
③2月2日
この日に
・栄光学園中学校
を受験する生徒様も多いようです。
そのほか、
・鎌倉学園中学校
・山手学院中学校
都内に住んでいる生徒様で、通いやすさも重視して
・法政大学第二中学校
を受験したという声を聞きます。
④2月3日
3日は2次入試が行われるため、そちらに出願している生徒様が多いようです。 ただ、
・浅野中学校
を受験している生徒もそれなりにいました。
3次入試は、上位校を狙っていた生徒が流れて来る可能性がより高くなるので、逗子開成中学が第一志望の生徒様は、できれば2次入試までに合格を掴んでおきたいところです。
そのほかには、
・青山学院横浜英和中学校
・山手学院中学校
などの名前も挙がっていました。
⑤2月4日・5日
4日以降の受験校としては、
・法政大学第二中学校
・聖光学院中学校
・サレジオ学院中学校
・東京都市大学付属中学校
がよく挙げられます。
5日は3次入試が行われるため、そちらに出願している生徒様が多い印象ですが、それ以外の学校では
・本郷中学校
・立教池袋中学校
などが挙げられます。
4. 逗子開成中学校の受験対策方法

ここでは、逗子開成中学校の受験に向けて、
「いつ、どんなことをしていったらいいのか?」
「過去問はいつ頃、どのように取り組むのがよいのか?」
「保護者様がご家庭でできるサポートとは?」
といった、具体的な受験対策に関する疑問について、お伝えしていきます。
①時期別・教科別対策方法
ここでは、小学校4年生から受験直前までの、時期別・教科別の受験対策方法をご紹介します。
(1)小学4年生
この時期は、中学受験を多少意識していても、受験をするか決めきれていなかったり、学校について情報収集している段階のご家庭も多いことでしょう。
ですが、学校の学習も少しずつ難しくなっていき、クラス内での学力差が顕著になってくる時期でもあるので、受験する/しないや志望校にかからわず、自律した学習習慣を身に着けさせる時期です。
学校や塾の宿題などのやるべきことをしっかりこなす時間を確保するとともに、興味関心を広げられるよう、様々な分野の図鑑や百科事典などをみたり、博物館や科学館などに行ってみましょう。
特に逗子開成中学校でも、入学後も土曜講習などを通じて、そうした経験を重視しているように感じます。
(2)小学5年生
本格的に中学受験を意識して学習する生徒様の増える5年生。
一方で、気持ちのコントロールが難しい時期でもあります。この1年を頑張りきれるかどうかが、最終的に中学受験の結果を左右するのではないでしょうか。
5年生では、小学校の学習範囲の基礎・基本を固めるとともに、育成に時間のかかる読解力や批判的思考力などを意識した問題など、直前期には取り組むのが難しいようなものをやっておくことがおすすめです。
算数:基礎計算のスピードと正確さを意識しましょう。中学受験に頻出のつるかめ算や旅人算などは、5年生のうちに使いこなせるようにしておきましょう。
国語:語彙の学習と読解力を強化したいのがこの1年間。大問1で毎回必ずことわざが出題されていることから、小学生用のことわざ辞典などを用意することをお勧めします。
わからない言葉に出会ったら、すぐに調べる習慣をつけましょう。
はじめは穴埋めや一問一答形式の問題で、その言葉自体を覚えているかどうかを確認し、その段階がある程度進んだら、今度は文章の中での使い方を確認するなど、自分の語彙として運用する練習をしていくとよいです。
理科・社会:必要な知識を入れる段階の理科や社会。塾や学校で習ったことを丁寧に復習するとともに、資料集などの細かいところにも繰り返し目を通して、知識の取りこぼしがないようにしましょう。
(3)小学6年生(4月~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
算数:時間を意識して解けるように、このころから準備を始めていきましょう。また、標準レベルの問題に関しては、この夏を迎えるまでにある程度解けるように、基礎固めを重視しましょう。
国語:このころまでに、漢検5級範囲までの漢字は確実に読み書きできるようにしましょう。また、実際の出題形式を意識して、3000字程度の文章を読み、要旨を掴む練習をしておきましょう。
理科:苦手分野をつくらないよう、幅広く基礎固めに取り組んでいきたい時期です。用語を答える問題など、標準レベルの問題はしっかり解けるようにしましょう。
社会:理科と同様に、用語を答える問題などは確実に解けるようにしておきたいです。また、時事的な問題にも対応できるよう、新聞やニュース番組にも目を向けるようにしましょう。
(4)小学6年生(7月~8月)
「夏は受験の天王山」と言われるほどのこの季節。体調管理と生活リズムを整えることに注意しながら過ごしたいですね。
算数:頻出の図形の問題に力を入れて、様々なパターンの問題にチャレンジしましょう。
国語:読解問題の練習に取り組んでいきましょう。特に選択式の問題については、正解、不正解の根拠も明確に説明できるように、本文に線を引いたり、印をつけながら読むことを勧めます。
理科:実験や観察をもとにした問題の出題に対応できるよう、実験の手順や器具の使い方などについて、普段より時間がとれる夏休みに確認しておいてください。
社会:出題の約40%を占める歴史に力を入れていきましょう。古代から現代までの流れを掴むとともに、用語は漢字で正確に書けるようにしましょう。
また、理科・社会に共通して言えることですが、逗子開成では環境問題や防災に関連する事項について、様々な取り組みを行っているので、学校のホームページやfacebookなども参考にどのようなことをしているのか、現在どんな課題があるのかなどを調べておくことをお勧めします。
(5)小学6年生(9~11月)
志望校合格に向け何をしなければならないのか、ゴールから逆算して考えるのがこの時期です。秋以降は、過去問にもチャレンジしましょう。
算数:過去問に挑戦し、できなかった問題は徹底的に復習をしましょう。記述問題も意識して、考える課程もしっかり書きましょう。
国語:記述問題や空欄補充の問題を意識して練習しましょう。特に、字数制限のない記述については模範解答も参考にしつつ、精度を高めていきましょう。
理科:手間のかかる問題が多いので、過去問など解く際は、時間をかけてでも解く問題とそうでない問題のより分けができるようにしていきましょう。
社会:過去問を利用して、オーソドックスな出題パターンと総合的な出題パターンのどちらにも対応できるようにしましょう。
(6)小学6年生(12~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、新しいことをしたり、覚えたりというよりは、どの科目もこれまでしてきたことを振り返り、抜け漏れているところがないかどうか確認し、見つけ次第復習する期間です。
②逗子開成中学校の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
過去問を解く目的は大きく2つあると考えています。1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。つまり、自分の弱点を知るために過去問を利用するのです。
間違えたところは、決してそのままにはせず、解説をしっかり読んで何を間違えたのかを整理し、教科書や参考書を読み直したり、似たような問題を練習して、再度その問題に挑戦してみましょう。
過去問を解く目的の2つ目は、時間的な感覚を掴むためです。
入試は、決められた時間内に問題を最後までやりきり、かつ合格点をとらなくてはいけません。
過去問に取り組む時には、時間の感覚を身につけるために、時間通りに問題を解くだけでなく、できれば入試本番と同じスケジュールで問題を解いてみることをお勧めします。
また、逗子開成中学校・高等学校のYouTubeチャンネルでは、過去問の解説動画を配信していますので、そちらも合わせてご覧になるとよいかと思います。
(2)過去問はいつから解き始めればよいか
基本的には、過去問に挑戦するのは、受験校が固まり、間違えた分野の問題に取り組む時間的・精神的な余裕がある、6年生の11月~12月ごろをお勧めしています。
実際に問題を解いてみることで、応用的な問題の対策や基礎基本の抜け漏れを補う学習をどのようにしていくか、計画を立てていきましょう。
また、過去問を解いて解けなかった問題は、まだ基礎が不十分なところと考え、直前期に向けてしっかり克服してきましょう。
併願校として受験する場合でも、試験日直前は過去問が売り切れてしまっていて手に入らない、ということもあり得ますので、冊子として持っておきたい場合には、余裕を持って準備しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばよい?
逗子開成中学校を受験する場合、基本的には3年分程度、全ての回の問題を解いておくとよいでしょう。
また社会に関しては、大問3題の出題形式を最低3回分、大問1題の出題形式を最低3回分解いて、どちらのパターンで出題されても対応できるようにしておきたいです。
それ以上前の問題についても、例えば算数の図形問題など、頻出の分野に関しては、対応力をつけたり、演習量を増やして確実に点数に繋げていくためにも、5年分程度チャレンジしてみてもよいでしょう。
ただし、年数が経過しているものについては、学習指導要領が改定され、出題範囲が今と異なることがあるので注意が必要です。
過去問を解く回数については、一周すれば十分だと考えています。
一回で解けた問題は、ケアレスミスなどがない限り、何度やっても同じように解けるからです。もうすでに解けた問題にさらに時間を使うよりも、今できないことをできるようにすることのほうが、合格への近道になります。
過去問は一周で構いませんが、一度解いて間違えた問題は、解説をよく読んで間違えた理由を確認し、解けるまで何度でもチャレンジしましょう。
③保護者様にできるサポート内容
(1)親子で入学後にしたいことを語る
生徒様はもちろん、保護者様も学校に関わる機会が多くある逗子開成。
例えば、父親懇親会や母親による合唱団などが存在し、活発に活動を行っている他、文化祭や体育祭以外にも、遠泳やボートの帆走、マラソン大会など、様々な場面で生徒様の活躍を保護者の方が見ることができる機会があります。
生徒様ご自身が入学後にしたいことを明確にしてもらうことはもちろんですが、保護者様も入学後、どのように学校と関わりたいかをお話しされると、生徒様のやる気の後押しにもなるのではないでしょうか
ただ、生徒様のプレッシャーになりすぎないようには注意が必要ですね。
(2)生徒様に合った学習環境、リラックスできる環境を整える
どのような環境で学習するのが適しているのかは、生徒様によって違います。
整理整頓された机の上で静かに取り組みたい生徒様もいれば、音楽を聴いたり、ねそべったりしながらのほうが、学習がはかどるという生徒様もいます。
集中して学習に取り組める環境が保護者様と生徒様で違うということもよくあることなのです。
ですので、生徒様がどのような環境なら心地よく学習に取り組めるのかを見極め、それに合った環境を準備できるようにしましょう。
また、生徒様が気持ちをリセットしたりほっと安心できるような、一人になれる空間や時間を作るように手助けすることも重要なサポートの一つです。
最後に
逗子開成中学校は、神奈川で最も長い歴史を持つ私立の男子校で、逗子湾に近接する立地を活かした「海洋教育」や、教科横断的・総合的なカリキュラムで生涯にわたって学習する力を育てる「人間学」、普段の学習とは一歩離れて、ユニークな内容を学べる土曜講習など、さまざまな独自の学習プログラムが行われています。
また近年、大学入試実績が大きく伸びていることからも、人気が高まっている学校の一つです。
一般入試は2月の1,3,5日の3回行われます。問題の難易度としては、標準レベルから応用的な内容まで、幅広い分野から出題される点が特徴です。
標準レベルの問題はミスなく確実にこなし、応用的な内容でどれだけ得点できるかが合格に繋がるといえるでしょう。
単に知識が求められるだけではなく、中学受験レベルの知識を複合的に組み合わせて柔軟に考える力が求められていると言えます。
逗子開成中学校が第一志望の場合、同校の他の入試回を受験する生徒様が多い印象です。
併願校としては、鎌倉学園中学校や神奈川大学附属中学校、山手学院中学校などに出願するケースが多く見られます。
入学後も保護者様が学校で生徒様の様子を間近に見られる逗子開成中学校だからこそ、親子で一緒に入学後のイメージを膨らませたりすることも、生徒様の学習へのモチベーションを保つための一助となることでしょう。
合格に向け、しっかり準備を行い、素敵な春を迎えられるようお祈りしております。
【参考文献】
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら