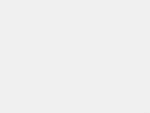1.お茶の水女子大学附属中学校とは
お茶の水女子大学附属中学校は、東京都文京区にある男女共学の国立中学校で、最寄り駅は丸の内線「茗荷谷駅」です。
教育方針は「自主自立の精神を持ち、広い視野で行動する生徒の育成」です。最終的には、変化する社会の中で主体的に生き、自分らしく生きる力を養うことを目指しています。
カリキュラムは、国語・数学・理科・社会・英語・音楽・美術・保健体育・技術家庭に加え、道徳・特別活動・自主研究・「お茶の水タイム」(総合学習)が組み込まれ、総授業時間の約1/6を占めています。
2.お茶の水女子大学附属中学校の入試の出題傾向と受験対策
お茶の水女子大学附属中学校の入試は、検査I(国語)、検査II(算数)、検査III(理科・社会)の3つがあります。
記述式の問題が多く、特に文章力が求められる傾向があります。
以下では、入試の特徴と対策方法を解説します。
①検査Ⅰ:国語
(1)出題傾向
近年、大問1でリスニング問題が出題される傾向があります。複数名の会話から要点をつかみ、内容を正しく理解したうえで、適切な選択肢を選ぶ問題が約6問出題されます。
また、問3以降は内容の要約を記述する問題も含まれ、聞き取った情報を整理し、的確に表現する力が求められます。
(2)対策のポイント
リスニング問題を出題する中学校は少なく、対策が不十分になりがちです。そのため、日常的にニュースやラジオを聴き、保護者様と一緒に内容を確認する習慣をつけることが大切です。
また、リスニング問題は決められた時間内で解く必要があり、時間配分が難しくなります。普段から制限時間を意識しながら問題を解く練習をすることで、本番でも焦らず対応できるようになります。
②検査Ⅱ:算数
(1)出題傾向
前半に計算問題を出題し後半に文章題を出題するオーソドックスな形式ですが、問題文をしっかり読む必要があり、時間配分が難しいのが特徴です。
問題数が少ない分、一問あたりの配点が高く、ケアレスミスが致命的になります。
(2)対策のポイント
前半の計算問題は素早く正確に解き、後半の文章題に時間を残す意識を持ちましょう。
特に文章題では、論理的思考力と説明力が求められ、答えだけでなく途中式や解答のプロセスを明確に示す必要があります。
対策として、日本語力を鍛えることが効果的です。本を読む習慣をつけ、伝えたいことを的確に表現する力を身につけることで、算数における記述力も向上します。
③検査Ⅲ:理科
(1)出題傾向
記述問題が大半を占め、選択肢問題は少ない傾向があります。特に最終問題では100~150字の記述が求められます。短い記述問題の配点も高いため、論理的思考力と説明力が重視されています。
(2)対策のポイント
与えられた情報をもとに理由を考え、100~150字で説明する高度な記述力が求められます。特に最終問題は時間配分が難しく、多くの受験生が苦戦するポイントです。
記述問題では、文章力・思考力・想像力の3つが必要です。与えられた情報を分析し、観察や実験の結果から論理的に説明する力が求められます。
対策としては、読書に加え、アルゴカードや推理小説を活用し、情報を整理して考える力を鍛えることが大切です。
④検査Ⅲ:社会
(1)出題傾向
社会は問題数が非常に多く、試験時間内に解き切るのが難しい傾向があります。選択肢問題が中心ですが、読解量が多く、ペース配分が重要です。
特に、最後に出題される記述問題が難所となります。
(2)対策ポイント
記述問題では、問題文にヒントや採点基準が示されていることが特徴です。与えられた条件に沿って論理的に回答を組み立てる力が求められます。
対策としては、他の教科でも挙げたように、読書を通じて文章力を鍛え、要点を的確にまとめる練習をすることが大切です。
⑤出題傾向の似ている学校
お茶の水女子大附中学校は記述問題が比較的多く、全科目に出題されています。こうした特徴は最難関校に多く見られます。
中でも、麻布中学校はほぼ記述式の問題で構成されており、出題傾向が似ています。
3.お茶の水女子大学附属中学校に受かるには:中学受験のポイント
お茶の水女子大附中学校の入試に向けて、おすすめの併願校や、時期別の学習計画、過去問の効果的な使い方についてご紹介いたします。
①おすすめの併願校
同じ偏差値帯の併願校として、明治学院中学校をおすすめします。2月4日実施のため、2月3日にお茶の水女子大附属中学校を受験した翌日に、落ち着いた気持ちで臨める点が魅力です。
また、1月受験で試験の雰囲気に慣れておくことも重要です。埼玉県の栄東中学校を受験することで、本番に向けた良い準備になります。
②時期別の受験対策
学習時間を決めつつ、自由時間もしっかり確保することが大切です。こうすることで、生徒様のやる気を保ち、メリハリをつけながら学習に取り組むことができます。
※以下の学習時間は、筆者の経験に基づく目安です。
(1)5年生
学習習慣を定着させましょう。目安として1日あたり3~4時間程度の学習時間を確保できるとよいでしょう。
(2)6年生(4月~8月)
5時間以上の学習時間を確保しましょう。また、受験校についても本格的に絞り込みをしていくとよいでしょう。夏休みに突入したら、1日に9時間程度は勉強するようにしましょう。
(3)6年生(9月~12月)
この時期から週に1~2本程度、過去問に取り組むようにしましょう。過去問は新しいものから取り組み、どの問題を間違えたのか整理するようにしましょう。過去問の効果的な使い方は以下で詳しく解説いたします。
③過去問の効果的な使い方
ここでは過去問の効果的な使い方を解説いたします。
過去問に取り組む目的は大きく分けて3つあります。
(1)問題の難易度や傾向をつかむ
過去問を解いた後は必ず復習し、解けなかった問題や、どのような問題が出ていたかをしっかり確認するようにしましょう。直近5年分の過去問は、試験直前の1か月前から解くのがおすすめです。
(2)試験の時間配分に慣れる
試験では時間内に解ききる力も重要です。過去問を解く際は、本番と同じスケジュールで取り組むようにしましょう。
(3)予備知識や基礎知識の定着を確認する
過去問に取り組むことで、自分の知識がどれだけ定着しているかを確認できます。間違えた問題は、関連するテキストや資料で補強し、類似問題にも挑戦しましょう。これを繰り返すことで、試験本番で活用できる確かな知識が身につきます。
④保護者様ができるサポート
(1)勉強が嫌いにならない工夫をする
「テストで良い点を取れたら外食に行こう」など、成果に応じたご褒美を用意するのも一つの方法です。楽しみながら勉強を続けられる環境を作りましょう。
(2)点数が悪くても叱らず、学習方法を見直す
叱るのではなく、生徒様に合った学習方法を探り、より効果的な学び方に調整しましょう。
(3)他の子と比較しない
受験は競争ですが、大切なのは他人との比較ではなく、自分の成長です。模試の結果が振るわなくても、本番で力を発揮できるよう、学習環境を整えることを優先しましょう。
まとめ
お茶の水女子大学附属中学校の入試は、検査I(国語)、検査II(算数)、検査III(理科・社会)の3つに分かれています。
記述式の問題が多く、特に文章力が求められるため、日頃から読書を習慣にし、要点を的確にまとめる練習をするとよいでしょう。
また、同レベルの学校と比べて出題数が多いため、問題の取捨選択や解く順番を意識することも重要です。本番で効率よく解答できるよう、過去問演習を通じて戦略を立てておきましょう。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら