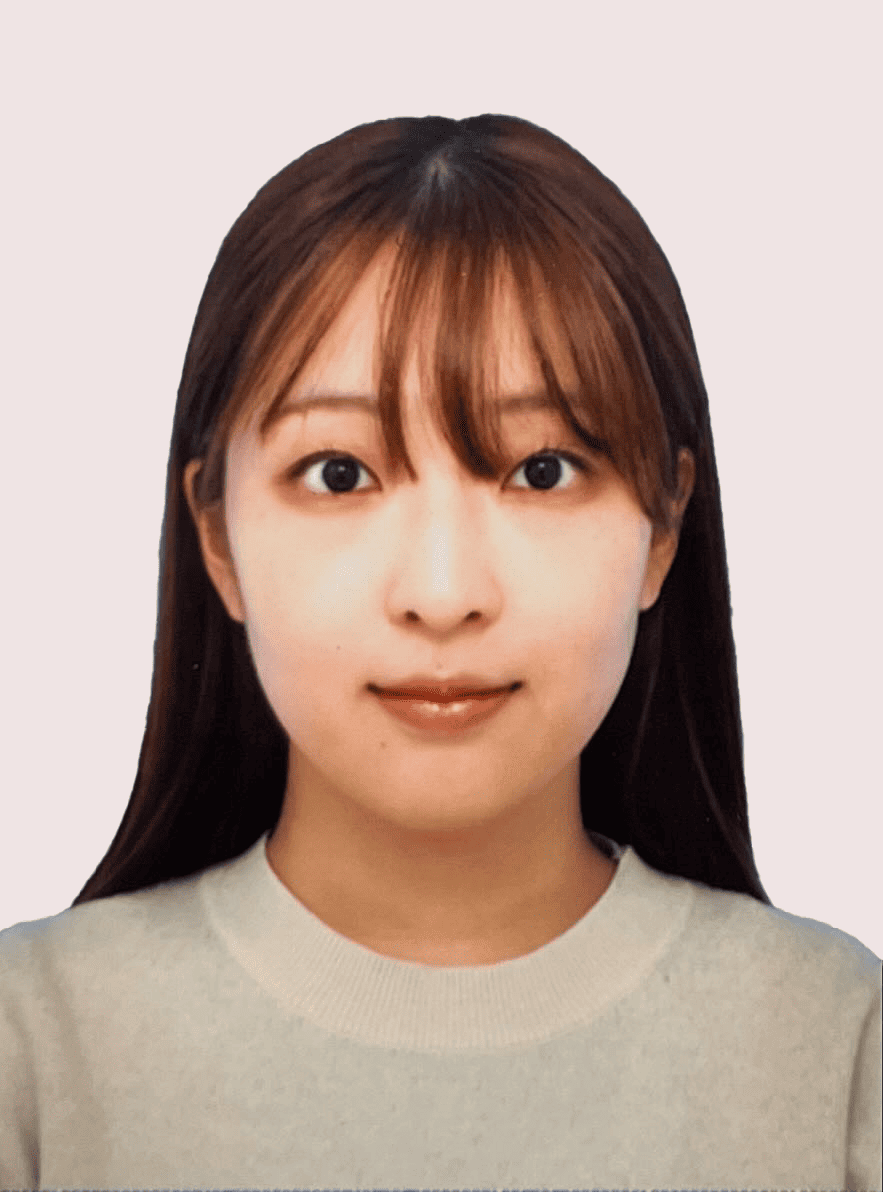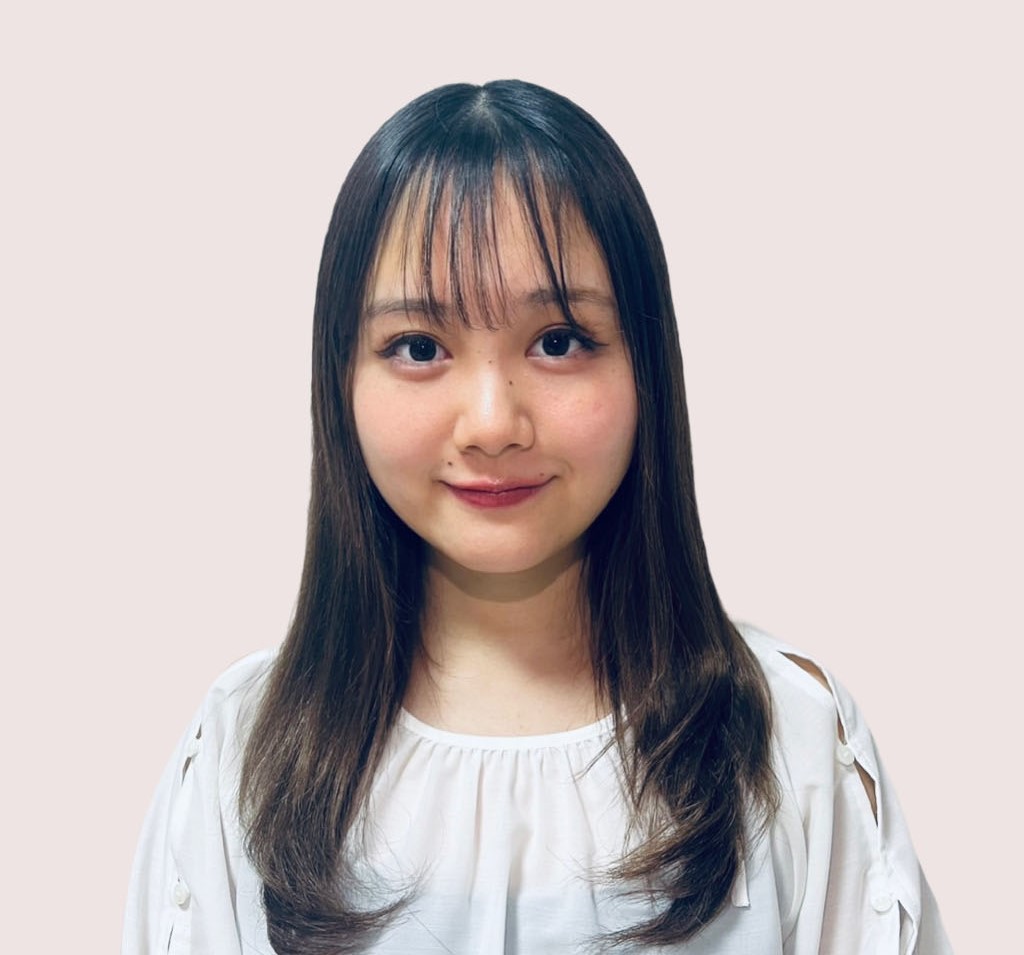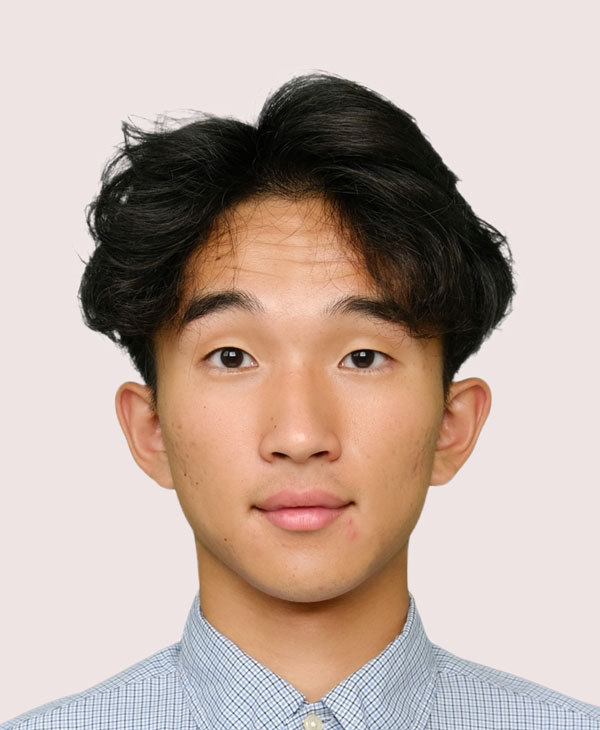進学校で「落ちこぼれた」「ついていけない」と感じる5つの原因
せっかく入学した進学校でも、「受験でがんばったからこそ、授業についていけなくなってしまう」ということがあります。
ここでは、進学校だからこそ落ちこぼれやすくなる原因を、5つご紹介します。
①受験で燃え尽きてしまう
「〇〇学校に受かりたい」という一心で、なんとか受験を乗り切った……という生徒様の場合、解放感で燃え尽きてしまうことがあります。
しかし、進学校は入学してからが大変です。授業の進度は早く、周囲の環境も変わります。勉強への意欲が戻らないと、どんどんと授業についていけなくなってしまいます。
②授業のスピード・難易度が急激に上がる
進学校の授業進度はとても早いです。先生方も生徒の知識を前提に授業を設計するため、「このくらいはわかっているよね」と細部を説明しないことも多いです。
さらに、難易度も上がります。「高校1年生から大学入試の問題を扱う」、「大学のゼミレベルの課題を出す」こともあります。その結果、「気を抜くと『わからない』が積み重なる」という状態に陥ってしまいます。
③授業スタイルや学習法が生徒に合っていない
進学校は、特色のある授業を行うことが多いです。その分、授業スタイルが合わないと感じることもあります。
例えば、私が卒業した学校では、数学の授業は公式の証明とディスカッションにたっぷり時間を使い、基礎は自学するスタイルでした。大学に入ってからこの授業の豊かさを痛感したのですが、当時は理解できず、多くの同級生も混乱していました。
このように、「良い授業であっても、内容がピンとこない」ということはあります。
④環境の変化によるストレスや不安
進学校の場合、周囲の環境が大きく変化することが考えられます。クラスメイトや部活の同期と自分を比較し、苦しい思いをすることもあるでしょう。
また、学校が家から遠い場合は、通学により身体的な疲労が生じたり、十分な睡眠が取れなかったりすることもあります。
こういった、ストレスの積み重ねからモチベーションが低下する場合もあります。
⑤人間関係のストレス
厳しい受験を突破してきた学生が集う進学校は、「競争意識」を良しとする校風の場合が多いです。
よく言えば芯が強くて真面目な空気、悪く言えば少しピリッとした空気が教室にあります。
生徒様が学校の校風と合わない場合、人間関係においてストレスを感じることが予想されます。その結果、勉強に集中しづらくなってしまいます。
進学校で落ちこぼれてしまうとどうなる?
進学校で落ちこぼれることには、短期的・長期的にさまざまな影響があると考えられます。
ここでは、進学校で落ちこぼれるとどうなってしまうのかを3つご紹介します。
①自信をなくし、学習意欲が低下する
進学校に合格された生徒様は、本来は学ぶことが好きで、これまで良い成績をキープしてきたのではないかと思います。しかし、一度落ちこぼれてしまうと、「勉強が楽しい」という気持ちや自信を喪失してしまいます。
適切なサポートがあれば、辛い経験を将来の糧にすることができます。しかし、十分なサポートがない場合、自信を喪失する経験は生徒様に強いショックをもたらし、長期的にもアイデンティティを揺るがす経験につながってしまいます。
②学校が楽しくなくなる
授業で「理解できない」「ついていけない」と感じることで、学校に行くこと自体が苦痛になってしまうことは十分考えられます。周りの人と自分を比較し、落ち込んでしまうこともあり得るでしょう。
そうすると学校にいることがストレスになり、行きたくないと感じるようになるかもしれません。
③大学受験への意欲が保てなくなる
自信をなくし、学校が楽しくなくなることで、将来に対しても良いビジョンを描けなくなることがあります。
その結果、大学への進学意欲を持ちづらくなります。
本来は、大学進学は積極的に環境を変えるチャンスです。
しかし、「今この瞬間」がうまくいっていないと、それがずっと続くのではないかという不安に苛まれてしまうのです。
「落ちこぼれたかも」「ついていけない」と感じたら試したい4つの対処法
「授業についていけない」という状況を防ぐためには、どのような勉強が効果的なのでしょうか。
ここでは、「落ちこぼれる」状況を防ぐために日頃からできることを、4つご紹介します。
①教員やスクールカウンセラーに相談する
進学校の場合、例えば有名大学で数学を専攻していた人が教えている、ということがあり得ます。
そのため、授業でわからないことがあった場合は、まずは先生に聞くのが最も効果的です。
先生にとっても「今日の授業は生徒にとって難しいのか」と気がつくきっかけになり、今後、授業のテンポを落として解説を具体的にしてくれる可能性があります。
全体的に学習につまずいている場合は、担任の先生に相談しましょう。学習習慣のアドバイスなど、落ちこぼれた状況を打開するための手助けをしてくれます。
また、担任の先生に間に入ってもらいながら、各教科の先生と相談ができるというメリットもあります。
身体面・心理面での不安感がある場合は、保健室の先生・スクールカウンセラーに相談するのも一つの手です。
一見、学習とは関係ない存在のように思えますが、様々な形のサポートを提案してくれると思うので、ぜひ相談してみてください。
②試験勉強に力を入れる
試験は、「今まで習ったこと」を総合的にチェックし、どこに穴があるかを確認することができる、とても重要な機会です。
この機会を活用して、「わかったつもりになる」ことを防ぎましょう。
基礎は授業中であまり解説されないため、わからない部分もなあなあにできてしまうことがあります。そして、その積み重ねで、いつか大きな落とし穴に遭遇してしまいます。
これを防ぐために、定期試験のタイミングで知識が定着しているかをしっかりと確認しましょう。
③外部の模試を活用して、自分の実力を把握する
進学校はカリキュラムが独特であることが多く、また、周囲の学生の成績も良いです。
そのため、学校の試験だけだと、自分にどの程度の実力があるのか確認できず、モチベーションが上がらないことがあります。
こういうときに役立つのが、外部の模試です。模試を受験して、より一般性・客観性の高い形で自分の実力を測ることで、また違った角度で勉強のモチベーションを保つことができます。
④個別指導塾や家庭教師に頼る
落ちこぼれた期間が長い場合、どうしても学校だけでは十分なサポートができないこともあります。
そのような時は、個別指導塾や家庭教師を活用しましょう。
外部のサービスを利用する際は、事前に大まかな目標を立ておくと良いです。例えば、
「大体いつくらいまでに授業についていけるようになりたいのか」
「今はどこがわかりづらいのか」
を整理した上で、どの塾が良いか/どの家庭教師に依頼するのが良いかを検討しましょう。
また、進学校の場合、授業内容が他の学校と比べて難しい可能性が高いため、事前にその旨を塾・家庭教師側にも伝えた上で、確かな実力がある教師を選択することをおすすめします。
可能であれば、通っている学校を卒業した教師だと、生徒様の事情も理解でき、ロールモデルとして生徒様を導くこともできるので、進学校の落ちこぼれ指導として最適です。
親ができるサポート|子供が「落ちこぼれているかも」と感じたら
実際に「授業についていけない」という状況が発生すると、どうしても焦ってしまいますよね。生徒様ご自身も不安になるでしょうし、保護者様も不安になるかと思います。
ここでは、「授業についていけない」「落ちこぼれてしまったかも」と感じた際に保護者様にできることを、4つご紹介します。
①どのような心構えでいるべきか
「子供が落ちこぼれてしまったかも」と感じても、保護者様は、生徒様の前ではどんと構えていましょう。
生徒様にとっては、学校が生活のほぼ全てです。特にこれまで勉強を頑張ってきた生徒様であるほど、強いショックを感じていると予想されます。
保護者様は、そんな生徒様にとって、学校以外の世界を見せてくれる貴重な存在です。大学や社会では今と違う生活が待っていることを、保護者様自身がイメージしましょう。
保護者様は、生徒様にとって最も身近で信頼できる大人です。生徒様にとって話しやすい雰囲気を作り、生徒様を信頼していること、そして他にも様々な世界があることを伝えましょう。
②生徒様から相談された時の対応
生徒様から悩みを話してくれることは、とても貴重なことです。保護者様のことを信頼しているからこそ、不安を打ち明けることができたのです。
そのため、まずは「話してくれたこと」への感謝を伝えましょう。
「話してくれてありがとう、〇〇が思っていることを聞けて嬉しかった」
「話しづらかったかもしれないね、でも話そうと思ってくれたことがすごく嬉しい」
ときちんと言葉にすることで、生徒様も「これは話していいことなんだ」と理解することができます。
落ちこぼれた状況を乗り越えるには、保護者様の協力が不可欠です。生徒様との信頼関係を構築し、解決策を一緒に考えていく姿勢を見せましょう。
③保護者様から切り出す対応
保護者様から話を切り出す場合は、少し対応が難しくなります。まず、「落ちこぼれても対策はいくらでもある」と前向きな気持ちを保護者様が持ってから、声をかけるとスムーズです。
切り出し方は、例えば、
「授業はどう? 難しい?」
「今回のテストは苦戦してたね。どの辺が難しかった?」
などがオーソドックスです。ポイントとしては、保護者様の方から「難しい」という選択肢を提示することです。
「授業はどう?」だけだと「大丈夫」と返される可能性が非常に高いです。
一方で、「難しい」と選択肢を提示することで、「難しいっていう答えもありなのか」という前提が生徒様にも生まれ、より具体的な返事をしやすくなります。
生徒様が話したくないようなら、「もし話したくなったら、いつでも聞くからね」と伝えると、次に繋げることができます。
④解決策を一緒に考える姿勢を持つ
相談を受けた後、注意すべきことは「叱る」のではなく「一緒に対策を考える」姿勢を持つことです。
多くの生徒様は、成績が伸びないことを過剰に自分の責任だと感じています。そこで保護者様が叱ってしまうと、「自分のせいだ」という思い込みに拍車がかかり、適切に原因を分析できず、解決が遠ざかってしまいます。
また、「一緒に原因を探していく」というスタンスをとることは、保護者様にとっても良い結果になります。
熱心で生徒様想いの保護者様ほど、ご自身を責めてしまいます。そういうときは、気分転換も兼ねて、生徒様と一緒に選択肢を探してみましょう。
「どんな塾があるのか」
「どんな学校に転校できるか」
「落ちこぼれた人で、大学に合格した人はいるのか」
など、調べてみると、思ったより状況が開けていることに気がつきます。何より、困難な状態でも前向きな保護者様の姿勢は、生徒様にとって大切な人生の学びになるでしょう。
⑤家庭教師や塾など、個別支援を検討する
解決策を考える上で、「抱え込む」のではなく「周りに頼る」という選択肢をぜひ検討してみてください。
責任感の強い保護者様や生徒様は、苦しいときに自分たちだけで抱え込もうとすることが多いです。ご家庭様だけで抱え込んでしまうと、生徒様にとってもご家庭が苦しい場になってしまう可能性があります。
私自身も、そのようなご家庭様をたくさん見てきました。むしろ、悩むことは他の人に任せ、ご家庭では楽しい時間を過ごすのが一番大切です。
特に、同じような進学校出身の教師であれば、生徒様の状況にも理解を示し、寄り添うことができます。ご家庭の中で抱え込みすぎず、家庭教師や個別指導塾など、外部の助けも落ちこぼれ対策には効果的であることを視野に入れてみてください。
まとめ|「落ちこぼれたかも」と感じたら一人で抱えず、協力を得て巻き返そう
この記事では、進学校で落ちこぼれないためのポイントや、落ちこぼれてしまったときの対応をご紹介しました。
進学校には、進学校ならではの「授業についていけなくなる」「落ちこぼれやすい」原因がたくさんあります。
しかし、困った際に頼れる先はたくさんあります。学校だけのサポートで足りない場合は、個別指導塾や家庭教師に頼るのも一つの手です。
当会には進学校出身の教師も多数在籍しております。生徒様や学校の事情にも詳しく、生徒様の憧れとなるような難関大学に在籍し、ロールモデルとして良い影響を与えることもできます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
▼当会では、中高生・中高一貫校生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
あわせてチェック|中高一貫校の勉強法を解説
東大家庭教師友の会の特徴
当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
進学校の落ちこぼれ指導が可能な教師をご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。