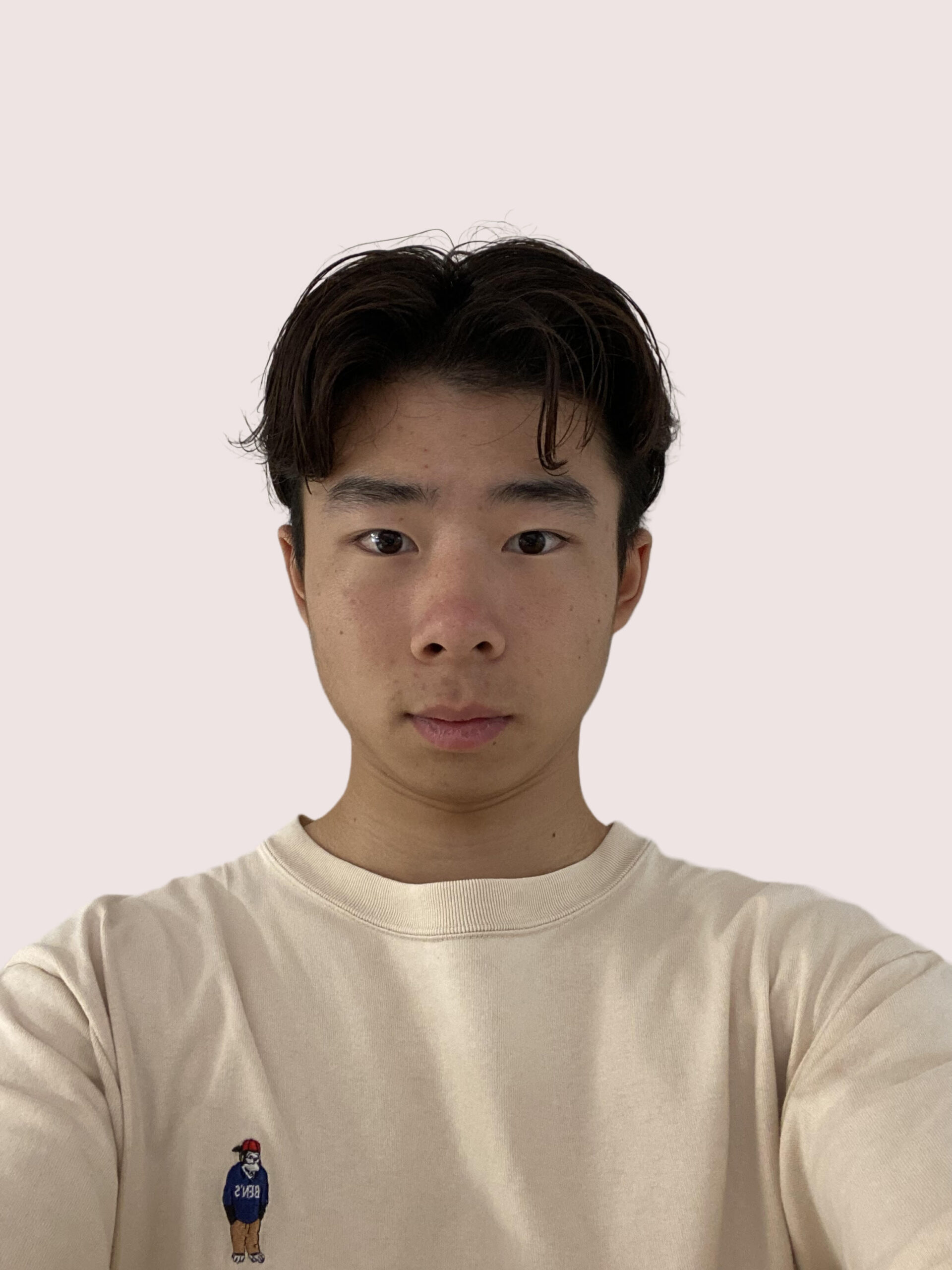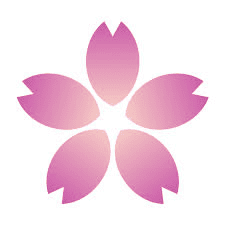2023年 最新入試情報
【入試予告情報】
AO入試
●文化情報学部において、学部が定める出願要件の一部を変更
変更前⇒入学後勉学を継続し、より充実したものとするため に、「英語」、「国語」、「数学」のいずれかの学習成績 の状況が4.0以上であることが望ましい。
変更後⇒入学後勉学を継続し、より充実したものとするため に、「英語」、「国語」、「数学」のいずれかの学習成績 の状況が4.0以上である者。
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制)
●経済学部自己推薦入学試験において、第二次選考における選考方法を変更
筆記試験(英語)を廃止し、各種英語資格試験の成績(スコア)を証明する書類の原本(オリジナル)の提出を求め、当 該出願書類および筆記試験(小論文)、面接とあわせて総合的に判断し、合格者を決定します。
●文化情報学部推薦選抜入学試験において、出願要件を追加
従来の出願要件に加え、以下の要件を追加します。
『高等学校の第3学年1学期末(2学期制の高等学校は、第3学年前期末)までの「英語」、「国語」、「数学」のい ずれかの学習成績の状況が4.0以上である者。』
※追試の有無など、新型コロナウイルスの影響等による変更が行われることも考えられるため、大学からの情報に注意してください。>同志社大学HP
【各学部各教科配点】
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 外国語 | 200 | 200 | ||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 小論文 | 200 | 200 | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 外国語 | 200 | 200 | ||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 英語/口頭試問 | 100 | 100 | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/数学/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
|
| 国語 | 200 | 500 | ||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 数学 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー |
||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民から1科目
|
|
| 国語 | 200 | 700 | ||
| 数学 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※地歴/公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
国語/地歴/公民/数学/理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
公民/数学/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 | ||
| 地歴 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 公民 | 100 | |||
| 数学 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
国語/地歴/公民/数学/理科/外国語から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | 地歴/公民から1科目 |
|
| 国語 | 200 | 800 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
国語/地歴/公民/数学/理科/外国語から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 小論文 | 200 | 200 |
||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 小論文 | 200 | 200 |
||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/数学/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
英語:300点満点換算をさらに500点満点に換算
|
|
| 国語 | 200 | 800 |
||
| 数学 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 外国語 | 500 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
英語:300点満点換算をさらに200点満点に圧縮
|
|
| 国語 | 200 | 700 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/数ⅡB/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数ⅠA | 100 | |||
| 数ⅡB | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | 地歴/公民から1科目 |
|
| 国語 | 200 | 700 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/数ⅡB/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
英語:200点満点を300点満点に換算、のちに250点満点に圧縮
|
|
| 国語 | 200 | 650 | ||
| 数ⅠA | 100 | |||
| 外国語 | 250 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 数ⅡB | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | 地歴/公民/数学から1科目 |
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) |
|
| 国語 | 100 | 200 |
||
| 理科 | 100 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 数/外 | 各150 | 300 | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 700 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ※理科は物理、化学、生物から2科目選択 |
|
| 数学 | 200 | 600 |
||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー |
||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ※理科は物理・化学、各100点 | |
| 数学 | 200 | 600 |
||
| 外国語 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ※理科は物理・化学、各100点 |
|
| 国語 | 200 | 800 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ※理科は物理、化学、生物から、2科目選択。 |
|
| 数学 | 200 | 600 |
||
| 外国語 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 | ※理科は物理、化学、生物、地学から1科目選択。 |
|
| 数学 | 200 | 600 |
||
| 外国語 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
国語/地歴/公民/数学/理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 100 | 400 |
||
| 数学 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民から1科目
|
|
| 国語 | 100 | 600 |
||
| 数学 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
国語/地歴/公民/数学/理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
書類審査あり。
|
|
| 国語 | 100 | 400 |
||
| 数学 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
地歴/公民/数学/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
| 共通テスト | 備考 | |||
| 科目 | 配点 | 満点 |
※理科は基礎2科目または発展1科目から選択
数学/理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
地歴/公民から1科目
|
|
| 国語 | 200 | 600 |
||
| 数学 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 無し | ー | ー | ||
2023年同志社大学
入試傾向と対策ポイント
英語の傾向・対策
【傾向】「王道シンプル!長文読解が最大の鍵!」
同志社大学の英語は、長文読解力がとにかく重要です。大問3つの内、2つが長文読解。そして、残り1つの大問も他大学の中問レベルの長さの会話文読解が出題されるのが定番の形です。
この点からも長文読解力が顕著に大事になってくることがわかります。そして他大学の英語の問題と比較しても、非常にシンプルで単純な出題形式となってきます。
しかしながら、同志社大学は西日本でも最高難易度の私立大学ということで、難易度は突き抜けています。単語・文法・構文・精読・速読といった英語の全ての要素を詰め込み、出題してくる長文は、いずれも良問中の良問です。
全ての知識をバランスよく鍛えて、フルに動員する必要がある長文読解のため、一筋縄ではいかないでしょう。しかしながら、「捨て問」などはほとんどなく、実力が如実に出る入試問題でもあります。努力が報われやすい大学ですので、愚直に勉強をする姿勢が問われていると言っても過言ではないでしょう。
【対策】「実力の底上げ必須!速読も大事」
同志社大学の英語は長文が中心ということで、単語・文法・構文・精読・速読といった英語の全ての実力を底上げする必要があります。小手先のテクニックなどで解ける問題は少ないです。その分、特殊な勉強をする必要はないので、普段からしている勉強を地道にしていきましょう。
英単語の勉強は難関用の単語帳ではなく、一般的な単語帳を隅から隅まで覚えれば対応可能ですし、文法も高校で扱う英文法の内容を完璧に理解出来れば問題ありません。そういった基礎をとにかく抜かりなく勉強し、万全の土台を築きあげましょう。その先に長文読解力は養われます。
もちろん、多読で長文に慣れたり、読解の勘所を掴む訓練も必要なのですが、同志社大学の英語はとにかく時間もタイト。そのため「速読」の訓練も行う必要があるでしょう。「速読力」を鍛えるにはとにかく音読が効果的です。音源がついている長文問題集を購入し、一度解いた長文問題を繰り返し、繰り返し音読しましょう。
ネイティブスピーカーの速度で文章を理解できることにも繋がりますし、何より後置修飾があったとしても、返り読みをしない訓練になります。そういった勉強法をしておけば「飛ばし読み」などをせずとも、全ての文章を読み、鋭い解答を連発出来ます。
国語の傾向・対策
【傾向】「意外に平易で高得点勝負必至」
同志社大学の国語は、意外にも簡単です。一般的な受験生の声を聴くと、「同志社だから国語も難しいだろう」「自分には解ける気がしない」などと言う方も多くいらっしゃいますが、そういった先行的なイメージに惑わされてはなりません。
同志社大学の国語は現代文2問に、古文が1問と関関同立の中で比較をしても、簡単な方ですし、非常に解答もスムーズにいきます。
同志社大学は英語の読解も、いかに当たり前のことを当たり前にこなすか、といったことを問われている側面が強いですが、国語も似た傾向があります。国語の文章自体はそこそこ長いものの、択一式の問題数は10問前後と多くありません。選択肢ごとの違いも大きいので、そこまで困らないでしょう。
唯一難儀なのは各大問に一つ用意されている記述問題。全体を鳥瞰して、要素をつまみあげる解答であることが多いので、その点で差がついてきます。
【対策】「択一よりもとにかく記述対策を」
同志社大学の国語は難易度がそこまで高くないことは前述の通りです。特に択一の問題は、国語が得意でない方でも解きやすく、満点が当たり前の世界。
択一問題への対策はそこまで比重を高くしなくても良いというのが本音です。センター試験形式の文章を多読する、標準的な問題集一冊を完璧にする、といった王道の勉強が最も近道になってくるでしょう。
語彙問題・漢字問題も出題されます。配点こそ少ないのですが、高得点勝負が必至の同志社大学の国語では、落とすと大きな差となってきます。学校などで配布される、漢字が網羅された参考書と語彙の参考書一冊ずつはしっかりと頭に叩き込んでおくことが必要です。
そして、同志社大学の国語で最も肝になってくるのは、記述問題です。ここで国語の差が決まると言っても過言ではなく、日ごろから意識をして対策をしておく必要があります。そしてこちらの記述の特徴として、「全体を通して、内容をまとめられるか」という能力を図る問題が多い事が挙げられます。
一部分をつまんでの説明はあまり見かけないので、「全体を通して、まとめる」能力をつけるには要約の練習が最も重要でしょう。
数学の傾向・対策
【傾向】「数学Ⅱ・Bの比重高めで難解」
同志社大学の文系数学は、関関同立を中心とする西日本の私立大学ではトップクラスの難易度を誇ります。大問は三つで、時間的にもタイトです。大問一はセンター試験などでも定番の小問集合の形で、答えだけを導き出せば良いのですが、大問二・三の記述式の問題が難解です。
同志社大学の数学で出される問題は、小手先の知識だけでなく、様々な数学の知識や計算力、スピード感を総合的に問われる問題で、一筋縄ではいきません。分野としても幅が広く、付け焼刃の勉強では通用しませんし、文系の学生に課す入試問題としては、やはり少し敷居が高いところがあるでしょう。
しかし、同志社大学の数学の選択問題には得点調整の概念があり、日本史や世界史と比較をすると、得点が相対的に上昇することもありますので、しっかり勉強をすればお得な科目とも言えます。また、数学Ⅱ・Bからの出題が目立つという傾向もありますので、そちらを中心に学習されるのも効率的だと言えるでしょう。
【対策】「難解な融合問題への対策も必至」
同志社大学の文系数学はレベルも非常に高いことから、しっかりとした対策をしておくことが最も大切です。大問一で出題される小問集合はセンターレベルの対策で事足ります。教科書の内容をしっかりと把握し、教科書準拠の問題集などを何周も解くことで理解が深まります。
厄介なのは大問二・三の記述問題です。こちらはまず記述問題ということで、他の大学では必要とされない証明力や記述力などが必要となってきます。日頃の勉強から、途中式を意識する、計算のロジックを頭の中で説明できるようにしておく、などの訓練を意識的にしておくことが最も大切です。
そしてこれらの大問では、融合形式の問題が頻発するのも大きな特徴です。色々な分野や単元を横断的に出題してくる形式は同志社大学の数学の名物といっても過言ではありません。
そのため苦手な単元は絶対に潰しておく必要があります。また日頃の勉強でも、別の単元や他の解法を自分で意識する、広い視野で問題について向き合う、といった姿勢が肝心になってきます。
そして最後にですが、時間的にもかなりタイトなため、正確かつ高速に計算が出来る計算力も養っておく必要があります。こちらは毎日の演習の積み重ねが物を言います。総合的に数学の力を底上げしておく必要があるでしょう。
日本史の傾向・対策
【傾向】「記述と記号がまんべんなく出題される」
同志社大学の日本史は、記号問題と記述問題がまんべんなく出題される傾向があります。
他の大学では、記号問題だけの出題をしてくる大学もありますが、さすが同志社大学といった感じで、総合的な力を問われてきます。記述問題・記号問題共に難易度はやや高めで、一筋縄ではいかないでしょう。また出題範囲も、古代から近代までと幅広く、ヤマを張る勉強法や付け焼刃の勉強が通用しづらい仕様になっています。
そういった全般的な勉強を求めてくる一方で、ディープな一つのテーマだけを取って1つの大問を作り上げてくることも。かつては「倭の五王」だけで1つの大問を出題してきたこともあるように、警戒が必要です。
そういった時は全体的な得点も下がるのですが、やはり通史を見て、抜かりなく「広く・深い」勉強を求めてきている印象があります。
【対策】「「広く・深い」勉強が必要」
同志社大学の日本史は出題範囲も膨大で、ディープな大問を丸ごと出題してきたりすることもあり、「広く・深い」勉強が必須になってきます。しかし、その分、特殊な勉強や同志社大学専門の対策などは必要なく、愚直な勉強が必要になってきます。
そういった王道の日本史力を築くためには、「インプット→アウトプット」の鍛錬が最も大事です。
インプットとは、講義や授業などを聴いて、知識を頭の中に入れることです。同志社大学では整序問題なども出題されるので、流れと因果関係を意識して、歴史を覚えていくことは最も大切です。画一的な暗記のみではとても追いつかない膨大な量ですので、頭をフルに活用をして、効率的に覚えていきましょう。
そして、流れをインプットすれば一問一答形式での勉強が最も効果的。講義のお話を骨組みとして再現しながら、細部の肉付けをしていくイメージです。
一問一答は受験最終盤までお付き合いしていく必須アイテムで、何周も何周も回しましょう。即答できるようになった問題にはチェックを入れて、もう解かないようにするとスピーディーで良いです。
そして知識の土台を築けば、後は問題演習へ移行するのみです。市販の問題集を解くのも良いですが、同志社大学の過去問を手に入る分だけ全て解くのが効率的です。レベル的にも知識的にもぴったりの教材となりえますし、それらを解いた上で、流れがあやふやなところはインプットに立ち返る、といった繰り返しで、どんどん苦手を潰していくといいでしょう。
世界史の傾向・対策
【傾向】「高得点勝負必至!質より量で」
同志社大学の世界史は、標準レベルの難易度だと言うことが出来ます。過度に難しい問題は出題されず、オーソドックスな勉強をどれだけ愚直に積み重ねてきたかということが問われてくる受験問題です。
教科書レベルの内容をしっかりと繰り返して学習をしておくことが最も重要になってきます。形式としても記述・マーク式の問題のどちらからも出題され、漢字などについてもしっかりと抑えておく必要があるでしょう。
大問ごとの特徴としても、全体的な出題が目立ちます。全体を通して、幅広く深堀して学んでいきましょう。しっかりと勉強をしてきた方にとっては高得点を取ることもそこまで難しくなく、受験生のレベルが高い同志社大学の入試ですので、高得点勝負での決着になることもあります。
得点調整などによって、素点よりも点数が下がることがほとんどですので、なおさら不用意なミスは許されません。
【対策】「教科書レベルの知識の完全習得が最優先」
同志社大学の世界史は「広く・深い」勉強が必須になってきます。しかし、その分、特殊な勉強や同志社大学専門の対策などは必要なく、愚直な勉強が必要になってきます。難易度としてもそこまで難しくないので、教科書レベルの内容を完璧に抑えることが合格への最大の近道となるでしょう。
教科書が大事だと言うことは、学校や塾などでの講義をおざなりにしてはならないことです。しっかりと流れや因果関係を意識したインプットでまずは土台を築きましょう。
インプットをした後は、教科書準拠の穴埋め問題集や、東進ブックスから出版されている一問一答などを何周も繰り返して学習をしてきましょう。一問一答は、インプットとアウトプット、どちらの訓練の要素も兼ね備えており、問題演習へ移るための手段として最適です。流れや因果関係を抑えた上で、単語を暗記できれば、あとは同志社大学の入試本番を見据え、どんどん問題集を解いていきましょう。
政治経済の傾向・対策
【傾向】「基礎~標準まで幅広い難易度」
同志社大学の政治経済は、過去問の傾向から、基本的に3題構成です。最近では、政治分野1題、経済分野2題の構成や、政治分野1題、経済分野1題、政治・経済分野の要素を含んだ時事問題1題の構成が見受けられました。
「日本史」や「世界史」「現代社会」に関連した出題もあり、全体としては国民生活分野や国際関係などからの出題がある年もあります。同志社大学の政治経済の出題では、基本的な問題ももちろんありますが、計算問題や時事問題などの難易度の高い出題が見受けられるため、しっかりとした対策が必要です。
【対策】「標準レベルの問題は解けるように」
同志社大学の政治経済では、時事問題が出題される事が多いため、普段からニュースに気を配るようにしましょう。難易度は標準レベルのものから難解なものまで幅広いので、間違えたものは解き直しをしっかり行う事で標準レベルの問題は確実にとれるようにしましょう。
同志社大学の政治経済の入試問題数はそこまで多くないので、時間との闘いに慣れておくべきというわけではありませんが、実際の形式に慣れるためにも過去問対策は必須です。他にも、日本国憲法関連の問題や社会保障や金融の問題もあるので、資料集を併用した学習を進めましょう。
物理の傾向・対策
【傾向】「計算問題の比率が高め」
同志社大学の物理は、大問が3題出題されます。入試問題の傾向は、毎年一定でワンパターンそれぞれ問題文のボリュームがあり、読解しながら問題に解答していくスタイルとなります。
計算問題の比率が高く、複雑な計算が必要な問題も出題されます。領域を問わず典型問題の解法は必ずマスターし、正確に素早く解答することが求められます。
【対策】「基本の法則を固める」
全科目に通ずることですが、同志社大学の入試問題の傾向が毎年一定でワンパターンな場合が多いので、過去問演習をして傾向をしっかりつかむのが良いでしょう。出題形式がやや独特なことから、周到に準備して慣れておくことが求められます。
また、基本的な公式や重要項目を押さえ、基本法則を理解することを徹底しましょう。力学ならニュートンの第一・第二・第三法則とフックの法則、力学的エネルギー保存則、万有引力の法則などで、電磁気学なら電気容量の保存などです。
化学の傾向・対策
【傾向】「難問は少ない」
同志社大学の化学は、大問が3題出題されます。典型的な計算問題や重要な化学式、化学反応式、組成式、構造式などが数多く出題されます。マークシート方式と記述式の両方がとられ、問題数も多めです。
難易度に関してはそれほど高くないので、点を落とすと差がついてしまう教科ともいえます。
【対策】「理論理解を大事に」
考え方を理解をしているかしていないかで差が出るような問題が多いです。まずは基礎事項を覚え、論理をしっかり理解する事を重要視しましょう。
具体的な対策としては、同志社大学の記述式問題に重点を絞ることが重要です。教科書や問題集に記載されている重要な化学式やイオン式などは、全て正確に記述できるように準備しましょう。その際には暗記するだけでなく仕組み・構造をしっかり理解しましょう。
問題量がやや多いことから、時間配分を意識しながら素早く解答することがポイントになります。また、弱点を作らず標準レベルの問題は確実に解答できるよう基本知識を身につけることを心がけましょう。
生物の傾向・対策
【傾向】「難易度は標準的」
同志社大学の生物は、論述問題と計算問題のどちらも出題されるので総合的な対策が求められます。出題は全分野から行われ、浅い理解では高得点を望めない内容になっています。
標準的な難易度と言えますが、出題分野の予想的絞り込みは難しいので、幅広く対策を進めるようにしましょう。
【対策】「計算・論述への対応力を」
まずは短答式の問題をほぼ確実に正答できるだけの知識を入れましょう。全分野、教科書にあることをきっちり頭の中に入れる必要があります。また、同志社大学の計算問題には根気が必要です。特に有効数字には注意しましょう。
全体的に見て標準的な難易度と言えますが、同志社大学の実験考察の問題には注意をしましょう。過去問演習で問題の出され方、回答の仕方について詳しく見ておくといいです。また、正誤問題で一部、発展的な内容も出題されるので問題集で演習量を積み対策しましょう。
大学受験対策をご検討の方へ
関西で大学受験指導ができる家庭教師のご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
大学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会【関西】の特徴
当会には、京大生約2,200名、阪大生約1,800名、神戸大生約900名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
オンラインでの指導も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る