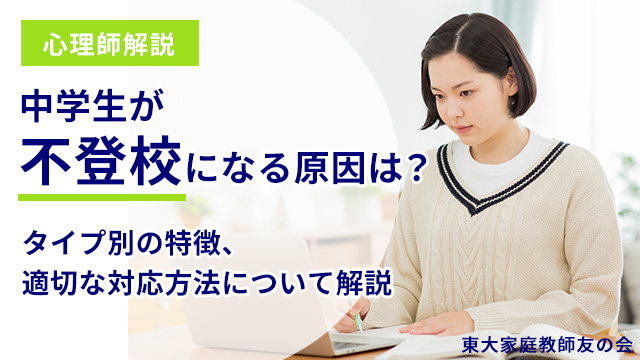1. 現在の中学生の不登校の情勢

はじめに近年の不登校の状況について紹介していきます。
保護者様が中学生の時と比べ、不登校問題は深刻化し、大きな社会問題となっています。具体的な数値を参考にしながら解説していきます。
①中学生の不登校は増えている
文部科学省による調査結果(注1)によると平成22年度には約9万7千人の不登校生徒が存在していました。
当時は全国に約350万人の中学生がいたので、不登校生徒の割合は2.73%となっていました。
100人に2~3人という計算になるので、1学年に数人といったイメージになると思います。
ところが令和4年になると中学生全体の人数は30万人程度減少したにもかかわらず、不登校生徒の人数は倍の約19万人となっています。
割合としては約6%となりますので、1クラスに1~2人いることになります。
わずか12年間でここまで増加した背景には何があるのでしょうか。
②不登校の生徒が増えている理由
不登校が増加している理由はまだ解明されていない部分が多いですが、様々な要因が複雑に関係していると言われています。
「核家族化が進み、両親が共働きという家庭が増えてきたため家族でのコミュニケーションの機会が減ったため」といった考え方もあれば、「不登校がメジャーになり、『学校に行かない』という選択肢を多くの子どもがとるようになったため」という考え方もあります。
また、文部科学省(注2)によると新型コロナウイルス感染症が不登校に大きく関係しているとし、
『新型コロナウイルス感染症によって学校や家庭における生活や環境が大きく変化し,子供たちの行動等にも大きな影響を与えていることがうかがえる。』、『コロナ禍による生活環境の変化で生活リズムが乱れやすい状況や,学校生活において様々な制限がある中,登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられる。』
といった見解を示しています。
このことは統計データでも明らかになっており、毎年5千人規模で不登校生徒が増加しており、令和2年の不登校生徒数は約13万人でした。
それに対して翌年の令和3年には約16万人と急激に増加しています。
それだけ新型コロナウイルスが子ども達に与える影響が大きかったということですね。
2. 中学生が不登校になる原因は?

不登校になってしまう原因は生徒様によって異なります。
原因がわからなければ対策を立てることもできないため、「どうして学校行けないのか」「学校に行けなくなった理由はなにか」について詳しく確認する必要があります。
ここでは文部科学省の研究データ(注1)における中学生の不登校理由のトップ3について解説していきます。
①無気力・不安
公立中学校において不登校になってしまう理由の中で一番大きなものが「無気力・不安」であり、不登校生徒の52%が「無気力・不安」のために不登校になったと回答しています。
中学校は小学校と異なり学習内容が高度になるだけでなく、学校全体の生徒数の増加、先輩後輩といった人間関係の複雑化が同時期に生じ、対処しなければならないため、人関関係作りが苦手だったり、不安感が強かったりする生徒様の場合には大きなストレスがかかってしまいます。
そんな生活が続くことで、つらい現実から逃げ出したくなり、何事に対しても無気力になる、もしくは何をするにも不安に感じ動けなくなってしまうといった状態へと発展し、不登校になってしまうと考えられています。
②生活リズムの乱れ・あそび・非行
次に多い理由として「生活リズムの乱れ・あそび・非行」が挙げられており、不登校生徒の10.9%が当てはまるとされています。
生活リズムの乱れは新型コロナウイルスが大きく関係していることは解説しました。
臨時休校やリモート授業になったことで人間関係が希薄になることで、学校以外の居場所を求めるようになり、非行グループに入るなど学校や家庭から離れてしまうといったことが考えられます。
また時間的な余裕も生まれたため、ゲームに時間を費やしすぎてしまう生徒様もいらっしゃいます。
最近はボイスチャットで会話をしながら楽しむことのできるゲームが増え、夜遅くまで起きていることで昼夜逆転し、そのまま生活リズムを戻せずに不登校になるケーズも少なくありません。
③いじめを除く友人関係をめぐる問題
SNSが発達した昨今では家にいながら友達とつながることができます。
一昔前までは教室や放課後にしか会えませんでしたので、交友関係を深めやすい時代になったとも言えます。
しかしいつでも友達と連絡を取れることはいいことばかりではありません。
常にメッセージの通知を気にする、自分がいないところで悪口を言われる、自分の会話ややり取りの内容をほかの人やネットに共有されてしまうなど、友人関係が複雑化し、子ども達に悪影響を与えている側面も存在しています。
そうしたことから友人関係でトラブルを起こし、学校に居場所をなくして不登校になってしまう場合もあります。
この場合は人の目に触れない場所でのやり取りのため、大人がトラブルに気づくのが遅れてしまいます。
3. 中学生の不登校の特徴

次に中学生の不登校の特徴について紹介していきます。
主に公立中学における不登校の特徴について解説していきます。私立中学における不登校については別記事にて解説しておりますので、是非そちらも参考にしてください。
▼私立中学の不登校に関する詳細は以下ページをご覧ください
①1年生で爆発的に増える
厚生労働省の調査結果(注1)では小学6年生では3万人ほど不登校児童が存在しますが中学1年生では5万人ほどの不登校生徒が存在しています。
このような現象は「中1ギャップ」と呼ばれています。小学校と中学校の環境の差が子ども達の不適応を引き起こしていると考えられています。
しかし文部科学省 国立教育政策研究所(注3)によると必ずしも中1ギャップが存在しているとは言い切れないとしています。
もともと不登校の可能性のあった児童が中学生になって問題が顕在化したにすぎないため、「中学生になったから不登校になった」と安易に考えることは危険であるという見解を示しています。
小学校と中学校の連携強化や小学校で起きている問題を小学生のうちに解決することが重要としています。
②不登校が長期化しやすい
また、前年度から不登校が継続している割合についての調査結果は以下の通りになっています。
・小学6年生から引き続き不登校になっている中学1年生 約5万人(約30%)
・中学1年生から引き続き不登校になっている中学2年生 約6万7千人(約56%)
・中学2年生から引き続き不登校になっている中学3年生 約6万6千人(約69%)
上記の結果はあくまで総数なので、詳細な部分についてはわかりませんが、中学生で不登校になった場合は半数以上が1年以上学校復帰できていないということが示されています。
一度学校から離れてしまうと、なかなか復帰するタイミングがつかめずズルズルと不登校状態を続けてしまうケースが多いことが分かりますね。
③反抗期の時期と重なる
反抗期は思春期の生徒様に見られる時期のことで、親や教師などの大人に対して反抗的になる時期のことです。
小学校高学年から中学生にかけて反抗期になる生徒様が多いです。
反抗期については別のページでも解説しているため、そちらも是非ご覧ください。
学校での嫌なことや悩みごとがある際には保護者様に相談し、学校と協力しながら問題解決に向かうことができますが、
反抗期になると保護者様とのコミュニケーションを避けたり、自分の思いを話さなくなるため、保護者様としては生徒様が何を考えているのか掴みづらく、学校復帰が難しくなり、不登校が長期化する傾向にあります。
▼中学生の反抗期の詳細は以下ページをご覧ください
「【心理士解説】反抗期の子どもへの適切な関わり方とは?勉強への促し方もご紹介!」
4. 保護者様がよく抱える悩み

生徒様が不登校になると保護者様は様々な感情を抱きます。
「どうして我が子が」「我が子に限って…」そんな思いがあふれて途方に暮れてしまうでしょう。
ここでは不登校の生徒様を持つ保護者様がよく抱える悩みについて紹介していきます。
①育て方が悪かったから不登校になったのか
中学生における不登校は全体の6%ですので、少数派になります。
大多数の生徒様は学校に通えているため、「育て方が悪かったのかな」「私達のせいで不登校になっちゃったのも」と考えてしまい、自分を責めたくなりますよね。
確かに家庭環境は不登校を引き起こす要因の1つに挙げられます。
しかしそれは子どもに関心が無い、または逆に関心が強すぎて過保護になっている場合や離婚・失業など家庭状況が不安定になっている場合です。
そのためすべての不登校の子ども達が家庭環境に問題を抱えているわけではありません。
これまでの生徒様への関わりを振り返り、もしコミュニケーションの時間が取れていないと感じたのなら、
生徒様の好きなことについて話を振ってみたり、外出に誘ってみたりする程度でも十分ですので、今後は意識的に時間を作ってあげてください。
②このまま不登校が続くと高校進学はどうなるのか
また、生徒様の進路についても不安ですよね。
「中学生で不登校になると内申点が悪くて高校進学できないのでは?」「引きこもるようになってずっとこのままなんじゃないか」そんなことが頭をよぎってしまうと思います。
ですが文部科学省の調査によると不登校中学生の約20%が学校復帰を果たし(注1)、また不登校生徒の5年後の状況を調べた調査(注4)では約80%が就職もしくは進学、または両方をしているというデータもあります。
公立の高校に行きたい場合は出席日数や学力の遅れが壁になる場合もありますが、現在では週に1日学校に行けばよいとする高校や、オンラインで好きなときに授業を受けることのできる学校もありますので中学卒業後にどこにも行けないというケースはだいぶ少なくなりました。
もちろん何の対応もせずにこのまま不登校問題を放置してしまうと悪化する可能性はありますが、適切な対応や進路選択を行うことで、生徒様の将来は十分ひらけたものになりますので安心してくださいね。
▼中学生の不登校の詳細は以下ページをご覧ください
5. 不登校の中学生に対して、してはいけない対応

ここまで不登校についての概要や保護者様が抱える悩みについて紹介していましたが、ここからは不登校の中学生への関わり方について解説していきます。
まずは不登校の中学生に対して、してはいけない対応について、説明していきます。
①意思疎通の機会を減らす
不登校の中学生は反抗期も相まって、保護者様の話を聞こうとしないかもしれません。
だからと言って「勝手にしなさい!」「もうしらない!」と生徒様とのやり取りを絶つ行為はNGです。
言葉で拒絶しなくても態度で出てしまうケースがあります。
子ども達は敏感で、自分に対してマイナスな感情を持っている際にはすぐに気づいて心を閉ざしてしまいます。
自分の態度はなかなか自分では気が付くことができないので、家族同士で確認し合えるといいですね。
保護者様は不登校解決のためのキーパーソンです。
生徒様の言動にイライラしてしまう気持ちはよくわかりますが、ひとまずの飲み込み、生徒様との開かれた関係作りを意識してください。
②保護者だけで問題を抱え込む
不登校の生徒様と保護者様の方を数多く見てきましたが、なかには「不登校は家庭内の問題」「よそ様に迷惑はかけられない」と外部機関を頼らず自分達だけで何とかしようとするご家庭があります。
保護者様の意向ですので無理強いはできませんが、色々な機関と連携を取った方が多角的な目線での支援ができますし、生徒様と保護者様の負担も減ります。
また、不登校には家庭環境に問題があるケースがあることは紹介しましたが、そのほかにも担任の先生と相性が悪いなどといった学校環境に問題があるケースと、適応障害や対人関係構築の苦手さなど生徒様自身に要因があるケースがあります。
これらの場合は保護者様だけでは対応が難しい場合が多いです。
教育センターや、適応指導教室など不登校の生徒様をサポートする機関は数多く存在しますので、ぜひ活用してください。
6. 不登校のタイプ別の対応方法について

最後に不登校の中学生に対してどのように関わればよいかについて解説していきます。
冒頭でも触れた通り、様々な理由・背景から不登校が生じますので、個別の対応が必要になります。
そこで、先に挙げた不登校の原因(「無気力・不安」、「生活リズムの乱れ・あそび・非行」、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」)ごとに対応方法を解説していきます。
①スモールステップで登校を促す
生徒様が気力を失っていたり、不安が強かったりする場合にはすぐに学校復帰することは難しいでしょう。
そこで大切な概念になるのが「スモールステップ」です。
スモールステップとは「目標を細かく設定し、1つずつ達成していくことで最終的な目標にたどり着く手法」のことを指します。
最終的な目標を「学校復帰」とするなら
|
「誰もいない時間帯に昇降口に行ってみる」
|
というところからスタートしてもいいですし、それよりも前段階の
|
「午前中に起きる」
|
といった初歩の初歩からスタートしてもかまいません。
大切なのは少しずつ前に進んでいるという実感を生徒様に持たせてあげることです。
また、最終目標は生徒様が決めた方が良いでしょう。
保護者様としては学校に戻ってほしいと願っているかもしれませんが、生徒様がそう思っているとは限りません。
「学校以外の場所で過ごす」「高校で再スタートする」ことが目標になるかもしれません。
その際は否定せず、保護者様や先生の思いを伝えながら、全員が納得できる部分まですり合わせていけるといいですね。
②規則正しい生活リズム作り
生活リズムが崩れ、夜間に外出したり、遅くまでゲームをしたりしている場合には、生活リズムの改善を図っていきましょう。
とはいえいきなり「早く寝て早く起きる習慣をつけなさい」と生徒様に言ったところでまともに聞いてはもらえないでしょう。
日ごろからコミュニケーションを取り合い、「親は自分の味方なんだな」と思ってもらえるような関係性が必要です。
またルール作りも効果的です。
外出について門限を決めたり、ゲームができる時間を決めたりすることで子ども達の行動をある程度抑制することができます。
この場合も保護者様が一方的に決めるのではなく、生徒様の意見も取り入れながら決めていけるとより効果的です。
③学校以外の居場所を提案する
今の時代、学校だけが子どもの居場所ではありません。
実際にフリースクールや適応指導教室など、不登校の生徒様の活動の幅は広がっています。
またこれらの機関に通うことで出席扱いになることもあります。
子ども達の視野は狭く「学校は必ず行かないといけない」という思いと「学校にいけない自分」という現実の自分の間で苦しんでいることがあります。
そこで「学校がすべてではない」と選択肢を広げてあげることも保護者様にできることの1つです。
また、自宅での学習も出席扱いとする制度が令和元年から始まっています。
手順を踏む必要がありますが、高校進学も含めて進路の幅を広げることに繋がります。
1人での自宅学習が不安なら家庭教師を利用することも方法の1つです。
不安の強いお子さんでも自宅なら安心して取り組むことができますし、より効率的に学習を進めることができます。
まとめ
ここまで中学生の不登校について、現状と、してはいけない対応、不登校のタイプ別の対応方法について解説してきました。
中学生は多感な時期で様々なことを大きくとらえてしまったり、問題を複雑に考えてしまったりと私達からすれば「そんなことで?」と思ってしまうようなことで思い悩んでしまい、不登校へと発展してしまいます。
どんな悩みであれ、子どもを取り巻く大人は決して否定や非難はせず、そっと受け止め問題解決に協力していく姿勢を示す必要があります。
信頼関係を築くことが不登校支援では最も重要なことの1つです。
今回の内容を参考に、子ども達をより良い方向へと導いてあげてください。
▼当会では、不登校の生徒様に対応した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
【脚注】
注1)文部科学省(2023) 令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
注2)文部科学省(2021) 令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果について
注3)文部科学省 国立教育政策研究所(2015) 生活指導リーフ「中1ギャップ」の真実
注4)文部科学省(2014) 「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~
お問合せ・体験授業はこちら
不登校の関連記事
東大家庭教師友の会をもっと知る